重症筋無力症のある人のための仕事選びとキャリア戦略
重症筋無力症とその雇用への影響を理解する
重症筋無力症の症状と分類の概要
重症筋無力症(Myasthenia Gravis)は、自己免疫疾患の一種であり、筋肉の神経と連動する信号伝達が阻害されることで、疲れやすくなり筋肉に力が入らなくなる病気です。
症状は個人によって異なり、軽度なものから重度なものまで幅広いですが、日常生活や仕事において多大な影響を及ぼすことがあります。

眼筋型、全身型、呼吸筋型の症状
重症筋無力症の症状にはいくつかの分類があり、それぞれ特徴的な症状があります。
眼筋型
眼瞼下垂(まぶたが下がる)、複視(物が二重に見える)など、主に目の周りの筋肉に影響を及ぼします。
視覚的な負担が主な問題となります。
全身型
手足や体幹の筋力が低下し、動作全般に支障をきたします。
筋力の低下が全身に及ぶため、仕事や日常生活の多くの場面で影響が出る可能性があります。
また嚥下がうまくできなくなるほか、呼吸に関わる筋肉が麻痺し、呼吸困難を引き起こすことがあります。
生命に関わる可能性があるため、慎重な管理が必要です。
変動する筋力低下と疲労
重症筋無力症の特徴として、筋力の低下が一日の中で変動する点があります。
特に、日中活動が多いと夕方や夜に症状が悪化しやすく、休息を取ることで一時的に回復する場合があります。
こうした特性から、患者は一日をどのように過ごすかを計画的に考える必要があります。
また、慢性的な疲労感も多くの患者が抱える課題です。
筋力が低下するだけでなく、疲労により集中力や持続力が低下することがあり、仕事のパフォーマンスにも影響を与えます。
このため、重症筋無力症の人が自分の症状を理解し、無理なく働ける環境を整えることが重要です。
仕事における制限と配慮事項
重症筋無力症を抱える人にとって、働く上での課題は個々の症状や仕事の内容によって異なります。
適切な職場環境の調整や働き方の工夫が、より安定したキャリア形成に繋がります。
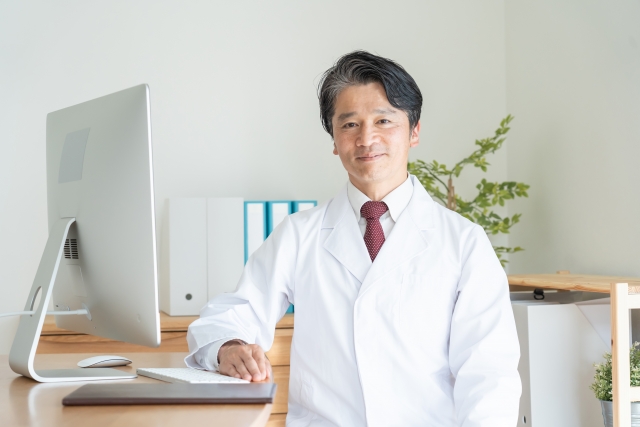
職務に関連する課題の特定
重症筋無力症が仕事に与える影響を考える際、以下のような課題を特定することが役立ちます。
- 体力を要する仕事:筋力が低下するため、重い物を運ぶ、長時間立ち続ける、激しい身体運動を伴う仕事は困難になる場合があります。
- 視覚的な負担:眼筋型の場合、長時間の画面作業や細かい作業が眼精疲労を引き起こしやすくなります。
- 集中力の持続:疲労が蓄積すると、集中力や注意力が低下し、作業効率が下がる可能性があります。
- 不規則なスケジュール:不規則なシフトや長時間労働は、症状を悪化させるリスクが高まるため、配慮が必要です。
合理的な調整と適応の検討
職場での課題に対処するためには、合理的な調整を行うことが不可欠です。
以下のような具体的な対応が考えられます。
- 柔軟な勤務形態:フレックスタイム制や在宅勤務を活用することで、体調に合わせた働き方が可能になります。日中に休憩を取れるスケジュールを設定することも有効です。
- 作業環境の改善:高さ調整可能なデスクや、身体への負担が少ない椅子を導入することで、快適な作業環境を整えることができます。また、画面のブルーライトを軽減するツールや、作業を効率化するためのソフトウェアを活用することも推奨されます。
- 業務内容の調整:チーム内での業務分担を見直し、体力を要する作業を軽減することで、無理なく仕事を続けられるようにします。
- 職場内でのサポート体制:同僚や上司に症状や必要な配慮について理解してもらい、緊急時に備えた支援体制を構築することが大切です。
重症筋無力症を持つ人にとって、職場での適応や働き方の見直しは重要な課題です。
しかし、自分の症状や特性を理解し、職場と協力して適切な環境を整えることで、無理なく働き続けることが可能です。
これらの取り組みを通じて、長期的なキャリア形成を目指していきましょう。
適した職種とキャリアの選択
重症筋無力症(MG)を抱える方にとって、キャリア選択において重要なのは、体調の波に合わせて柔軟に働ける環境を選ぶことです。
以下では、柔軟な勤務形態が可能な職種や、体調に配慮できる働き方を詳しく解説します。
柔軟な勤務形態が可能な職種
柔軟な勤務形態は、体調に応じた働き方を可能にし、無理なくキャリアを続けるための鍵となります。
在宅勤務やテレワークの選択肢
近年、多くの企業が在宅勤務やテレワークを採用しており、重症筋無力症を持つ方にとっても適した選択肢となります。

在宅勤務は、通勤の負担を減らし、自宅で休息を取りながら仕事ができるため、体調管理がしやすいという利点があります。
- IT関連の職種:プログラマー、ウェブデザイナー、システムエンジニアなどは、パソコンを使った作業が中心で、在宅勤務と相性が良い職種です。
- ライターや編集者:執筆や校正業務は、自宅で取り組みやすく、スケジュール管理も自分で行えるため、体調の波に合わせた働き方が可能です。
- カスタマーサポート:チャットやメールを使った顧客対応を行う職種も、在宅勤務に適しており、電話対応がない場合はさらに負担が軽減されます。
在宅勤務を選ぶ際には、自宅の作業環境を整えることが重要です。
たとえば、作業の合間にリラックスできるスペースや、適切な椅子・デスクを用意することで、体への負担を軽減できます。
短時間勤務やジョブシェアリングの機会
短時間勤務やジョブシェアリングは、フルタイムの仕事が難しい場合に適した働き方です。
これらの形態は、1日数時間や週に数日の勤務を可能にし、体調の良い時間帯を活用して働くことができます。
- パートタイムの事務職:データ入力や書類整理といった仕事は、負担が比較的少なく、勤務時間を調整しやすい職種です。
- 販売スタッフや接客業:短時間の勤務であれば、適切な休憩を取りながら無理なく働くことが可能です。ただし、長時間の立ち仕事が求められる場合は適性を検討する必要があります。
- 教育・研修のサポート業務:教材準備や学習指導の補助といった仕事も、短時間で行える場合が多く、負担が軽減される環境が整っています。
短時間勤務やジョブシェアリングを選ぶ際には、職場とのコミュニケーションを密に取り、体調に応じた柔軟な働き方ができるよう配慮を依頼することが大切です。
体調に合わせて働ける職種
体調が日によって異なる重症筋無力症の特性を考慮すると、自分のペースで仕事を進められる職種やキャリアパスが有利です。
自営業・フリーランス
自営業やフリーランスは、働く時間や場所を自由に選べるため、体調に合わせた働き方がしやすい選択肢です。
- デザイナー:グラフィックデザインやイラスト制作は、自宅で集中して作業できる職種であり、納期に合わせた柔軟なスケジュール管理が可能です。
- ライターや翻訳家:執筆や翻訳業務も、完全に個人で進められるため、症状が軽い時間帯を活用して取り組むことができます。
- ネットショップ運営:ECサイトでの商品販売や顧客対応を行う仕事も、自営業の一環として取り組めるため、在宅で働きたい方に適しています。
フリーランスとして働く場合、収入の安定性を確保するために、複数のクライアントを持つことや、スキルの継続的な向上が重要です。
コンサルティングや専門職
コンサルタントや専門職は、高度な知識やスキルを活かし、クライアントの課題解決をサポートする仕事です。
このような職種では、勤務時間や働く場所を調整しやすい場合が多く、重症筋無力症の方にも適しています。
- キャリアコンサルタント:求職者や企業のキャリア支援を行う仕事で、オンラインミーティングを活用することで、移動の負担を減らせます。
- ITコンサルタント:クライアントのシステム導入や業務効率化をサポートする仕事で、プロジェクトごとに働き方を調整しやすいのが特徴です。
- 法律・会計分野の専門家:弁護士や会計士、税理士といった職種は、資格を活かして自分のペースで業務を進められる場合が多く、リモートでの相談業務にも対応できます。
重症筋無力症を持つ方が適切な職種や働き方を選ぶためには、まず自分の体調や生活スタイルを正確に把握することが重要です。
そして、柔軟な勤務形態を提供している企業や、自分のペースで働ける職種を選ぶことで、無理なくキャリアを築くことが可能になります。
必要に応じて専門機関やサポートを活用し、安定した働き方を実現しましょう。
障がい者雇用制度と障害年金について
重症筋無力症(MG)を抱える方にとって、障がい者雇用制度や障害年金の活用は、安定した生活と働き方を実現するための重要なサポートとなります。
本章では、障がい者手帳の取得方法や障害年金の受給要件、具体的な認定事例について解説します。

重症筋無力症と障がい者手帳の取得
障がい者手帳の概要
障がい者手帳は、身体的または精神的な障がいを持つ方が、必要な支援や制度を受けやすくするために交付されるものです。
重症筋無力症は主に「身体障害者手帳」の対象となり、筋力低下や身体機能の障がいとして認定されます。
取得の要件と手続き
取得の要件
重症筋無力症で障がい者手帳を取得するには、以下のような症状が認定基準に該当する必要があります。
- 筋力低下が著しく、日常生活や仕事に支障をきたす状態。
- 動作や歩行が困難な場合や、介助が必要な場合。
必要な書類
- 医師が記入した「診断書」
- 身体障害者手帳の交付申請書(市区町村役場で入手可能)
- 身分証明書や写真など
申請手続き
最寄りの市区町村役場に申請書類を提出します。
その後、専門機関での審査が行われ、障がいの等級が決定されます。
等級に応じた手帳が交付され、障がい者雇用制度や福祉サービスを利用できるようになります。
活用できる制度やメリット
- 障がい者雇用枠の利用: 障がい者雇用促進法に基づき、企業が雇用しやすい環境が整備されています。
- 税制優遇や交通費助成: 所得税控除や公共交通機関の割引などが適用される場合があります。
- 医療費助成: 特定の医療費が減免される制度もあります。
障害年金の受給要件と申請方法
障害年金は、病気や障がいにより日常生活や就労に困難が生じる場合に支給される公的年金制度です。
重症筋無力症による筋力低下や疲労が日常生活に支障を及ぼす場合、受給対象となる可能性があります。

障害年金の種類
- 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方、もしくは20歳未満だった方が対象です。
- 障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
受給要件
初診日の要件
重症筋無力症の診断を初めて受けた日が、年金保険加入期間内であることが条件です。
初診日が厚生年金の加入期間の場合は障害厚生年金の対象となり、厚生年金に加入していない時期にあたる場合は障害基礎年金の対象となります。
保険料の納付要件
初診日の前日時点で、次の条件を満たす必要があります。
- 初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間に、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が全体の3分の2以上あること。
- 上記に当てはまらない場合の特例として、初診日の前日時点で、2カ月前までの直近1年間に保険料未払期間がないこと。
支給額の目安(令和6年度時点)
- 障害基礎年金:1級で約102万円、2級で約81万円(年間)
- 障害厚生年金:加入期間や給与水準により変動
障害等級の認定
障害基礎年金の受給には、障がいの状態が1級、2級のいずれかに該当することが必要です。
障害厚生年金の場合は1級~3級のいずれかに該当する必要があります。
重症筋無力症の場合、筋力低下や動作の困難度が判断基準となります。
申請手続き
- 初診日の証明
初診を行った医療機関で初診日証明書類を取得します。過去のカルテや診療記録が重要な証拠となります。
初診を行った医療機関での証明が難しい場合は、2番目以降に診察をした担当医に依頼し、症状の詳細や日常生活への影響を記載した「受診状況等証明書」または診断書を作成してもらいます。 - 診断書の作成
障害認定日より3カ月以内の現症のものが必要です。 - 必要書類の準備
・年金手帳または年金番号通知書
・戸籍謄本
・病歴・就労状況等申立書
・振込先口座の情報 - 申請書類の提出
年金の種類によって提出先が異なります。
障害基礎年金の場合、最寄りの市区町村役場の窓口で申請を行います。
障害厚生年金の場合、年金事務所または街角の年金相談センターが申請先になります。
審査には数か月かかる場合があるため、余裕を持った手続きを心がけましょう。 - 審査結果の通知
申請が受理されると、年金証書が交付されます。万が一不支給となった場合は、不服申し立てが可能です。
重症筋無力症の方が障害年金や障がい者手帳を活用することで、生活の安定性を高めながら、自分に合った働き方を見つけることができます。
障害厚生年金の認定事例
障害厚生年金2級の認定事例
ケース1:筋力低下が全身に及び、日常的な動作が困難な状態。
日常生活の多くを介助者に依存している。
このような場合、2級が認定された事例があります。
障害厚生年金3級の認定事例
ケース2:筋力低下が四肢にあり、重い荷物を持つ作業や長時間の歩行に支障がある状態。
自宅内での動作は可能だが、外出時には杖や補助具を使用。
就労はデスクワークや短時間勤務で可能。
この事例の場合、3級が認定され、厚生年金加入者であれば報酬比例での支給額が決定されました。
重症筋無力症の障がいがある方が支援を受けられる機関
重症筋無力症(MG)の方が働きやすい環境を整えるためには、専門の支援機関を活用することが重要です。
以下では、利用可能な主要機関やサービスの特徴と、それぞれが提供するサポート内容について詳しく解説します。

難病相談支援センター
概要と役割
難病相談支援センターは、都道府県や政令指定都市が設置している公的機関で、難病を抱える方の相談窓口として機能しています。
重症筋無力症を含む指定難病に該当する疾患に対し、医療・福祉の面から包括的な支援を行います。
提供される主なサポート
- 生活相談:病気と向き合いながら生活を送るためのアドバイスを提供。福祉サービスや制度利用の方法を案内。
- 医療情報の提供:専門医療機関や治療法に関する情報を共有。必要に応じて医療機関への紹介状作成をサポート。
- 就労に関する支援:雇用支援の窓口やハローワークとの連携。病状に配慮した働き方の提案。
利用方法
最寄りの難病相談支援センターに連絡し、直接相談や訪問支援を依頼します。
多くの場合、予約制となっているため、事前に問い合わせることが推奨されます。
ハローワークの活用
ハローワークとは
ハローワークは、職業紹介や雇用保険手続きのほか、障がい者や難病患者向けの支援サービスを提供する公共機関です。
重症筋無力症を抱える方も、一般の求人情報に加えて障がい者雇用枠の求人を利用することができます。
提供される主なサポート
- 専門援助部門の設置:障がい者や難病患者を対象とした専門窓口が設置されており、個別相談が可能です。
- 職業訓練の案内:スキルアップや再就職に必要な職業訓練の情報を提供。
- トライアル雇用制度の活用:一定期間試験的に働きながら、職場との相性を確認するトライアル雇用制度を案内します。
利用方法
障がい者手帳を持っている場合は、専門窓口での相談が可能です。
初めて利用する方は、事前予約をして訪問し、担当者に自身の状況や希望を伝えましょう。
就労移行支援事業所による職業訓練
就労移行支援事業所とは
就労移行支援事業所は、一般企業への就職を目指す障がい者を対象に、職業訓練やスキルアップ支援を行う施設です。
重症筋無力症の方が症状と向き合いながら働くためのスキルや知識を身につける場として活用できます。
提供される主なサポート
- ビジネスマナーの指導:社会人としての基本的なマナーやルールを学ぶことができます。
- スキルアップ研修:ITスキル(パソコン操作やデータ入力など)や資格取得のための講座を提供。
- 就職前後のフォロー:職場での課題や問題解決に向けたアフターフォローを実施。
利用方法
医療機関や市区町村役場から紹介を受けることが一般的です。
希望する事業所を見学し、自身の目標に合ったプログラムを選ぶことが重要です。
障がい者雇用専門の求人サイト
概要
障がい者雇用に特化した求人サイトでは、体調や症状に配慮した求人情報を多く扱っています。
これらのサイトを活用することで、在宅勤務や短時間勤務など柔軟な働き方を提供する企業と出会うことが可能です。
特徴
- 多彩な求人情報:フルタイムやパートタイム、テレワークなど、さまざまな雇用形態の求人を検索可能。
- 専門エージェントのサポート:履歴書添削や面接対策のサポートを受けられます。
- 症状に配慮した求人探し:重症筋無力症などの難病に理解がある企業を選びやすい。
スグJOBの活用
特におすすめのサイトが「スグJOB」です。
このサイトでは、障がい者に特化した求人情報を豊富に提供しています。
専門のエージェントがサポートを行い、応募先企業との調整や面接対策を徹底的に支援してくれるため、初めての就職活動にも安心です。
まとめ
重症筋無力症を抱える方が働きやすい職場を見つけるためには、専門の支援機関を積極的に活用することが重要です。
難病相談支援センターやハローワークでは、個別の相談や支援が受けられるほか、就労移行支援事業所では、就職に必要なスキルを身につけることができます。
また、障がい者雇用専門の求人サイトを活用することで、自分の体調や希望に合った働き方を提案してくれる企業と出会うことが可能です。
支援機関のサポートを最大限活用しながら、自分に最適な働き方とキャリアを築いていきましょう。







