障害者雇用での疲れやストレスの原因と対処法
「障害者雇用で働いているけれど、毎日なんだかくたびれてしまう…。」
「理解してもらえていないように感じて、職場に行くのが少しつらい…。」
こんなふうに感じている方は、けっして少なくありません。

実際、障害者雇用の現場では、配慮が十分でなかったり、仕事内容や職場の雰囲気が合わなかったりといった理由で、心や体に疲れを感じている方が多くいらっしゃいます。
特に、周囲に相談できる人がいないと「自分だけがつらいのでは?」と感じてしまいがちですが、同じような悩みを抱えている方はたくさんいます。
この記事では、そうした方に向けて、障害者雇用の現状をわかりやすく整理しながら、疲れやストレスが生まれる原因とその対処法について、丁寧にお伝えしていきます。
また、もし「今の職場では続けるのが難しいかも…」と思っている方には、転職を前向きに考えるためのヒントや情報もご紹介します。
どんな働き方が自分に合っているのか、どうすれば少しでも楽に仕事ができるのか――
そんなヒントを見つけるお手伝いができれば嬉しいです。
ぜひ、肩の力を抜いて、ゆっくりと読み進めてみてくださいね。
障害者雇用の現状
障害者雇用は、法律や制度の整備とともに少しずつ進んできました。
企業も社会全体としても、以前より障害のある方々を雇用することへの理解が深まってきているのは事実です。
しかし一方で、働いている当事者の声に耳を傾けると、「思ったよりしんどい」「配慮が足りない」といった悩みが多く聞かれます。
その背景には、制度と実際の職場環境との間にあるギャップが存在しています。
ここでは、障害者雇用のメリットとともに、雇用の実態や課題について詳しく見ていきましょう。
今の働き方に不安や悩みを感じている方にも、「なぜしんどいのか」を客観的に理解するヒントになるかもしれません。

障害者雇用のメリット
障害者雇用の最大の特長は、個々の事情に配慮した柔軟な働き方が可能であることです。
「通院がある」「フルタイム勤務は体力的に難しい」「朝が苦手」など、それぞれの困りごとに寄り添った対応を受けられることが期待されています。
具体的には、以下のような配慮が行われるケースが多く見られます。
- 通院や体調への配慮(早退・遅刻への柔軟な対応)
- 勤務時間の短縮や時差出勤
- 音や光に敏感な方向けの座席配慮
- 業務内容の調整(できることを中心に任せる)
また、障害者雇用枠での就労には、企業内に支援体制があることも多く、ジョブコーチや専門の産業医、カウンセラーが配置されている職場も増えてきました。
こうした体制の中で、安心して働けることや長く続けられる可能性が高まるのは、障害者雇用の大きな魅力と言えるでしょう。
法定雇用率と障害者の雇用数
企業には、障害のある方を一定の割合で雇用することがが定められており、この割合を「法定雇用率」といいます。
2024年4月からはこの法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられ、2026年度からは2.7%にまで上がる予定です。
この改正により、これまで以上に企業が障害者の採用に積極的になっており、実際に障害者の雇用数も年々増加しています。
とくに大企業や行政機関では、採用枠を拡大したり、特例子会社を設けたりといった動きも進んでいます。
しかし、「雇うこと」と「働きやすさの確保」は必ずしもイコールではありません。
雇用数が増えても、職場の配慮や受け入れ体制が整っていないまま採用されると、かえって働きにくさや孤独感を感じてしまうケースもあるのです。
障害者の離職率と離職理由
就職した障害者のうち、約半数が1年以内に離職しているというデータもあります。
この数字からも、障害者雇用の「定着」が大きな課題であることがわかります。
離職の主な理由としては、次のような項目が挙げられています。
- 業務内容や職場環境が合わなかった
- 上司や同僚との人間関係に悩んだ
- 障害への理解や配慮が不十分だった
こうした理由は、特別なものではなく、働く多くの方が感じている「しんどさ」にも通じています。
ですが、障害を抱えながら働く場合は、そのしんどさが身体や心により強く影響してしまうこともあるのです。
とくに、職場で「配慮をお願いしづらい」「頼れる人がいない」と感じてしまうと、それだけで精神的に疲弊してしまうこともあるでしょう。
このように、障害者雇用には多くの可能性がある一方で、実際の現場ではまだまだ働き続けるための支援や理解が追いついていないのが現状です。
今感じている「疲れた」「もう限界かも」という思いも、けっしてあなただけのものではありません。
このあとに続く章では、その疲れやストレスの具体的な原因と、対処法について詳しくお伝えしていきます。
どうか、焦らず、ご自身の心と体を大切にしながら読み進めてみてくださいね。
障害者雇用での疲れやストレスの原因
障害者雇用において、「疲れた」「しんどい」と感じてしまうのは、決してあなたのせいではありません。
実際には、企業側と障害者本人の両方にさまざまな背景や要因があるのです。
ここでは、企業側・障害者側それぞれの視点から、ストレスや疲れの原因を一つずつ丁寧に見ていきましょう。
「なぜつらいのか」を知ることは、対処への第一歩になります。
企業側の疲れやストレスの理由
企業が障害者雇用を進める中で、意図せず当事者に負担をかけてしまうケースがあります。
これは決して悪意があるわけではなく、「知らなかった」「どう配慮すればよいかわからなかった」という状況によるものが多いのです。

障害の特徴や個別の特性の理解不足
障害とひと口に言っても、その特性や必要な配慮は人それぞれ異なります。
しかし企業側が、「〇〇障害=こういう人」と一括りにしてしまうと、適切なサポートができず、逆に負担をかけてしまうことがあります。
たとえば…
- 体調の波がある方に、毎日同じペースの勤務を求めてしまう
- 注意力が必要な作業を、集中力が長時間続かない方に任せてしまう
- コミュニケーションが苦手な方に、窓口対応を割り振ってしまう
こういった配慮のズレが、「なぜ自分ばかりうまくいかないのか…」というストレスにつながってしまうのです。
理解不足は、悪気がなくても大きな壁になります。
障害者雇用にフィットする部門の不在
障害者の方がその力を十分に発揮できるような仕事や部署が、社内にまだ整備されていない場合もあります。
その結果、「とりあえずこの部署へ」と配属され、業務とスキルが合わないまま働くことになってしまうことも。
このような状態では、企業側も「せっかく雇ったのに活躍してもらえない」、本人も「役に立てない」と感じ、双方にとってストレスや不安のもとになります。
このようなミスマッチを防ぐためには、障害者が働きやすい環境づくりを企業全体で考えていく必要があります。
障害者側の疲れやストレスの理由
企業側の体制だけでなく、当事者として働く側にも、「疲れた」「つらい」と感じる理由はさまざまあります。
特に、配慮が十分でなかったり、自分の特性と業務が合っていないと、毎日の仕事そのものが負担になってしまいます。
職場環境や業務内容とのミスマッチ
自分の得意なことや、苦手なことを職場が把握していないと、苦手な業務を繰り返し任されてしまうことがあります。
たとえば…
- マルチタスクが苦手なのに、複数業務を同時に求められる
- 静かな環境が必要なのに、オープンフロアで働かされる
- 曖昧な指示が理解しにくいのに、「察して行動して」と言われる
このような状況が続くと、精神的にも体力的にもどんどん消耗してしまいます。
特に発達障害や精神障害をお持ちの方にとっては、このミスマッチが「限界」「辞めたい」という思いを引き起こす大きな要因になりやすいです。

周囲の理解不足や偏見
もう一つの大きな要因が、「周囲の無理解」です。
これは、悪意というよりも、障害についてよく知らないことからくる行動であることが多いです。
たとえば…
- 「また休み?」「気分の問題でしょ?」という心ない一言
- 頑張っていても「配慮されて楽をしている」と誤解される
- 周囲に迷惑をかけたくないと思い、自分から相談できなくなる
こうした空気の中で働き続けることは、非常に強いストレスになります。
「いつも気を張っていなければならない」「無理をしてでもやらなければ」と思ってしまい、心がすり減ってしまうこともあります。
障害者雇用は、本来「安心して働ける場所」であるべきです。
でも、現実には「しんどい」「つらい」と感じる瞬間がたくさんあるのも事実です。
次の章では、そういった疲れやストレスに対して、企業側がどう対応していくべきか、具体的な対処法をご紹介します。
「誰かに理解してもらいたい」「もっと働きやすくなってほしい」と思っている方に、少しでも安心してもらえるヒントになれば幸いです。
企業側の疲れやストレスへの対処法
障害者雇用を進めていくうえで、企業が抱える悩みやストレスも無視できません。
「どう配慮すればいいのかわからない」「思うように活躍してもらえない」など、企業側にも戸惑いや不安があるのが現実です。
しかし、それらの課題を放置したままでは、当事者にとっても企業にとっても、働きやすい環境づくりは実現できません。
ここでは、企業が取るべき具体的な対処法を、わかりやすくご紹介していきます。
少しずつでも対応を積み重ねることで、職場の雰囲気や社員の安心感はきっと変わっていきます。
当事者からのヒアリングによるストレス原因の把握
まず企業側が対策するに当たって大切なのは、障害当事者の声をしっかりと聞くことです。
「何に困っているのか」「どんなことがストレスになっているのか」を直接確認することで、表面では見えない課題が明らかになります。
ヒアリングの際は、以下のような工夫をすると、より安心して話してもらいやすくなります。
- 面談は静かな場所で実施し、落ち着いた雰囲気をつくる
- 上司ではなく、信頼できる第三者(産業医や人事担当者)が同席する
- 一度きりで終わらず、定期的な聞き取りの場を用意する
「話しても無駄だ」と感じさせないよう、真剣に受け止めてくれる姿勢が何より大切です。

ストレス原因の分類と対策方法の検討
ヒアリングから得られた情報は、単に聞いて終わりにせず、ストレスの原因を分類・整理して対応策を考える必要があります。
下記の表は、よくあるストレス原因とその対策例です。職場の状況に応じて、応用してみてください。
| ストレスの要因 | よくある内容 | 具体的な対策例 |
| 環境要因 | 騒音、照明、温度など | デスク位置の変更、間接照明の導入、空調の調整 |
| 人間関係 | 指示が曖昧、上司との距離感 | 業務のマニュアル化、メンター制度の導入 |
| 業務内容 | 複雑な作業、マルチタスク | 作業工程の分解、役割分担の見直し |
| コミュニケーション | 会話が苦手、説明が理解しづらい | チャットやメモでの指示、確認タイミングの設定 |
整理することで、「どこから手を付ければいいのか」が明確になります。
改善策の実施
課題が整理できたら、優先順位をつけてできるところから改善を始めてみましょう。
すべてを一度に変えるのは難しくても、小さな改善の積み重ねが大きな信頼につながります。
たとえば…
- 難しい業務は一部切り出して別の人と分担する
- 朝礼を文字ベースに変える
- 出退勤の打刻を柔軟に運用する
「会社がちゃんと考えてくれている」と感じられること自体が、大きな安心感になります。
障害者雇用の必要性の組織内共有
障害者雇用を「法律で決まっているから仕方なく」ではなく、組織の多様性や成長のために必要なこととして、全社的に理解を深めることも大切です。
社内での共有方法としては、次のようなものがあります。
- 定例会議での事例共有
- 成功事例を社内報で紹介
- 採用背景や目的を、全社員に説明する研修の実施
「誰かが配慮してくれるだろう」ではなく、組織全体で支える風土が、離職防止にもつながります。
定期的なヒアリングと改善体制の構築
一度対応したからといって、すべてが解決するわけではありません。
状況は常に変化しますし、体調や環境の変化により、新たな困りごとが生まれることもあります。
だからこそ、定期的にヒアリングの場を設け、改善を続けていく体制づくりが欠かせません。
おすすめの方法としては…
- 半年ごとに定期面談を実施する
- 匿名アンケートで意見を集める
- 担当部署に「配慮状況チェックリスト」を持たせる
こうした取り組みが、問題の早期発見と離職防止に直結します。
障害の特徴や個別の特性の把握・共有
障害の理解は、特別な知識がなければ難しいと感じる方もいるかもしれません。
ですが、ポイントを押さえて学べば、誰でも基本的な理解を持つことは可能です。
そのためには、以下のような社内の取り組みが効果的です。
- 外部の専門家を招いた研修会
- 社内イントラで障害特性の資料を共有
- メンターや上司向けの勉強会を実施
「知らなかったこと」がわかるようになると、自然と関わり方が変わっていくものです。

障害者雇用にフィットする部門の設置
企業の中には、業務を見直して障害者が働きやすい部署や職種を新たに設けるケースもあります。
たとえば…
- データ入力や事務処理に特化したチームをつくる
- 清掃・備品管理などを集約したユニットを設ける
- 特例子会社の設立によって業務を最適化する
こうした取り組みによって、当事者の強みがより活かされるようになり、企業側の生産性向上にもつながるのです。
専門の支援機関への相談
「社内だけでの対応に限界を感じている…」
そんなときは、外部の専門機関の力を借りることも検討してみてください。
主な支援機関・サービスは以下のとおりです。
| 支援機関 | 主なサポート内容 |
| 就労移行支援事業所 | 就職後のフォロー、職場との調整 |
| ジョブコーチ支援(地域障害者職業センターなど) | 職場訪問、上司や同僚へのアドバイス |
| 障害者就業・生活支援センター | 働くことと生活面の両方をサポート |
専門知識を持った第三者のサポートが入ることで、当事者と企業の間に橋渡しが生まれ、無理のない形で職場改善が進むことも多くあります。
どの対処法も、「できることから一歩ずつ」で構いません。
企業側の姿勢が少し変わるだけでも、当事者が感じるストレスは大きく減ることがあります。
次の章では、障害のあるご本人ができる工夫やセルフケアについて、詳しくお伝えしていきますね。
ご自身の気持ちも大切にしながら、一緒に見ていきましょう。
障害者側の疲れやストレスへの対処法
障害のある方が、毎日の仕事の中で「疲れた…」「つらい…」と感じるのは、けっして特別なことではありません。
環境や仕事内容、人間関係など、さまざまな要因が重なって、心や体に負担がかかってしまうことはよくあります。
そんな時に大切なのは、「無理をしすぎないこと」と「自分を守る準備をしておくこと」です。
ここでは、就職前にできる準備と、就職後にできるセルフケアについて、優しく丁寧にご紹介していきます。
「もっと自分らしく働きたい」「少しでもラクに過ごしたい」――そんな気持ちを大切にしながら、読み進めてみてくださいね。
就職前の準備
就職前にしっかり準備をしておくことで、働き始めてからの不安やストレスを軽減することができます。
自分に合った職場を見つけ、必要な配慮を伝えられるようにしておくことが、安心して働く第一歩です。
自分に合った職場や業務の選択
「どんな仕事なら無理なく続けられそうか」「どんな環境が落ち着くのか」――そうした自己分析をしておくことがとても大切です。
たとえば、以下のようなことをノートに書き出して整理してみましょう。
- これまでに得意だった仕事や作業は何か
- 苦手だったことや体調が悪くなった理由は何か
- 自分が落ち着いて過ごせる職場環境はどんな場所か(静か/にぎやか、個室/オープンスペース など)
- 1日どのくらいの時間なら無理なく働けそうか
こうした情報を把握しておくことで、面接や職場見学の際にも「自分に合う職場かどうか」を見極める材料になります。
焦らず、「自分が安心して働ける場所」を探す気持ちで大丈夫です。
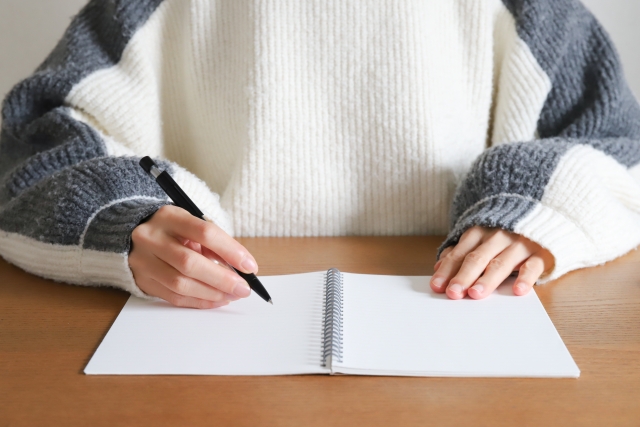
必要な配慮の明確化と伝達
就職する前に、「こういう時に困りやすい」「こうしてもらえると助かる」というポイントを明確にしておくと、配慮をお願いしやすくなります。
以下のような形式で整理しておくのがおすすめです。
| 困りごと | 必要な配慮 |
| 朝の体調が安定しないことがある | 始業時間を遅らせてもらえると助かる |
| 大きな声や騒音が苦手 | 静かなスペースで作業したい |
| 電話対応が苦手 | メールやチャットでのやり取りを中心にしてほしい |
このように事前に伝えることで、入社後の「言いづらさ」や「我慢しすぎ」が減るだけでなく、職場の理解も得やすくなります。
もし「どう伝えていいかわからない」と感じたら、支援機関に相談してみても大丈夫です。
働きながらのセルフケア
働き始めてからも、心と体のバランスを保つためには、自分自身でのケアがとても大切になります。
無理をせず、自分に優しく接することを心がけてみましょう。
上司や同僚との良好なコミュニケーション
困ったことがあった時、「どうやって伝えよう……」と悩んでしまうこと、ありますよね。
でも、小さなことでも早めに相談することが、ストレスをためないコツです。
- 体調が優れない時は無理せず報告する
- わからないことはそのままにせず聞いてみる
- 感謝の気持ちを伝えることで関係がスムーズになることも
「話しやすい関係」を日頃から少しずつ作っておくことで、困った時に助けを求めやすくなります。
信頼関係は、一度にできるものではありませんが、小さな積み重ねが大切です。
ストレス解消法の実践
仕事の疲れやストレスは、ため込まずにこまめに発散することが大事です。
自分に合った方法を見つけて、「こころのリセットタイム」を意識的に作るようにしてみましょう。
おすすめのストレス解消法の例:
- ゆっくりお風呂に入る
- 自然の中を散歩する
- 好きな音楽を聴く
- 日記やメモに気持ちを書く
- 動物と触れ合う(ペットや猫カフェなど)
「これは子どもっぽいかな?」「こんなことをして意味があるのかな?」と思わなくても大丈夫。
自分がホッとできる時間こそが、最大のケアです。

支援機関の活用
もし「ひとりで抱えるのがしんどい」「職場に相談しづらい」と感じたら、外部の支援機関を頼ってみてください。
専門のスタッフが話を聞いてくれたり、職場との間をサポートしてくれることもあります。
活用できる支援機関の一例:
| 支援機関 | 主な支援内容 |
| 障害者就業・生活支援センター | 仕事と生活のバランスに関する相談全般 |
| ハローワークの専門援助部門 | 就職・転職の支援、企業との調整 |
| 就労移行支援事業所 | 職場定着に向けたトレーニングと相談 |
| 地域障害者職業センター | ジョブコーチ派遣、職場へのアドバイス |
「こんなこと相談していいのかな?」と思うようなことでも、まずは一度話してみてください。
頼れる場所があるというだけでも、心の支えになります。
大切なのは、無理せず、自分らしい働き方を少しずつ見つけていくこと。
それが、疲れやストレスと上手に付き合っていくカギになります。
次の章では、「今の職場ではどうしても難しい」と感じたときに、転職という選択肢を考える際のポイントを詳しくお伝えしますね。
どうか、ご自身を責めずに、「より良い働き方」を見つけるためのヒントとして読んでみてください。
障害者が転職を考えるとき
「もう頑張れないかもしれない」「このままここで働き続けるのは、正直しんどい…」
そんなふうに感じたとき、転職という選択肢を持つことは、決して間違いではありません。
我慢を続けて体調を崩してしまう前に、自分自身の未来を守るためにも、「転職」という道を前向きに考えることはとても大切です。
ここでは、転職を考え始めたときにやっておきたい準備や、相談できる機関、そして頼れる転職サイトについて、丁寧にお伝えしていきます。
少しずつで大丈夫です。
あなたのペースで、次の一歩を考えていきましょう。
転職の準備とタイミング
「辞めたい」と思った瞬間にすぐ退職するのではなく、少しずつ準備を進めながら動くことが大切です。
転職を考えるきっかけは人それぞれですが、以下のようなサインが出ている場合は、転職の準備を始めるタイミングかもしれません。
- 朝起きるのがつらく、仕事のことを考えると体が重くなる
- 職場にいるだけで緊張が続き、帰宅後はぐったりしてしまう
- 上司や同僚に相談しても改善されない
- 配慮を求めることに限界を感じている
- 体調不良が続いて、仕事に集中できなくなってきた
これらのサインを無視し続けると、心や体が悲鳴を上げてしまうこともあります。
「今すぐ辞めるべきか」ではなく、「このままここにいて大丈夫か?」と自分に問いかけてみてください。
そして、少しでも不安があるなら、今のうちから情報を集め、準備を始めることをおすすめします。

就労支援機関や制度の活用
転職活動を一人で進めるのは不安…という方も多いかと思います。
そんなときには、障害のある方の就労をサポートする専門機関をぜひ頼ってみてください。
ここでは、主な支援機関とそのサポート内容をご紹介します。
| 支援機関名 | 主な支援内容 |
| 就労移行支援事業所 | ビジネスマナーやPCスキルの習得支援、職場体験、就職活動のサポート |
| 地域障害者職業センター | ジョブコーチ派遣、職場適応指導、企業との連携支援 |
| 障害者就業・生活支援センター | 仕事と生活の両立支援、転職相談、福祉サービスとの連携 |
これらの機関では、「今の仕事が合わないかもしれない」と悩む段階からでも相談可能です。
「まだ辞めると決めていないけれど、話を聞いてほしい」
「自分に合う働き方を一緒に考えてほしい」
そんな気持ちを受け止めてくれるスタッフが、あなたの力になってくれるはずです。
ひとりで抱えず、まずは話してみることから始めてみましょう。
転職サイト・エージェントの活用
転職活動を進めるうえで、障害者雇用に特化した転職サイトやエージェントを活用することは、とても大きな力になります。
一般の求人サイトには掲載されていない「障害者専用の求人情報」や、「配慮事項をしっかり確認している企業情報」など、安心して働ける職場を探すための情報がそろっているのが特徴です。
中でも、業界トップクラスの求人数を誇る スグJOB は、こんな方におすすめです。
- 障害への配慮がある職場を探したい
- 自分の障害に合う求人だけを見たい
- 専任のスタッフに相談しながら転職活動を進めたい
- 就職後もフォローを受けたい
さらに、スグJOBでは、「在宅勤務OK」「通院配慮あり」などの条件でも検索できるので、自分に合った働き方を選びやすくなっています。
転職を考えることに、不安や迷いを感じるのは自然なことです。
でも、あなたが「今よりもっと心地よく働ける職場」を見つけることは、きっと可能です。
無理をせず、少しずつ動き出してみてくださいね。
次の場所で、あなたらしく輝ける未来を、一緒に目指していきましょう。
まとめ
障害者雇用で働いているなかで、「毎日がしんどい…」「なんだかずっと疲れている…」と感じている方は、あなただけではありません。
職場の理解不足、業務とのミスマッチ、周囲からのささいな言葉や態度――
そういった小さな負担が積み重なって、気づけば心も体もヘトヘトになってしまうこと、ありますよね。
これは、あなたの努力や気持ちが足りないわけでは決してありません。
むしろ、よくここまで頑張ってこられましたね、と伝えたいです。
今回の記事では、障害者雇用の現状や、「なぜ疲れやストレスがたまりやすいのか」といった背景を、企業側・ご本人側の両方の視点からお話しました。
そのうえで、以下のような対処法もご紹介しました。
- 企業側が取り組むべきヒアリング・環境整備・外部支援の活用
- 障害当事者としてできる職場選び・配慮の伝え方・セルフケア
- どうしても合わないと感じたときの、転職という前向きな選択肢
こうした工夫を少しずつ取り入れていくことで、「無理せず働ける」「安心して続けられる」環境はつくれるはずです。
そして、もし今の職場が合っていないと感じたら――
その時は、無理して我慢を続けるのではなく、新しい環境を探すことも、あなた自身を守る大切な選択肢です。
また、スグJOBでは、障害のある方に向けて、配慮のある求人を多数掲載しています。
自分に合う職場を探したい方、まずは話だけでも聞いてみたい方にも、きっと役立つはずです。
どうか、これからの毎日が少しでも穏やかに、あなたらしく過ごせますように。
疲れを手放して、自分らしく働ける未来を、一緒に見つけていきましょう。






