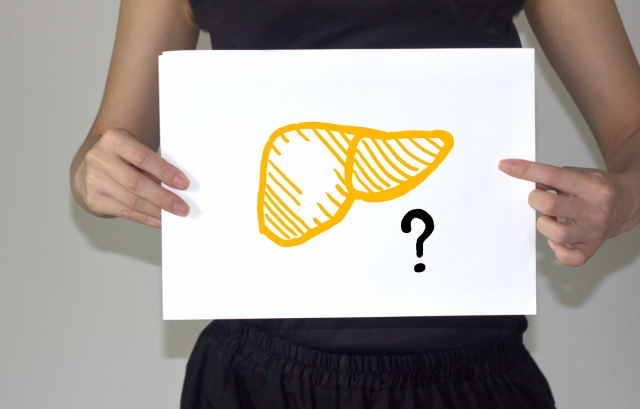
肝臓機能障害のある方の就職・復職と仕事の両立
肝臓機能障害の診断を受け、これからの「仕事」との向き合い方に不安を感じていらっしゃいませんか。
「治療と仕事を両立できるだろうか」「職場の理解を得られるだろうか」「自分に合った働き方が見つかるだろうか」など、就職や復職、日々の業務に関する悩みは尽きないことでしょう。
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、症状が自覚しにくいために、ご自身でも気づかないうちに負担を抱えていることも少なくありません。
しかし、正しい知識を身につけ、利用できる制度やサポートを適切に活用することで、ご自身の体調を大切にしながら、やりがいを持って仕事を続けることは決して不可能ではありません。
この記事では、肝臓機能障害の基礎知識、治療と仕事を両立するための具体的な働き方、そして活用できる就労支援サービスまで、一人ひとりが自分らしいキャリアを築くためのヒントを分かりやすく解説していきます。
あなたの「働きたい」という気持ちに寄り添い、安心して次の一歩を踏み出すための道しるべとなることを願っています。
肝機能障害とは
まずはじめに、ご自身の体と向き合う上で大切な「肝臓機能障害」そのものについて理解を深めていきましょう。
肝臓が私たちの体でどのような役割を担い、なぜ機能障害が起こるのか、そしてどのような症状が現れるのか。
基本的な知識を持つことは、今後の治療や仕事との両立を考える上での大きな土台となります。
ここでは、専門的な内容もできるだけ分かりやすく解説しますので、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
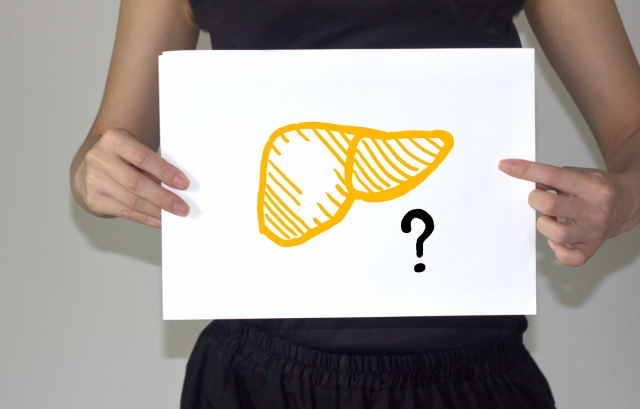
肝臓の働きと障害の原因
肝臓は、私たちの生命活動を支えるために、休むことなく働き続ける非常に重要な臓器です。
その働きが何らかの原因で低下してしまう状態が「肝臓機能障害」です。
主な原因と症状
肝臓は「体内の化学工場」に例えられるほど、多くの複雑な役割を担っています。
その中でも、特に重要な3つの機能をご紹介します。
- 代謝機能:
食事から摂取した栄養素(糖質、たんぱく質、脂質)を、体内で使いやすい形に変えてエネルギーとして供給したり、貯蔵したりします。
この働きが低下すると、エネルギー不足から疲れやすさを感じたり、体力が続かなくなったりすることがあります。
これは、仕事のパフォーマンスにも直接関わる重要な機能です。
- 解毒機能:
アルコールや薬、体内で発生したアンモニアなどの有害物質を分解し、無害な物質に変えて体外へ排出します。
肝臓のこの機能がなければ、私たちの体は有害な物質に満たされてしまいます。
機能が低下すると、体内に毒素が溜まりやすくなり、だるさや集中力の低下につながることがあります。
- 胆汁生成:
脂肪の消化・吸収を助ける「胆汁(たんじゅう)」という消化液を生成・分泌します。
胆汁が十分に作られないと、脂っこい食事で胃がもたれたり、食欲がなくなったりする原因にもなります。
ウイルス性肝炎、アルコール性肝障害、NASH等の原因疾患
肝臓機能障害を引き起こす原因は一つではありません。
代表的な原因疾患には以下のようなものがあります。
- ウイルス性肝炎:
B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの感染によって肝臓に炎症が起こる病気です。
感染経路は主に血液や体液を介したもので、適切な治療を行わないと慢性肝炎や肝硬変、肝がんへと進行するリスクがあります。
- アルコール性肝障害:
長期間にわたる過度な飲酒が原因で肝臓にダメージが蓄積される状態です。
初期は脂肪肝ですが、飲酒を続けることでアルコール性肝炎、そして肝硬変へと至る可能性があります。
仕事上の付き合いであっても、飲酒量のコントロールが不可欠となります。
- NASH(非アルコール性脂肪性肝炎):
「ナッシュ」と読みます。
アルコールをほとんど飲まないにもかかわらず、肥満や糖尿病、脂質異常症(高脂血症)などを背景に肝臓に脂肪が溜まり、炎症を引き起こす病気です。
食生活の欧米化に伴い近年増加しており、生活習慣の改善が治療の鍵となります。
主な症状と日常生活への影響
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれています。その理由は、ダメージを受けても初期段階ではほとんど自覚症状が現れないためです。
これは、肝臓の予備能力が高く、多少のダメージではSOSのサインを出さない性質によるものです。
しかし、障害がある程度進行すると、以下のような様々な症状が現れ始めます。
- 倦怠感(だるさ)や疲れやすさ
- 黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)
- 食欲不振や体重減少
- むくみや腹水
これらの症状は、日常生活はもちろん、仕事にも大きな影響を及ぼします。
例えば、「以前のように集中してデスクワークができない」「通勤だけで疲れてしまう」「会議中に強い眠気を感じる」といった困難が生じることがあります。
症状が外見からは分かりにくいため、周囲から「怠けている」と誤解されてしまうこともあり、精神的なつらさを抱える方も少なくありません。
だからこそ、自分自身の体調の変化に気を配り、無理をしないことが何よりも大切です。
そして、仕事と治療を両立させていくためには、これらの症状について職場の理解を得るための工夫も必要になってきます。
肝臓機能障害の診断と治療
体に不調を感じたり、健康診断で異常を指摘されたりすると、誰もが不安になるものです。
しかし、正確な診断を受けてご自身の状態を正しく把握することは、効果的な治療への第一歩であり、仕事との両立に向けた計画を立てる上でも不可欠です。
ここでは、肝臓機能障害の診断方法や、仕事と両立していく上での基本となる治療法について見ていきましょう。
検査方法と重症度分類
肝臓機能障害の早期発見と適切な治療は、症状の進行を抑え、安定した生活を送る上で非常に重要です。
ここでは、どのような検査が行われるのか、また、治療はどのようなものがあるのかをわかりやすく説明します。
- 血液検査:
臓の細胞がダメージを受けると、血液中に特定の酵素が漏れ出します。
この酵素の数値を調べることで、肝臓の状態を把握します。
「AST(GOT)」や「ALT(GPT)」、「γ-GTP」といった項目がこれにあたり、健康診断の結果で見たことがある方も多いかもしれません。
これらの数値は、肝臓の炎症の度合いを示す重要な指標となります。
- 画像検査:
腹部超音波検査やCT検査、MRI検査など
肝臓の状態や病変の有無を確認するために行われます。これらの検査結果や、症状の程度、合併症の有無などによって、肝臓機能障害の重症度が分類されます。

これらの検査結果を総合的に判断し、医師は肝臓機能障害の有無やその原因、そして「重症度」を分類します。
重症度とは、肝臓がどのくらいの余力(予備能)を残しているかを示すものです。
この重症度の分類によって、治療方針だけでなく、日常生活や仕事でどの程度の配慮が必要になるかという目安も変わってきます。
ご自身の状態を正確に知ることが、無理のない働き方を考える上で非常に大切になります。
生活習慣の改善を中心とした治療
肝臓機能障害の治療において、多くの場合で最も重要となるのが「生活習慣の改善」です。
薬物療法と並行して、またはその前に、日々の生活を見直すことが治療の基本となります。
食事療法と運動療法
食事と運動は、肝臓をいたわる上で車の両輪とも言える要素です。
- 食事療法:
基本は、栄養バランスの取れた食事を規則正しく摂ることです。
特に、肝臓の再生を助ける良質なたんぱく質(魚、大豆製品、脂身の少ない肉など)を適度に摂り、肝臓に負担をかける脂質や塩分は控えめにします。
一度にたくさん食べる「ドカ食い」は避け、腹八分目を心がけることが大切です。
バランスの取れた食事は、仕事中の安定したエネルギー維持にも繋がります。
- 運動療法:
ウォーキングや軽いジョギング、水泳といった有酸素運動が推奨されます。
適度な運動は、肥満の解消や血糖値の安定に繋がり、特にNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の改善に効果的です。
大切なのは、無理なく、楽しみながら継続することです。
「少し息が弾むけれど、会話はできる」くらいの強度が目安とされています。
過度な運動はかえって体に負担をかけるため、主治医に相談しながら行いましょう。
アルコール摂取制限と禁煙
アルコールが肝臓に大きな負担をかけることは広く知られています。
アルコール性肝障害の場合は、治療の第一歩として「禁酒(断酒)」が絶対条件となります。
その他の原因による肝臓機能障害であっても、肝臓を休ませるために原則として禁酒が推奨されます。
仕事上の付き合いなどで難しい場面もあるかもしれませんが、ご自身の体を守ることを最優先に考えましょう。
また、喫煙も肝臓の血流を悪化させ、病状の進行に関わることが分かっているため、禁煙することが強く勧められます。

薬物療法と定期的な通院の必要性
生活習慣の改善と併せて、原因疾患に応じた薬物療法が行われることもあります。
例えば、ウイルス性肝炎に対してはウイルスの増殖を抑える薬、症状を和らげるための薬などが用いられます。
ここで最も重要なのは、自己判断で薬をやめたり量を調整したりしないこと、そして定期的な通院を必ず続けることです。
肝臓機能障害は、症状が安定しているように見えても、水面下で静かに進行している可能性があります。
定期的に通院し、血液検査などで状態を確認することで、病状の変化をいち早く捉え、治療方針を適切に見直すことができます。
仕事が忙しいと通院を後回しにしたくなるかもしれませんが、安定した状態で長く働き続けるためには、この定期的なメディカルチェックが不可欠な自己管理の一部であると捉えましょう。
肝臓機能障害者の就労状況と課題
肝臓機能障害を抱える方々が、仕事を継続したり再び職場に戻ったりする際には、さまざまな壁や不安がつきまといます。
近年では、治療の進歩や支援制度の整備により、就労可能なケースも増えてきましたが、職場での理解不足や体力的な制限により、離職を選ばざるを得ない方も少なくありません。
ここでは、現状の課題を整理し、どのような対策が取れるかを考えてみましょう。
就労率と離職率の現状
肝臓機能障害のある方が就労を継続するためには、症状の安定だけでなく、職場環境や労働条件との相性も大きく影響します。
統計によれば、身体障害者全体の有業率は約52.7%であり(令和3年 障害者白書より)、肝臓疾患に限らず、障害のある方の就労環境にはまだ改善の余地があります。
特に肝臓病のように「外見からは分かりにくい」内部障害の場合、病気への理解不足から、配慮を得られず離職に至るケースもあります。
仕事上の困難(体力低下、通院への配慮等)
では、具体的に仕事上でどのような困難が生じるのでしょうか。
多くの方が直面する課題として、以下のような点が挙げられます。
- 体力の低下や疲労感:
肝機能の低下は、エネルギー不足や有害物質の蓄積により、慢性的なだるさや疲れやすさに直結します。
「以前は当たり前にできていた残業が難しい」「通勤だけで疲弊してしまう」「午後は集中力が続かない」といった体力的な問題は、仕事のパフォーマンスに直接影響を与えます。
- 定期的な通院時間の確保:
肝臓機能障害の管理には、定期的な通院と検査が欠かせません。
しかし、仕事を始めると「平日に休みを取りづらい」「何度も休暇を申請することに罪悪感を覚える」といった壁に直面することがあります。
通院と仕事のスケジュール調整は、両立における大きな課題の一つです。
- 外見からは分かりにくい障害特性による誤解:
内部障害は「見えない障害」とも言われ、外見からはそのつらさが分かりにくいという特性があります。
そのため、体調不良を訴えても「怠けている」「やる気がない」と周囲から誤解されてしまうケースも少なくありません。
このようなコミュニケーションの壁は、精神的なストレスにも繋がり、職場で孤立してしまう原因にもなり得ます。
就労に向けた支援制度の活用状況
こうした課題を乗り越えるため、国は様々な就労支援制度を設けています。
しかし、現実には「どのような制度があるか知らない」「自分に何が使えるのか分からない」という方が多いのも事実です。
例えば、後ほど詳しく解説する「就労移行支援」のような専門的なサポートがあるにもかかわらず、その存在を知らないまま一人で就職活動を行い、結果的にミスマッチの多い職場を選んでしまい、短期離職に繋がってしまっているケースも見受けられます。
利用できるサポートを正しく知り、積極的に活用していくことが、課題を解決し、自分らしく働き続けるための重要な鍵となります。
次の章では、これらの支援制度について具体的に解説していきます。
肝臓機能障害者の就労支援
肝臓機能障害のある方が安心して働くためには、病状に合った働き方を見つけること、そして就職活動や職場定着を支援する制度やサービスを活用することがとても大切です。
ここでは、障害者手帳や年金の制度、就労移行支援事業所の活用法、そして専門の求人サービスについてご紹介します。
障害者手帳の取得と障害年金の活用
まず、肝臓機能障害がある場合、一定の条件を満たせば「身体障害者手帳」の交付対象となります。
これにより、以下のような公的支援を受けられる可能性があります。
- 障害者雇用枠での就職活動
- 通勤や医療に関する各種割引や助成
- 就労支援サービスの利用
また、働くことが難しい状態の場合は、「障害年金」の対象となることもあります。
障害年金は、生活費の一部を補うことで、療養と社会復帰の準備を両立しやすくする支援制度です。
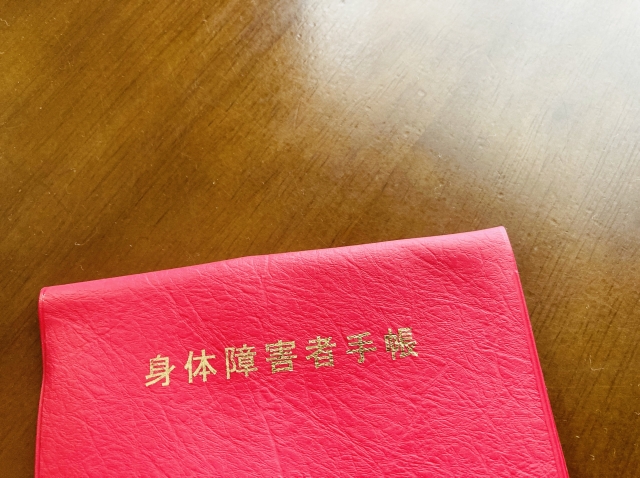
就労移行支援事業所の利用
ビジネススキルの習得と就職活動サポート
就労移行支援事業所では、働くことに不安がある方を対象に、就職に向けた訓練やサポートを行っています。
パソコン操作やビジネスマナーの指導、履歴書の書き方や面接練習など、基礎から実践まで一貫して学べる環境が整っています。
職場体験と実践的なトレーニング
支援事業所によっては、実際の企業での職場体験ができるプログラムもあります。
これにより、自分に合った職種や働き方を事前に確認することができるため、ミスマッチによる早期離職を防ぐ効果もあります。
就職後の定着支援
就職した後も、支援員による定期的な面談や職場との調整サポートが受けられる「定着支援サービス」が用意されています。
職場で困ったことがあっても一人で抱え込まず、相談できる窓口があることで、安心して働き続けることができます。
障害者雇用求人専門サイト・エージェントの活用
肝臓機能障害をお持ちの方の就職活動において、障害者雇用求人に特化した専門サイトやエージェントの活用は非常に有効です。
これらのサービスでは、一般には公開されていない非公開求人や、障害への理解がある企業の求人を多数取り扱っています。
専任のキャリアアドバイザーが、あなたのこれまでの経験やスキル、そして体調や希望を丁寧にヒアリングし、最適な求人を紹介してくれます。
また、履歴書・職務経歴書の添削や面接対策はもちろんのこと、企業への障害に関する配慮事項の交渉なども代行してくれるため、安心して転職活動を進めることができます。
あなたの就職・復職をサポートする情報が満載!
肝臓機能障害者の働き方と職場での配慮
肝臓機能障害がある方が安定して働くには、自身の体調に合った柔軟な働き方と、職場の理解・配慮が重要です。
「無理をせずに働ける環境」を整えることで、病状を悪化させずに、長く仕事を続けることが可能になります。
ここでは、肝臓機能障害者にとって有効な働き方や、企業に求められる配慮について解説します。
テレワークなど柔軟な働き方の導入
最近では、テレワーク(リモートワーク)やフレックスタイム制など、柔軟な働き方を導入する企業が増えています。
これらの働き方は、肝臓機能障害をお持ちの方にとって、大きなメリットがあります。例えば、テレワークであれば、自宅で仕事をすることで、通勤の負担を軽減したり、体調がすぐれない時に休憩を挟んだりしやすくなります。
また、フレックスタイム制であれば、通院の予定に合わせて勤務時間を調整するなど、自身の体調管理を優先しながら働くことが可能です。
このような柔軟な働き方を導入している企業を選ぶことも、安心して長く働くための一つの選択肢となるでしょう。

通院や体調管理に対する配慮
勤務時間の調整と休憩の確保
肝臓機能障害のある方は、定期的な通院が必要だったり、疲労を感じやすかったりするため、勤務時間や休憩の取り方に配慮が求められます。
- 通院日には有給休暇や時間休の取得をしやすくする
- 業務の合間にこまめな休憩時間を設ける
- 症状に応じて時短勤務制度を活用する
このような働き方の工夫により、治療と仕事を両立することが可能になります。
アルコールを伴う接待の制限
ビジネスシーンでは飲酒を伴う接待が行われることもありますが、肝臓疾患のある方には大きなリスクとなります。
そのため、
接待を断ることができる職場の風土
代替の会食(ノンアルコールの場)への理解
といった「飲酒を前提としない働き方」への意識改革も、職場に求められる配慮の一つです。
周囲の理解を深めるための情報共有と教育
見た目にはわかりづらい障害である肝臓機能障害においては、周囲の理解が不足しやすい傾向があります。
そのため、本人が無理なく開示できる範囲で、職場に対して病状や必要な配慮を伝えることが重要です。
また企業側としても、障害特性への理解を深めるための研修やマニュアル整備を進めることが求められています。
配慮事項を明文化し、同僚や上司が共有できるようにする
支援者(ジョブコーチなど)との連携でトラブルを未然に防ぐ
これにより、肝臓機能障害を持つ方が、安心して能力を発揮できる環境が整いやすくなります。
まとめ:自身に合った働き方の実現と周囲の支援が鍵”
肝臓機能障害を持ちながら働くことは、決して簡単なことではありません。
日々の体調変化や治療との両立、職場での理解不足など、乗り越えるべき課題が多く存在します。
しかし、自身の状況に合った働き方を選び、必要な支援や制度を上手に活用することで、安定した就労は十分に可能です。
本文でご紹介したように、
障害者手帳や障害年金の活用
就労移行支援事業所でのスキル習得や職場体験
障害 者 トライアル 雇用などの制度
テレワークや時短勤務といった柔軟な働き方
といった選択肢を組み合わせることで、「自分らしく、安心して働く」ことが実現しやすくなります。
また、企業や周囲の人々の理解も欠かせません。症状が目に見えにくい肝臓機能障害だからこそ、オープンな対話と相互理解が信頼関係の鍵となります。
そして、就職活動を始める際には、肝臓機能障害に理解のある企業を紹介してくれる専門サービスの活用が非常に心強い味方になります。
中でも、「スグJOB(https://sugujob.jp/shougaisha/)」では、あなたの体調や希望に寄り添った就職支援を提供しています。
専門のキャリアアドバイザーがサポート
病状への理解がある企業の紹介
就職後も安心のフォロー体制
就労への一歩を踏み出すことに迷いがある方も、まずは相談してみることが、未来を切り拓く第一歩です。
あなたの強みと可能性を活かし、自分らしい働き方を一緒に見つけていきましょう。

⇒障害者採用枠求人をお探しならスグJOB障害者

スグJOBは求人数トップクラス!
障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ
障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ
この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。










