
【最新】障害者雇用促進法とは—法定雇用率・合理的配慮・納付金と助成金を実務視点で総まとめ
企業の社会的責任(CSR)やダイバーシティ経営が注目される中で、障害者雇用促進法とはどのような法律なのかを正しく理解することは、すべての人事・労務担当者にとって不可欠です。
本法は、単なる雇用義務ではなく、障害の有無にかかわらず誰もが安心して働ける社会を支える基盤法です。
2025年現在、法定雇用率の引き上げや合理的配慮の明確化、除外率制度の縮小など、企業に求められる実務対応の難度は年々上がっています。
一方で、未達企業への納付金や達成企業への調整金・報奨金、各種助成金など、実務的なインセンティブ構造も整備されています。
本コラムでは、複雑な障害者雇用促進法の基礎から実務対応までを、最新情報とともに整理しました。
採用・定着・制度活用のポイントを、企業担当者の目線でわかりやすく解説します。

障害者雇用促進法とは何か—法律の目的と社会的意義を正しく理解する
障害者雇用促進法の正式名称と制定の歴史的背景
障害者雇用促進法の正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。
1960年(昭和35年)、前身となる「身体障害者雇用促進法」が制定されました。
この法律は、当初は第二次世界大戦で負傷した方など身体障害者の雇用機会の確保を目的としており、法定雇用率の義務は公的機関のみで、民間企業については努力義務となっていました。
その後、1976年の改正で全ての企業が法定雇用率の対象になります。
1987年には名称が現在の「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改正され、対象は身体障害者だけではなく知的障害者や精神障害者を含むすべての障害者へ拡大されました。
1998年には知的障害者が、2018年には精神障害者が、法定雇用率の算定基礎の対象に追加されています。
さらに、2016年には障害者に対する差別の禁止・合理的配慮を義務化するなど、より働きやすい環境を目指す改正が行われています。
このように、障害者雇用促進法は対象・内容ともに社会の変化に応じて拡張されてきました。
現在では、身体・知的・精神の3障害を中心に、その他発達障害者や難病患者なども対象に含み、より幅広い「多様な働き方」を支援する方向へと拡張されています。
根底にはノーマライゼーションの理念があり、障害者権利条約の批准を踏まえて国内法整備が進みました。
企業には、差別の禁止、合理的配慮の提供、雇用機会の確保、職業生活支援体制の整備という責務が課されます。

ノーマライゼーション理念と共生社会の実現に向けた基本的な考え方
障害者雇用促進法の根底には、「ノーマライゼーション」という理念があります。
これは、障害のある人もない人も特別視することなく、社会のあらゆる活動において等しく貢献し参加できる社会を実現するという考え方です。
日本では、国内法整備の一環として、障害者差別解消法や障害者総合支援法とともに、障害者雇用促進法が中心的な役割を担うようになりました。
この法律は単なる「雇用義務」ではなく、共生社会の実現を支える重要な社会インフラです。
企業は「法令遵守」のみならず、「社会的包摂(インクルージョン)」の視点から、障害者の活躍を支援する体制整備を求められています。
障害者雇用促進法が社会全体に果たす役割と企業に求められる責任
障害者雇用促進法は、企業に対して次のような役割と責任を明確にしています。
- 雇用機会の確保:一定規模以上の企業に対し、法定雇用率に基づいた障害者の雇用義務を課す。
- 差別の禁止:障害を理由に採用・待遇などで不利益な取扱いをしてはならない。
- 合理的配慮の提供:障害者が能力を発揮できるよう、職場環境や業務内容を柔軟に調整する義務を定める。
- 職業生活支援体制の整備:相談員の設置や外部支援機関との連携を求める。
これらは単なる法的義務ではなく、企業のESG経営・サステナビリティ戦略にも直結する要素です。
障害者雇用を推進することは、企業価値を高め、社会的信頼を獲得することにもつながります。
障害者雇用促進法の対象となる企業と雇用義務の範囲
障害者雇用促進法とは、企業だけでなく国・地方公共団体・教育機関など、あらゆる事業主を対象にした法律です。
民間企業は常用労働者40人以上で雇用義務が発生し、国・地方公共団体や教育委員会はより高い水準が設定されています。
実務の要点は、自社の常用労働者数の正確な把握と、雇用形態(常用・短時間・有期)の区分管理です。
法定雇用率に基づく「雇用義務数」は毎年6月1日時点で算定・報告します。
(後述する特例子会社の場合は、認定子会社の雇用数を親会社に合算できます)
民間企業・官公庁・教育委員会における対象範囲の違い
障害者雇用促進法の雇用義務の内容や法定雇用率は、事業の性質に応じて異なります。(2025年10月時点)
- 民間企業:障害者雇用率は2.5%で、常用労働者を40人以上雇用している場合に雇用義務が発生します。
- 国・地方公共団体:職員数にかかわらず雇用義務があり、法定雇用率は民間より高く設定されています。
- 教育委員会(公立学校):教職員を含む独自の算定が行われ、文部科学省が監督しています。
このように、法律上は「すべての事業主」が対象ですが、実務上のポイントは従業員数に応じて義務が発生するか否かにあります。
そのため、採用計画や人員配置を考える際は、自社の雇用形態(常用・短時間・契約社員など)を正確に把握することが必要になります。

法定雇用率と従業員規模に応じた雇用義務の発生条件
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率は、事業主が雇用すべき障害者の割合を示す基準です。
この雇用率をもとに、企業は「雇用義務数」を算出し、毎年6月1日時点で報告する義務があります。
2025年10月現在の法定雇用率は以下のとおりです。
| 区分 | 法定雇用率 |
| 民間企業 | 2.5% |
| 国・地方公共団体 | 2.8% |
| 教育委員会 | 2.7% |
さらに、2026年7月には民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられることが決定しています。
この改正により、これまで義務がなかった従業員37.5人以上の企業にも新たに雇用義務が発生します。
例えば、従業員が200人の企業では、
200人 × 2.5% = 5人以上の障害者を雇用する義務があります。
なお、算定対象には原則として常用労働者(週30時間以上勤務)が含まれますが、
短時間労働者(週20〜30時間未満)は0.5人としてカウントされます。
この仕組みを正しく理解しないと、実際の雇用率が不足し、納付金の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
特例子会社制度の仕組みと適用条件
企業グループ全体での障害者雇用を促進するために設けられているのが、特例子会社制度です。
これは、親会社が障害者の雇用を目的として設立した子会社を「特例子会社」として厚生労働大臣の認定を受けることで、その子会社に雇用されている障害者を親会社の雇用率に合算できる制度です。
特例子会社として認定されるには、次のような条件を満たす必要があります。
- 親会社と密接な経営関係(株主総会の議決権の過半数を親会社が有しているなど)があること。
- 親会社からの役員派遣など、親会社との人的関係が緊密であること。
- 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。
- 雇用されている障害者のうち、重度身体障害者、または知的障害者および精神障害者の割合が30%以上であること。
- 障害者の雇用管理を適正に行うことができること。
この制度は、製造・清掃・データ入力・事務代行などの分野で広く活用されており、大企業を中心にグループ単位での雇用率達成を実現する重要な仕組みとなっています。
一方で、特例子会社の運営には、独自の管理コストや労務対応も発生します。
そのため、設立を検討する際は、自社の雇用方針や障害者人材の活躍領域を明確化したうえで慎重に判断する必要があります。
障害者雇用促進法で定められている対象障害者の範囲
障害者雇用促進法とはどんな法律なのか、理解を深めるうえで重要なのが、そもそもどのような人が“障害者”として雇用義務の対象になるかという点です。
結論としては、雇用義務の算定対象は、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方です。

算定上、手帳未取得者は原則カウント外となります。
また、週20時間未満の勤務者については、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である方は0.5人としてカウントできます。
誤算定は報告誤りや未達指摘のリスクとなるため、契約・時間数・期間などの詳細を見ていきましょう。
身体障害者・知的障害者・精神障害者の具体的な定義
法律上の定義は、主に以下の3区分に分類されます。
| 区分 | 根拠法 | 認定方法 |
| 身体障害者 | 身体障害者福祉法(第4条) | 各都道府県・政令市が交付する「身体障害者手帳」 |
| 知的障害者 | 療育手帳制度について(厚生事務次官通知) | 知的障害者判定機関による判定(都道府県知事等による療育手帳の交付) |
| 精神障害者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第5条) | 「精神障害者保健福祉手帳」により確認 |
つまり、手帳制度を通じて公的に認定された人が原則として雇用義務の対象になります。
また、身体障害・知的障害・精神障害のいずれか1つに限らず、複数の障害を併せ持つ重複障害者も対象となります。
特に近年は、うつ病や双極性障害などの精神障害者の雇用が増加しています。
厚生労働省によると、2023年度の統計では、精神障害者の数は障害者雇用全体の約6割を占めるまでに拡大しています。
これは企業が「精神・発達障害者への理解を深める」取り組みを進めていることの表れでもあります。
手帳を持たない障害者とノーマライゼーションの観点からの雇用促進
一方で、障害者手帳を持たないが、就労上の支援が必要な人も増えています。
たとえば、障害の診断を受けていても症状の程度が低く手帳を取得していない人や、難病・高次脳機能障害などで生活に制約がある人などが該当します。
法律上、これらの人々は「法定雇用率の算定対象外」となりますが、国はノーマライゼーションの理念に基づき、雇用機会の拡大を促す施策を整備しています。
代表的なものに、次のような制度があります。
- トライアル雇用制度:手帳の有無を問わず、一定期間の試行雇用を通じて適性を確認できる。
- 障害者雇用サポート企業認定制度(自治体による):障害者雇用の実績や職場環境整備を評価する仕組み。
- 合理的配慮指針:診断書や手帳がなくても、本人の申告に基づき配慮を行うことを推奨。
このように、手帳の有無に関わらず、「個々の働きづらさに応じた支援」を行うことが今後の企業のあるべき姿といえます。
特に採用担当者は、「本人が働ける環境をどう整えられるか」を重視した対応が求められます。
雇用算定に含まれる障害者と含まれない障害者の区別
障害者雇用促進法では、雇用率を算出する際に算定に含まれる障害者・含まれない障害者の区別が厳密に定められています。
【算定に含まれる障害者】
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を保持している者
- 週20時間以上働く常用労働者(有期・無期を問わず)
- 特例子会社などに雇用され、グループ企業に合算される者
- 重度障害者(カウント上、1人を2人分として扱う)
【算定に含まれない障害者】
- 手帳未取得者(診断書のみの人)
- 雇用契約期間が1年未満(常用雇用者でない)の者
- 週20時間未満勤務の者(ただし重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者は0.5人としてカウント)
この区別を誤ると、障害者雇用状況報告書の誤提出や雇用率未達成の指摘を受けるリスクがあります。
実務では、雇用契約書の労働時間・勤務日数・雇用期間の確認を徹底することが重要です。
障害者雇用促進法における企業の4つの基本義務
障害者雇用促進法は、単に「障害者を一定割合で雇えばよい」という制度ではありません。
企業には、雇用から職場定着まで一貫した支援体制を整える法的責任が課されています。
ここでは、法律で明確に定められている4つの基本義務を、実務の視点で整理します。

1.雇用率制度の遵守と障害者の安定した雇用確保
まず最も基本となるのが、法定雇用率の遵守義務です。
民間企業であれば法定雇用率は2.5%となり、従業員40人以上の規模で雇用義務が発生します。(2025年10月現在)
もし雇用率を満たしていない場合、障害者雇用納付金制度による納付義務が生じるほか、厚生労働大臣による指導・勧告・企業名公表といった措置を受ける可能性もあります。
しかし、単に数値を満たすだけでは十分ではなく、雇用後に短期離職が相次ぐようでは、本来の趣旨である「安定した雇用の確保」とは言えません。
企業は、採用後の職場定着支援(業務内容の調整・メンター配置など)を実務として組み込むことが求められます。
2.差別禁止と合理的配慮の提供義務の具体的な内容
2016年の法改正以降、障害者雇用促進法では「差別の禁止」と「合理的配慮の提供義務」が明文化されました。
差別禁止義務とは
障害を理由に、採用・昇進・給与・雇止めなどで不利益な扱いをしてはならないという原則です。
例:
- 「車椅子の方は応募不可」といった募集要項の記載
- 面接で障害の有無だけを理由に不採用とする行為
合理的配慮の提供義務とは
障害のある人が職場で能力を発揮できるように、過度な負担にならない範囲で環境や業務を調整することを指します。
具体例としては、次のような対応が求められます。
- デスクや動線のバリアフリー化
- 聴覚障害者への筆談・チャットツール利用
- 精神障害者への勤務時間・休憩配慮
- 発達障害者への明確な指示文書化 など
重要なのは、一律の対応ではなく個々の状況に応じた調整を行うことです。
企業には「合理的配慮指針」に基づき、本人と対話しながら支援内容を決定する義務があります。
3.障害者職業生活相談員の選任と社内体制の整備
障害者を5人以上雇用している企業は「障害者職業生活相談員」の選任が義務付けられています。
これは、障害者本人の職業生活上の悩みを受け止め、職場環境改善や上司との調整を行う役割を担うポジションです。
選任された相談員は、都道府県労働局や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する指定講習を受講する必要があります。
相談員制度を形式的に置くだけでなく、実際に機能する仕組みとして運用することが企業の信頼性を高めます。
さらに、障害者雇用推進担当者や産業医、産業カウンセラーなどと連携する「社内支援ネットワーク」を整備することで、雇用から定着・キャリア形成までの一貫支援体制を実現できます。
4.障害者雇用状況報告書の提出義務
常用労働者40人以上のすべての企業は、毎年6月1日時点の雇用状況を報告する義務があります。
この報告はハローワークを通じて行い、厳密に管理されています。
なお、雇用している障害者が0人であっても報告が必要です。
もし、虚偽の報告や未提出が発覚した場合、厚生労働省による立入検査・報告徴収命令・勧告・企業名公表が行われる可能性があります。
また、改善命令に従わない場合には、30万円以下の罰金(第86条)も科されます。
つまり、雇用状況報告は単なる事務手続きではなく、企業の法令遵守意識を問われる重要な実務です。
報告内容の正確性を保つためには、労務担当者だけでなく、人事・経理・現場部門との情報共有を徹底し、雇用台帳・勤務時間・契約内容の整合性を確認する社内プロセスを構築しておくことが必要になります。
障害者雇用率(法定雇用率)の仕組みと計算方法
障害者雇用促進法における「法定雇用率」は、事業主が雇用すべき障害者の割合を定めた基準であり、
企業の障害者雇用の現状を測る最も基本的な指標です。
この制度を正確に理解していないと、未達による納付金徴収や企業名公表のリスクが生じるため、人事・労務担当者は計算方法と最新スケジュールを正しく把握しておく必要があります。

法定雇用率の現状と2026年までの引き上げスケジュール
厚生労働省は、障害者雇用の実態や労働人口の変化を踏まえ、段階的に法定雇用率を引き上げています。
2024年4月時点の法定雇用率と、今後の改定スケジュールは次の通りです。
| 区分 | 2024年4月〜 | 2026年7月〜 |
| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |
| 国・地方公共団体 | 2.8% | 3.0% |
| 教育委員会(公立学校) | 2.7% | 2.9% |
この改正により、これまで雇用義務のなかった従業員37.5人以上の企業にも新たに義務が生じます。
つまり、今後はより多くの中小企業にも法定雇用率達成が求められる時代となります。
人事労務担当者の方は今のうちから採用・職場環境整備・支援機関連携を計画的に進めておくことが重要です。
実雇用率の算出方法と雇用義務数の計算例
障害者雇用促進法に基づき、各企業は「実雇用率(=現在の障害者雇用割合)」を算出し、その数値が法定雇用率を上回っているかどうかを確認する必要があります。
【基本式】
実雇用率 = (障害者雇用数 ÷ 常用労働者数) × 100
ただし、「障害者雇用数」には、次に示すカウント上の特例が含まれます。
- 重度身体障害者・重度知的障害者:1人を「2人分」として算定
- 短時間勤務者(週20〜30時間未満):1人を「0.5人分」として算定
【計算例】
常用労働者数:200人
雇用している障害者:
・身体障害者2人(うち1人は重度)
・精神障害者2人(週20時間の短時間勤務)※当面の措置として、精神障害者は条件を満たせば短時間勤務でも1人としてカウントします。
計算式:
(身体障害者1人×1) + (重度身体障害者1人×2) + (精神障害者2人) = 5人
よって、実雇用率=(5 ÷ 200) × 100 = 2.5%
この例では、法定雇用率2.5%と同値のため、2025年10月現在では雇用義務達成となります。
ただし2026年の引き上げによって未達成になることが見込まれるため、早急に対応が必要になります。
短時間勤務者や重度障害者のカウント方法と特例措置
障害者雇用促進法では、障害の程度や勤務時間に応じてカウント上の特例措置が設けられています。
これは、障害の内容によって働ける時間や業務内容に制限があるケースを考慮した仕組みです。
| 区分 | カウント方法 | 備考 |
| 重度身体障害者・重度知的障害者(週30時間以上勤務) | 2人分 | 通常勤務の場合でも2倍カウント |
| 重度身体障害者・重度知的障害者(週20〜30時間未満) | 1人分 | 短時間でも1人分として計上可 |
| その他の障害者(週20〜30時間未満) | 0.5人分 | 雇用率算定上は半人カウント |
| 週20時間未満勤務 | カウント外 | 算定対象外 |
また、企業グループで特例子会社を設けている場合、その子会社の障害者雇用数を親会社の雇用率に合算できます。
これにより、企業全体での雇用率達成が柔軟に可能となります。
ただし、算定ルールは年度ごとに細かい通達で更新されるため、最新情報は必ず厚生労働省またはハローワークの公式サイトを確認しましょう。
障害者雇用促進法の改正点と今後の動向
障害者雇用促進法は、社会情勢や障害者の就労環境の変化に合わせて、段階的に改正が続けられている法律です。
特に2023年以降は、「法定雇用率の引き上げ」「合理的配慮の明確化」「除外率制度の見直し」など、企業の実務に直接影響する重要な改正が相次いでいます。
ここでは、担当者が押さえておくべき最新の改正ポイントと、今後の方向性を整理します。
2023年以降の改正内容と最新施行スケジュール
2023年の改正は、近年の障害者雇用の実態を踏まえた大規模な制度見直しとなりました。
主な改正内容は以下の通りです。
| 改正項目 | 改正概要 |
| 雇用の質向上のための事業主の責務の明確化 | 「職業能力の開発及び向上に関する措置」が事業主の義務として条文で明確化される |
| 法定雇用率の引き上げ | 民間企業:2.5%(2024年4月~)→2.7%(2026年7月~) |
| 週20時間未満の重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例 | 週の労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を、0.5人としてカウントできる |
| 関連助成金の新設及び拡充 | 障害者雇用相談援助助成金の新設、障害者雇用調整金の調整、報奨金の調整など |
このように、単なる雇用義務から「雇用の質の向上」へ重点がシフトしているほか、実質的なインセンティブ構造も整備されています。
2025年4月からの除外率制度の縮小・廃止の流れ
「除外率制度」とは、障害者の雇用が物理的に難しいとされる業種(例:建設業・運輸業など)について、一定割合を雇用義務の計算から除外できる制度です。
しかし、この制度は「障害者の就労機会を制限している」との批判があり、政府は2025年4月から段階的に縮小・廃止に向けた見直しを進めています。
これにより、これまで除外対象だった企業にも、実質的な雇用義務が拡大します。
つまり、今後は「除外だから関係ない」という姿勢は通用せず、どの業種でも障害者雇用のチャンスを広げる努力義務が求められる時代に入っています。
合理的配慮義務の明確化と企業への影響
今回の改正の中でも特に注目されているのが、合理的配慮義務の明確化です。
従来は「努力義務」とされていた部分も、改正により対話義務を伴う法的義務として位置付けられました。
企業は、以下の3ステップで合理的配慮を提供することが求められます。
- 本人からの申出(障害の内容・希望する配慮の説明)
- 事業主との建設的な対話(職務内容・業務範囲を考慮した調整)
- 過重な負担とならない範囲で配慮提供(設備・勤務形態・人的支援の検討)
このプロセスは「合理的配慮指針」として厚生労働省が示しており、対応を怠った場合は「差別的取扱い」として行政指導の対象となる可能性があります。
たとえば、
- 視覚障害者への音声読み上げアプリ導入
- 聴覚障害者へのチャット面談・テキスト連絡対応
- 精神障害者への柔軟な勤務開始時間設定
などは、配慮コストを抑えつつ有効な実務対応例です。
今後の採用面接や雇用契約書の段階でも、合理的配慮に関する記載・対話記録の保存が求められることになるでしょう。
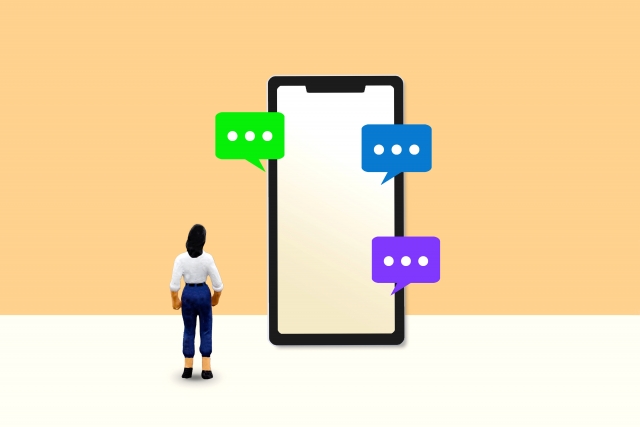
障害者の職業能力開発・キャリア形成を支える新たな制度
改正法では、単に雇用機会を増やすだけでなく、障害者の職業能力向上・キャリア形成支援を重視しています。
主な施策としては、次のような制度が整備されています。
- 職業リハビリテーションの充実
→ 公共職業安定所(ハローワーク)と地域障害者職業センターの連携強化。 - ジョブコーチ支援制度
→ 専門支援員が企業と障害者の間に入り、定着をサポート。 - 障害者トライアル雇用制度の拡大
→ 採用前に実習形式で適性を確認できる制度。 - 職業訓練校・就労移行支援事業所との連携
→ 障害特性に応じたスキル習得・職種マッチングの推進。
これらの取り組みは、「採用後の定着率向上」や「戦力化」につながる投資でもあります。
企業は「単なる義務対応」ではなく、「多様な人材活用による生産性向上」という発想で捉えることが重要です。
企業に課される納付金制度と支援措置の全体像
障害者雇用促進法には、雇用率を達成していない企業から納付金を徴収し、達成企業へ調整金や報奨金を交付する仕組みが設けられています。
これは「障害者雇用納付金制度」と呼ばれ、企業間の負担を公平にしつつ、障害者雇用を経済的に支援する制度です。
法定雇用率を満たす企業が損をしないように設計されており、制度全体を理解することで、助成金との併用によるコスト最適化も可能になります。
障害者雇用納付金制度の仕組みと徴収金額の算出方法
この制度は、「納付金」「調整金」「報奨金」という3つの経済的措置によって構成されています。
基本的な考え方は次の通りです。
- 雇用率未達成の企業 → 納付金を支払う義務がある
- 雇用率を上回る企業 → 調整金または報奨金を受け取ることができる
【納付金の仕組み】
- 対象:従業員100人を超える企業で、法定雇用率を下回る場合
- 金額:1人不足あたり 月額50,000円(年間600,000円)
例:
常用労働者200人の企業で、障害者雇用数が3人(法定雇用率2.5%=5人必要)の場合
→ 不足2人 × 50,000円 = 月額100,000円(年額1,200,000円) の納付が必要
なお、従業員100人以下の企業は納付義務が免除されていますが、調整金・報奨金の支給対象にはなるため、積極的な雇用は大きなメリットになります。
調整金・報奨金の支給条件と受給額の実例
法定雇用率を上回って障害者を雇用している企業には、「調整金」または「報奨金」が支給されます。
これにより、障害者雇用に伴う設備改修・人的支援などの費用を補填できます。
| 区分 | 支給条件 | 支給額(1人あたり/月) |
| 調整金 | 常用労働者100人超の企業が法定雇用率を上回る場合 ※1 | 29,000円 |
| 報奨金 | 常用労働者100人以下の中小企業が一定数以上の障害者を雇用している場合 ※2 | 21,000円 |
※1:支給対象人数が10人を超える場合には、超過人数分への支給額が1人当たり月額23,000円
※2:支給対象人数が35人を超える場合には、超過人数分への支給額が1人当たり月額16,000円
障害者雇用に活用できる助成金の種類と特徴
障害者雇用促進法の下では、雇用納付金制度とは別に、助成金制度も充実しています。
助成金は雇用開始・職場定着・設備改修など、目的ごとに分かれており、条件を満たせば返済不要で利用できます。
主な助成金は以下の通りです。
| 助成金名 | 概要 | 支給上限額 |
| 障害者作業施設設置等助成金 | バリアフリー改修・専用設備の導入などに対して支援 | 上限450万円 |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 障害者を新規雇用した場合に支給 | 最大50万/人
中小企業は最大120万円/人 |
| 職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金 | ジョブコーチ配置による定着支援を行った場合 | 上限3万6千円/1日 |
| 人材確保等支援助成金 | テレワークや在宅雇用に対応する環境整備費を支援 | 上限20万円、目標達成で10万円 |
これらは障害者雇用に関係の深い特化型の支援制度です。
ハローワークやJEEDを通じて申請でき、企業の雇用コストを大幅に軽減します。
在宅就業者特例報奨金・調整金制度の詳細
近年のテレワーク普及を踏まえ、在宅勤務の障害者を対象とする特例報奨金・調整金制度も導入されています。
これは、在宅就業している障害者を雇用している企業に対して、通常の調整金・報奨金に加えて追加支給を行う制度です。
この制度により、「出社が難しい人でも働ける環境づくり」が企業の新たな雇用戦略となりつつあります。
在宅雇用を活用することで、地方在住者や通勤困難な障害者の採用機会を広げることも可能です。
障害者雇用促進法に違反した場合の罰則と企業リスク
障害者雇用促進法は「努力義務」ではなく、企業に明確な法的義務を課す実効性のある法律です。
そのため、雇用率未達成や報告義務違反などに対しては、納付金徴収・勧告・罰金・企業名公表といったペナルティが設けられています。
一方で、こうした違反は「法的制裁」にとどまらず、企業の信用や採用ブランドの失墜にも直結します。
ここでは、障害者雇用促進法に違反した場合に想定されるリスクと、企業が取るべき対策を整理します。

納付金徴収・改善命令・企業名公表の流れ
障害者雇用率を達成していない企業に対しては、まず「障害者雇用納付金」の支払いが義務付けられます。
これは単なる罰金ではなく、雇用率を上回る企業への調整金支給に充てられる「再分配制度」です。
ただし、雇用率未達が長期にわたる場合、厚生労働省は次のような行政措置を段階的に行います。
- 報告徴収命令:未達企業に対して雇用状況の詳細な報告を求める。
- 改善命令:雇用計画の提出・実施を義務付ける。
- 勧告・企業名公表:改善が見られない場合、企業名を厚生労働省サイトなどで公表。
実際、過去には大手企業で企業名が公表された事例もあり、社会的信用の低下や株価への影響、訴訟を招いたケースもあります。
とくに近年はESG投資・サステナビリティ開示が重視されるため、障害者雇用の未達は「ガバナンス上の欠陥」とみなされる傾向が強まっています。
法定雇用率未達成による信用低下と社会的影響
障害者雇用率を満たしていない企業は、法的リスクだけでなく、社会的信用の失墜という重大な経営課題に直面します。
- 取引先や株主からの信頼低下:サプライチェーン全体でCSR評価が行われるため、改善を求められるケースがある。
- 自治体・公共事業の入札制限:入札条件に「法定雇用率達成」を含む自治体も増加。
- 採用ブランドの毀損:ダイバーシティ推進を重視する若年層・求職者から敬遠される傾向。
また、上場企業では「統合報告書」や「人的資本開示」において、障害者雇用率の数値公表が一般化しています。
そのため、雇用率の低さは、企業文化やマネジメント姿勢を問われる象徴的指標にもなり得ます。
逆に、雇用率達成・定着率向上に取り組む企業は、社会的評価が高まり、採用競争力の向上・企業価値の上昇につながる好循環を生み出しています。
罰則規定(30万円以下の罰金)の具体的な違反行為
障害者雇用促進法には罰則規定も定められています。
以下のような行為を行った場合、罰則規定の対象になることがあります。
| 違反行為 | 想定される罰則 |
| 雇用状況報告書の未提出・虚偽報告 | 30万円以下の罰金 |
| 雇用義務違反、改善命令への不履行 | 企業名公表・罰金併科 |
| 差別禁止・合理的配慮義務違反(悪質な場合) | 行政指導、勧告、公表の対象 |
これらは形式的な違反に見えても、企業コンプライアンス全体への重大な影響を及ぼします。
特に上場企業では、監査法人や株主からの指摘対象にもなり得るため、
法務・人事・広報の三部門で情報を共有し、リスク管理体制を明文化することが望まれます。
さらに、2024年以降は「合理的配慮提供義務」が強化されています。
虚偽の報告など悪質な場合は行政指導や社会的批判の対象になる可能性があります。
したがって、企業は「罰則を回避するため」ではなく、法令遵守と社会的信頼の両立を図る姿勢を明確に打ち出すことが求められます。
障害者雇用を成功させるための企業担当者の実務ポイント
障害者雇用促進法を「遵守する」だけでは、企業にとって本当の意味での成功とは言えません。
実務担当者に求められるのは、雇用率の達成とともに、採用後の定着・活躍を実現する仕組みづくりです。
ここでは、現場で成果を出している企業の共通点を踏まえながら、実務で重視すべき4つのポイントを紹介します。
社内理解を深める研修や情報共有の取り組み
障害者雇用を進めるうえで最初の壁となるのが、現場社員の理解不足や偏見です。
採用担当者だけが制度を理解していても、現場が受け入れ体制を整えなければ、早期離職の原因となります。
そのため、企業は次のような「社内啓発・教育」に力を入れることが重要です。
- 障害理解研修:障害特性・合理的配慮・言葉の使い方などを学ぶ
- 管理職向けセミナー:現場リーダーが適切なマネジメントを行えるよう支援
- 当事者講話の実施:実際に働く障害者の声を聞くことで理解を深める
- イントラネットや社内報での情報発信:成功事例や社内支援制度を共有
特に、障害者本人を「特別扱いする」のではなく、チームの一員として受け入れる姿勢を全社員が持つことが、長期定着のカギとなります。

雇用計画の立案と助成金制度の活用方法
障害者雇用は、単発的な採用ではなく、中長期的な「雇用計画」としての設計が必要です。
法定雇用率の引き上げが予定されている今こそ、早期に計画を立て、助成制度を組み合わせてコストを最適化しましょう。
【雇用計画を立てる際の流れ】
- 現在の雇用率・人員構成を分析
- 対象業務の洗い出し(清掃・軽作業・事務補助・データ入力など)
- 必要な職場環境整備(バリアフリー化・設備調整)
- 採用・研修・定着支援までの年間スケジュール作成
- 助成金・報奨金・調整金などの財政支援を活用
活用できる代表的な制度には、以下のようなものがあります。
助成金などの支援は、ハローワークやJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)を通じて申請できます。
担当者は定期的に最新情報を確認し、自社の雇用計画と助成金スケジュールを連動させると効果的です。
採用後の定着支援と離職防止のための工夫
障害者雇用の「成功」とは、採用後に本人が安心して働き続けられることです。
障害者雇用の離職率は高い傾向にあり、採用段階よりもむしろ、入社後のフォロー体制こそが最も重要な要素といえます。
具体的な定着支援策としては、以下の取り組みが有効です。
- メンター制度:直属上司以外に相談役を設けることで心理的安全性を確保
- 定期面談の実施:業務負担・人間関係・健康面などを定期的にヒアリング
- 業務マニュアル・チェックリストの整備:発達障害などで混乱を防ぐ
- 体調変化への早期対応:休職や短時間勤務への柔軟な切り替え
また、障害者職業生活相談員を中心とした社内支援ネットワークを構築し、産業医・産業カウンセラー・人事部門が連携して継続支援を行うことで、離職率を大幅に下げることが可能です。
民間の障害者雇用支援サービスやコンサル活用の重要性
障害者雇用の実務は、法律・助成金・人事・福祉の知識が複合的に求められる領域です。
そのため、すべてを自社だけで完結させるのは難しく、専門機関や民間支援サービスの活用が効果的です。
たとえば、「スグJOB」のような障害者専門の人材紹介サービスでは、
以下のような支援を一括して受けられます。
- 障害特性や配慮事項を踏まえたマッチング
- 事前面談・職場実習によるミスマッチ防止
- 定着支援スタッフによるフォローアップ
- 雇用計画に応じた採用戦略の提案
このように、外部リソースをうまく活用することで、
採用担当者の負担を軽減しつつ、「採用後に活躍できる障害者人材」の確保が可能になります。
まとめ—障害者雇用促進法を遵守し持続的な経営を実現する
障害者雇用促進法とは、単なる法律遵守のためのルールではなく、多様な人材が共に働ける社会を実現するための土台です。
企業にとって障害者雇用は「義務」であると同時に、ダイバーシティ経営・ESG経営・人的資本経営を支える「戦略資源」でもあります。
本記事で解説したように、障害者雇用促進法は以下のような多面的な仕組みを備えています。
- 法定雇用率制度による雇用義務の明確化
- 差別禁止・合理的配慮義務による職場環境整備の促進
- 納付金・助成金制度による経済的支援と公平な再分配
- 職業能力開発・ジョブコーチ支援制度による定着支援
これらの制度を正しく理解し、計画的に活用することで、
企業は「法令遵守」と「経営の持続可能性」を両立させることができます。
法律遵守から“共生経営”へ
これからの時代、障害者雇用は「法令対応」から一歩進んで、“共生経営”の実践へと進化していくでしょう。
共生経営とは、障害者を「支援の対象」ではなく「共に価値を生み出す仲間」として位置づける考え方です。
その実現には、企業のトップマネジメントが率先して方針を明確にし、現場の理解を深め、外部専門機関と連携しながら全社的な支援体制を構築することが不可欠です。
こうした取り組みは、単に社会貢献にとどまらず、社員のエンゲージメント向上・ブランド価値の向上・人材確保の強化といった、経営上の利益にも直結します。
「スグJOB」を活用して障害者雇用を次のステージへ
障害者雇用を成功させるためには、制度理解だけでなく、適切なマッチングと支援体制の構築が重要です。
そこでおすすめしたいのが、障害者のための職業紹介サービス「スグJOB」です。
スグJOBでは、
- 障害特性や職場環境に配慮した求人紹介
- 面接前の個別カウンセリング
- 採用後の定着フォロー
といった支援を通じて、企業と求職者の双方にとって「長く続く雇用関係」を実現します。
法定雇用率の達成にとどまらず、“働きやすく、活躍できる職場づくり”を目指す企業こそ、社会的信頼を得て、持続可能な成長を遂げることができるのです。
最後に
障害者雇用促進法は、今後も社会の変化に合わせて進化し続けます。
企業担当者として大切なのは、「制度が変わるのを待つ」のではなく、先手を打って環境を整備し、柔軟に対応できる体制を整えることです。
障害のある人が自分らしく働ける職場をつくることは、最終的にすべての社員にとっても「働きやすい環境」を生み出します。
障害者雇用促進法の精神である「共生社会の実現」は、企業にとっても新しい価値創造のチャンスです。
ぜひこの機会に、自社の取り組みを見直し、スグJOBと共に、より持続的で人に優しい経営を目指してください。
参考サイト
- 厚生労働省:障害者雇用対策(2025年10月確認)
- 厚生労働省:事業主の方へ ~従業員を雇う場合のルールと支援策~(2025年10月確認)
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(2025年10月確認)
- スグJOB…障害者の求人・雇用・転職サイト

スグJOBは求人数トップクラス!
障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ
障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ
この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。










