
障害者が働く場所がない理由と対策
「働く意欲はあるのに、応募してもなかなか採用されない……」
「ようやく働けたと思ったのに、職場が合わず長く続かなかった」
そんなふうに感じたことがある方は、少なくないのではないでしょうか。
実際、就職活動を進めていくなかで、「自分が安心して働ける場所がない」と感じて、あきらめてしまうケースは決して珍しくありません。
けれども、その背景には、社会の仕組みや企業の体制、そして就職に向けた準備不足など、さまざまな要因が複雑に絡んでいることも多いのです。

本記事では、なぜ「働く場所が見つからない」と感じてしまうのか、その原因をひもときながら、一人ひとりができる準備や行動、そして社会全体としての課題や取り組みについてご紹介していきます。
「働きたい」という前向きな気持ちを、現実の一歩につなげるために。
このページが、あなたの道しるべとなれば幸いです。
障害者の雇用の現状
障害者雇用という制度は、さまざまな法律によって支えられた制度です。
しかし法制度が整っていても、障害者の方が「働く場所がない」と感じる背景には、現実とのギャップが存在します。
この章では、障害者雇用の現状について解説していきます。
自分に合った職場を探すため、まずは現状について知っておきましょう。
法定雇用率と障害者雇用数の推移
日本では、障害のある方の就労を支えるために、「障害者雇用促進法」が整備されています。
この法律の第43条では、一定規模以上の企業に対して、障害者を一定割合で雇用することが義務付けられています。
2024年4月からは、この法定雇用率が民間企業で2.5%に引き上げられました。
また、2026年7月からは民間企業で2.6%にさらに引き上げられます。
しかしながら、厚生労働省の発表によると、2024年の時点で半分以上の企業(約54%)が法定雇用率を達成できていないというデータがあります。(「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」|厚生労働省|2025年8月確認)
一方で、障害者の雇用数は年々増えており、2024年には約67万人となり、21年連続で過去最多を更新しています。
つまり制度は整ってきているものの、企業現場ではその運用が十分に行き届いていないのが現状といえるでしょう。

障害種別の就労状況
障害のある方の就労状況を、障害の種類ごとに見てみると、それぞれに大きな違いがあることがわかります。
一般的に、身体障害のある方は就労率が高めで、企業も比較的受け入れに前向きな傾向にあります。
これは、業務によっては配慮の工夫次第で、健常者と同等のパフォーマンスが期待できるためです。
一方で、精神障害や発達障害をもつ方の就労率は低く、職場定着の難しさが課題となっています。
これには、症状の波やストレスへの耐性といった要素が関係しており、職場側の理解や配慮が十分でないことも、定着の難しさにつながっています。
なお、「労働施策総合推進法」第30条の2では、企業に対して合理的配慮の提供が努力義務として求められていることも、あわせて知っておきたいポイントです。
正規・非正規の割合
障害のある方の働き方には、非正規雇用の割合が高いという傾向があります。
たとえば2023年のデータによれば、身体障害者の正規雇用率は59.3%と比較的高いものの、精神障害者では約32.7%、発達障害者では36.6%、知的障害者では約20.3%にとどまっています。(令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します|厚生労働省|2025年8月確認)
この背景には、「まずはお試しで」という意味合いから非正規で雇用するケースや、企業側の体制が整っていないことによる不安感などがあります。
非正規雇用は柔軟性がある一方で、収入の不安定さやキャリアアップの難しさといった課題も抱えています。
そのため、正社員への転換支援や、評価制度の明確化・公平化がこれからの重要なテーマとなってくると予想されます。
平均賃金と一般雇用との差
障害者雇用においては、賃金格差も見逃せない問題です。
たとえば、週30時間以上働いている身体障害者の平均月収はおよそ21万5千円、精神障害者の平均賃金は12万5千円という調査結果があります。(「平成 30 年度障害者雇用実態調査結果 」|厚生労働省|2025年8月確認)
知的障害や精神障害を抱える方の平均賃金は、障害者雇用の枠組みの中で見ても比較的低く、生活の安定に大きな不安を抱えるケースもあります。
また身体障害者の方の平均賃金は障害者雇用の中では高いですが、一般雇用よりも低めに設定されている求人も多くあります。
この差は、職種や業務内容、雇用形態の違いに加え、昇給制度や評価の不備、スキルアップの機会の不足などが関係しています。
賃金格差を是正するためには、企業の意識改革に加えて、障害者のキャリア形成を支える制度的な支援も必要不可欠です。
障害者の働く場所が見つからない理由
「求人はあるのに、自分に合う職場が見つからない……」
そう感じる方は、決して少なくありません。
近年は障害者雇用される方は増加傾向にありますが、企業の理解不足などによって、結果的に「障害者の方が働く場所がない」状況が生じています。
ここでは、その背景にある主な要因について、いくつかの視点から解説していきます。
法定雇用率未達成企業の存在
先ほども触れたように、障害者の雇用を義務付ける「法定雇用率」は2024年から2.5%に引き上げられました。
しかし、現実にはこの基準を達成していない企業が約54%も存在します。(「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」|厚生労働省|2025年8月確認)
つまり、雇用義務のある企業のうち、約2社に1社がまだ障害者を十分に雇用していないということになります。
これにより求人の選択肢が限られてしまい、本来雇用されるはずの障害者に「働く場所がない」という状況が続いています。
また、形式的に雇用していても、実質的な受け入れ体制が整っていないケースもあります。
このような企業に応募してしまうと、採用にはつながらなかったり、定着できずに早期離職につながったりするリスクが高くなってしまいます。

企業規模による取り組み格差
障害者雇用への取り組みは、企業の規模によっても差が大きいのが現状です。
たとえば、大手企業では専門の支援担当者がいたり、制度や研修が整備されていたりするケースが多くあります。
その一方で、中小企業では採用ノウハウや体制が不十分で、受け入れに消極的な傾向も少なくありません。
特に、職場の人員や設備に余裕がない場合、障害に配慮した勤務体制を整えること自体が難しいという現実があります。
その結果、中小企業の求人が多くても、応募先として選びにくいという状況につながっているのです。
障害特性に応じた職務開発の難しさ
障害の内容や特性は人によってさまざまで、一人ひとりに合った仕事を用意するには、企業側にとっても工夫と準備が必要です。
しかし実際には、「この仕事は定型的な業務だから変更できない」といった固定的な考え方が、まだまだ根強く残っています。
適切な配慮と受け入れ態勢の不足
たとえば、「静かな環境で働きたい」「朝の混雑を避けたい」などの配慮を求めても、制度がないから無理です、と断られてしまうケースもあります。
これは、企業が障害に対する理解や準備を十分にしていないために起こることです。
本来であれば、合理的配慮として検討・実施されるべきことでも、知識やリソースの不足により実現されていない現場が多く存在しています。
このような環境では、自分らしく働くことが難しくなってしまいます。
離職率の高さと職場定着の課題
就職できた場合でも、定着できなかったことで再び「働く場所がない」と感じる方も少なくありません。
離職の原因には、「業務が合わなかった」「周囲との人間関係に悩んだ」「配慮が受けられなかった」など、さまざまな事情があります。
実際、障害者雇用での1年以内の離職率は4割というデータがあります。(「障害者の就業状況等に関する調査研究」|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構|2025年8月確認)
障害者雇用を含む全ての被雇用者の平均は8.4%であり、比較するとかなり高い水準であることがわかります。(「令和6年上半期雇用動向調査結果の概要」|厚生労働省|2025年8月確認)
特に企業規模が小さい企業で離職率が高くなる傾向にあり、この背景には、事前のマッチング不足や、入社後のサポート体制の不備があります。
長く働き続けるためには、「入ること」よりも「続けられること」を重視した職場選びが大切になります。
専門的な人材マッチングの必要性
こうした課題を乗り越えるためには、自分に合った職場を見極める専門的な支援が必要になります。
障害者雇用に詳しいキャリアアドバイザーや就労支援員は、本人の特性と企業の環境を総合的に見て、ミスマッチを防ぐサポートをしてくれます。
一般的な求人サイトだけでは、職場の雰囲気や実際の配慮内容まではわかりにくいものです。
だからこそ、障害者専門の就職支援サービスを活用することが、「働ける場所」を「働きやすい場所」へと変える第一歩になるのです。
個人に必要な働く準備
「働く場所がない」と感じるとき、自分自身にもできる準備があることをご存じでしょうか。
就職活動は、企業側の受け入れ体制だけでなく、自分自身の理解や備えも必要です。
この章では、就職に向けて個人が取り組める「働く準備」についてご紹介します。
自己理解を深める
まず第一に、自分自身の特性や希望を知ることが、ミスマッチを防ぐための第一歩になります。
「自分は何が得意なのか」「どんな配慮があれば働きやすいのか」などを明確にしておくことで、職場選びがしやすくなります。
得意な作業の棚卸し
これまでに経験した仕事や、学校・実習などで行った作業を振り返ってみましょう。
「単純作業を繰り返すのが好き」「パソコン作業が得意」「人と話すより黙々と集中したい」など、自分にとって負担になりにくい仕事を探すヒントになります。
書き出してみることで、自信にもつながりますし、面接や職場実習でも自分をうまく伝える材料になります。
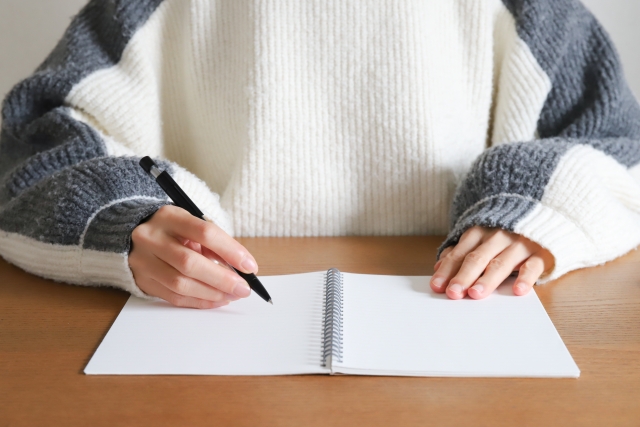
必要な配慮の明確化
苦手なことや、困りごとを整理しておくことも重要です。
「長時間立ちっぱなしはつらい」「対人対応が多いと疲れる」「環境音に敏感で集中しづらい」など、自分が困る場面を具体的に思い浮かべてみてください。
そのうえで、「こういう配慮があれば助かる」といった形で支援の方法を整理しておくと、企業に伝えやすくなります。
これは、合理的配慮をお願いする際の大切な材料にもなります。
スキルアップと資格取得
就職の選択肢を広げるためには、スキルを身につけることも有効です。
たとえば、パソコン操作(WordやExcel)、事務補助、軽作業、接客など、障害者雇用でニーズの高いスキルを磨いておくと、応募できる職種が増えていきます。
また、「MOS」「コミュニケーション検定」「ビジネスマナー検定」など、就職に役立つ資格を取得することで、面接でのアピールにもなります。
無理なく取り組める範囲から、少しずつチャレンジしてみましょう。
ビジネスマナーの習得
働き始めると、上司や同僚、お客様などとのやりとりが日常的に発生します。
そのため、基本的なビジネスマナーを身につけておくことは、とても大切です。
たとえば、あいさつの仕方、報告・連絡・相談のタイミング、身だしなみ、時間の守り方など、日常生活の延長にあるようなことから始めてみましょう。
これらのマナーは、職場での信頼関係づくりにもつながります。
支援機関では、こうしたマナーを実践的に学べるプログラムもあるので、活用してみるのもおすすめです。
自己PRの練習
就職活動では、自分を「言葉で伝える」ことが必要になります。
面接の場面では、「これまでの経験」「自分の強み」「できること」「必要な配慮」などを限られた時間で話さなければなりません。
そのためには、あらかじめ自己PRの内容を準備し、何度か練習しておくことが大切です。
支援員や家族、友人に聞いてもらって、フィードバックをもらいながら修正することで、自信をもって面接に臨むことができます。
このように、自分のことをしっかり理解し、伝える準備をしておくことで、働きやすい場所との出会いがぐっと近づきます。
「ちょっと不安……」という方も、支援機関やキャリアアドバイザーに相談しながら進めていけば大丈夫です。
就労に向けた行動のポイント
「働きたい」という気持ちを行動に移すとき、どこから始めればよいか迷ってしまうこともあるかもしれません。
ここでは、実際の就職活動に向けて、どのような支援機関や機会を活用すればよいかを、具体的にご紹介していきます。
ハローワークの専門窓口の活用
まず最初に活用したいのが、全国にあるハローワークの「障害者専門窓口」です。
ここでは、障害のある方を対象とした求人を紹介してくれるだけでなく、就職に関する相談や模擬面接、職業訓練の案内など、幅広いサポートを受けることができます。
担当の職員は、障害特性への理解もあり、配慮が必要なポイントや、企業との調整なども丁寧に対応してくれるのが特徴です。
一人で進めるのが不安な方こそ、早めに相談しておくと安心です。

就労移行支援事業所の利用
障害福祉サービスのひとつである「就労移行支援事業所」も、就職準備に役立つ場です。
ここでは、通所しながらビジネスマナーの習得、スキル訓練、履歴書の作成支援、面接練習など、就職に必要な力を総合的に身につけることができます。
また、スタッフが企業との連携や就職後の定着支援まで対応してくれるため、長く働き続けたい方にとっても心強い存在です。
障害福祉サービス受給者証が必要ですが、市町村の福祉窓口で相談すれば手続きが可能です。
自分のペースで就職活動を進めていきたい方におすすめです。
障害者向け合同面接会への参加
就職活動を一歩進める場として、「障害者向け合同面接会」があります。
これは、複数の企業が一堂に会し、障害のある求職者と直接面談できるイベントです。
書類選考を免除してもらえるケースも多く、初めての面接を経験する場としても活用しやすいのが特徴です。
また、その場で企業の人事担当と話すことで、職場の雰囲気や受け入れ体制の確認もできるというメリットがあります。
ハローワークや自治体、支援機関が主催することが多いので、定期的に情報をチェックしておきましょう。
企業見学・職場実習への応募
気になる企業が見つかったら、実際に見学や職場実習に参加してみるのも有効です。
求人票や面接だけではわからない「実際の現場の雰囲気」や「一緒に働く人たちの様子」を、自分の目で確認できます。
就職後のミスマッチや早期離職を防ぐことにもつながります。
実習から雇用につなげる工夫
職場実習を受け入れている企業の中には、その後の採用を見据えて実習を実施しているところもあります。
ですから、実習の場では積極的に取り組む姿勢を見せることが大切です。
また、支援員やアドバイザーに相談しながら、実習先に自分の希望や配慮が伝わるよう工夫することで、そのまま採用につながるケースもあります。
自分にとって「働きやすい場所」かどうかを見極める機会として、ぜひ前向きに活用してみてください。
当事者会の活用
就職活動は、時に孤独を感じることもあります。
そんなとき、同じような立場の仲間とつながることができる「当事者会」や「ピアサポートの場」が、心の支えになることがあります。
そこでは、実際に就職した人の話を聞いたり、困っていることを共有したりすることができます。
「こんな働き方もあるんだ」「こんな工夫で乗り越えたんだ」という具体的な体験談は、きっとあなたの視野を広げてくれます。
一人で抱え込まず、仲間と情報を交換しながら前に進むことも、大切な行動のひとつです。
キャリア形成のための視点
「とにかく働ければいい」──そう思って始めた仕事でも、長く続けるうちに「もっと自分らしく働きたい」「成長していきたい」と感じることは自然なことです。
将来を描く前に「今、働く場所がない」という不安を感じている方もいるかもしれません。
しかし働くことは、生活の安定だけでなく、自分の人生をつくっていくプロセスでもあります。
ここでは、障害のある方が中長期的な視点で「キャリア」を育てていくために、知っておきたいポイントをご紹介します。

目指す仕事と必要なスキルの明確化
まず大切なのは、「どんな仕事をしてみたいか」「将来どうなっていたいか」という自分の目標を少しずつ明確にしていくことです。
最初はぼんやりしていても構いません。
「人の役に立てる仕事がしたい」「体力的に無理のない範囲で働きたい」「家から通える範囲で働きたい」など、具体的な条件を整理するところから始めてみましょう。
その上で、「この仕事に就くには何が必要か?」を考えることで、必要なスキルや資格、経験が見えてきます。
逆算して準備することで、希望の職場に近づくことができるのです。
ロールモデルを探す
自分と同じような立場で働いている人の姿を見ることは、大きな励みになります。
「同じ障害を持ちながら、こんな働き方をしている人がいるんだ」「この人の工夫なら自分も真似できそう」──そんな気づきが、新しい選択肢を教えてくれます。
最近では、障害者雇用で活躍している方のインタビュー記事や動画、SNSなどでもさまざまなロールモデルに出会うことができます。
就労支援機関や当事者会などでも、実際に就職した方の体験談を聞けることがあります。
自分の未来のイメージを広げるために、ぜひ積極的に探してみてください。
雇用形態の理解と活用
「正社員にならなければいけない」と思いがちですが、働き方にはいろいろな形があります。
たとえば、契約社員、パートタイム、アルバイト、業務委託など、自分の体調や生活リズムに合わせた選択肢も検討する価値があります。
特に、体調に波がある方やブランクのある方は、まずは短時間勤務から始めて徐々に慣れていくという方法もあります。
また、契約社員や嘱託職員としてスタートし、実績を積んでから正社員登用を目指すというケースも少なくありません。
大切なのは、自分に合ったペースで無理なく働けること。
就労を「ゴール」ではなく「スタート」として考えることで、継続的なキャリア形成につながります。
キャリアカウンセリングの利用
「自分の適職がわからない」「これからどう進んでいいか迷っている」──そんなときには、障害者支援施設サービスや転職支援サービスでキャリアカウンセリングを受けてみるのも有効な手段です。
キャリアカウンセラーや就労支援員は、あなたの強みや希望、課題を一緒に整理しながら、より良い進路を見つけるお手伝いをしてくれます。
一人で悩んでいると視野が狭くなりがちですが、専門家と話すことで新たな選択肢や可能性に気づけることもあります。
スグJOBなどの就職支援サービスでも、キャリア相談を随時受け付けています。
「誰かに相談しながら進めたい」と感じたら、ぜひ気軽に相談してみてくださいね。

まとめ
「働く場所が見つからない」と感じている障害のある方にとって、その背景にはさまざまな理由があります。
それは、企業側の受け入れ体制の不足、制度の運用上の課題、そして求職者自身の準備や情報不足など、複数の要因が重なっているからです。
たとえ求人票に「障害者雇用あり」と書かれていても、実際の業務内容や職場環境が合っていなければ、安心して働けるとは言えません。
「働く場所がない」と感じてしまうのは、決して本人のせいではなく、社会全体の課題でもあるのです。
ですが今、状況は少しずつ変わりつつあります。
法定雇用率の引き上げや、就労移行支援、専門エージェントの充実など、障害のある方の就労を支える仕組みは、確実に整ってきています。
こうした支援制度やサービスを正しく理解し、自分に合ったものをうまく活用していくことが、これからの働き方において重要になります。
自分らしい働き方を見つけるためには、次の3つの柱が大切です。
自分らしい働き方を実現する3つのポイント
- 自己理解を深めること
自分の得意・不得意や、働く上で必要な配慮を言語化しましょう。 - スキルや知識を身につけること
小さなステップでもかまいません。できることを少しずつ増やしていくことが自信に繋がります。 - 行動に移すこと
専門支援を活用し、実習や面接会などの機会に一歩踏み出すことが大切です。
これから就職を目指す方も、今の職場で悩んでいる方も、「ひとりで悩まない」ことを大切にしてください。
支援機関や専門のアドバイザーは、あなたの「働きたい」という気持ちを全力で応援してくれます。
もし今、「自分に合った仕事が見つからない」と感じている方は、障害者向けの就職支援サービス「スグJOB」の利用もご検討ください。
経験豊富なキャリアアドバイザーが、一人ひとりの特性や希望を丁寧にヒアリングし、求人のご紹介から職場定着までしっかりとサポートいたします。
あきらめずに、
焦らずに、
あなたらしい働き方を、私たちと一緒に見つけていきましょう。

スグJOBは求人数トップクラス!
障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ
障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ
この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。










