
【2025年最新】障害者の方に適した仕事と雇用形態!種類と探し方を徹底解説
「自分に合った仕事って、どんなものだろう?」
「障害があっても、安心して働ける場所ってあるのかな?」
そんな不安を感じている方も、きっと少なくないはずです。
特に、はじめて就職を目指す方や、久しぶりに働くことを考えている方にとって、仕事探しはハードルが高く感じられるかもしれません。
ですが、今は障害者雇用枠や在宅勤務、就労支援サービスなど、障害をお持ちの方が自分に合った仕事を選べる制度や環境が整ってきています。
一般企業での雇用や特例子会社での勤務、在宅勤務といった選択肢も広がりつつあり、障害者の方が自分らしく活躍できる社会が近づいています。
この記事では、障害をお持ちの方が自分らしく働ける仕事を見つけるために、就職・転職活動に役立つ情報をまとめています。
障害をお持ちの方に適した仕事の種類や、雇用形態ごとの特徴、活用できる支援制度などを解説していきます。
記事の最後には、障害者雇用の求人を多数掲載する求人サイト「スグJOB」の活用方法もご紹介しています。
ご自身の働き方を考えるきっかけとして、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
障害者雇用の現状と法的枠組み
障害をお持ちの方が安心して働ける環境を広げるために、日本ではさまざまな法律や制度が整備されています。
その中でも特に重要なのが、「障害者雇用促進法」と「障害者雇用率制度」です。
これらは、企業や公的機関に対して、障害をお持ちの方を一定数以上雇用することを義務づけるもので、働く場を広げるための大切な仕組みといえます。
まずは、こうした制度の内容を知ることで、自分に合った働き方や就職支援の活用方法が見えてきます。
障害者雇用促進法の概要
法律の目的と主要な規定
障害者雇用促進法は、正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」といいます。
この法律の目的は、障害をお持ちの方が職業を通じて自立した生活を送れるように支援することです。
企業には、一定割合以上の障害者を雇用する義務が課されており、これを「法定雇用率制度」と呼びます。
その割合を満たさない場合には「障害者雇用納付金制度」によって金銭的な負担が発生します。
さらに、「合理的配慮の提供」が企業に義務づけられています。
これにより、障害をお持ちの方が働きやすい職場づくりが、企業の法的責任として強化されています。

最新の法改正ポイント
2024年4月の法改正では、障害者雇用に関するいくつかの変更が行われました。
- 法定雇用率が段階的に引き上げられ、2024年には2.5%となりました。2026年には2.7%となる予定です。
- 「発達障害者」や「精神障害者」への配慮が明確に盛り込まれ、より幅広い障害の種類に対応する必要があることが示されました。
- 合理的配慮の対象や提供方法についての基準が明確化され、企業が取るべき対応がより具体的になりました。
これにより、障害者の方の就労環境は一段と整備され、自分らしく働ける仕事の選択肢が広がりつつあります。
障害者雇用率制度と対象者
法定雇用率の推移
障害者雇用率制度とは、企業が雇用する従業員のうち、一定割合以上を障害者として雇用することを義務づける制度です。
以下のように、法定雇用率は段階的に引き上げられています。
- 2021年:2.3%
- 2024年:2.5%
- 2026年(予定):2.7%
この制度により、企業は障害者の採用を積極的に進める必要があります。
雇用率の算定方法
雇用率の算定対象となるのは、身体障害者・知的障害者・精神障害者です。
また、週20時間以上30時間未満で働く短時間労働者は0.5人分としてカウントされます。
企業は、年に1回、障害者の雇用状況をハローワークに報告する義務があります。
障害者手帳の種類と等級
障害者雇用制度の対象となるには、以下のいずれかの手帳を所持している必要があります。
- 身体障害者手帳(1〜6級)
- 療育手帳(A〜B2など、自治体によって異なります)
- 精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)
手帳の種類や等級によって、受けられる支援内容や配慮の内容が異なるため、自分がどの制度に該当するかを把握しておきましょう。
障害者の方に適した仕事の種類
障害をお持ちの方が安心して長く働き続けるためには、ご自身の特性や体調に合った仕事を選ぶことが重要です。
どんな仕事が自分に向いているのかは、障害の内容や程度によって異なります。
そのため、無理のない範囲で、ご自身にとって快適な職種や職場環境を見つけることが望ましいです。
ここでは、障害者雇用でニーズの高い仕事を、以下の4つに分類してご紹介します。
- オフィスワーク
- 技術職
- 現場作業
- バックヤード業務
それぞれの特徴や、向いている方の傾向を詳しく見ていきましょう。

オフィスワーク
体力面の負担が比較的少なく、静かな環境で作業できる職種です。
主にパソコンを使った作業が多く、事務処理やデータ入力が得意な方に向いています。
最近では、パートタイム勤務や在宅ワークも可能な企業が増えており、自分に合った働き方を選びやすいのも魅力です。
一般事務
文書の作成やファイリング、備品管理、郵便物の仕分けなどを行う職種です。
基本的なパソコン操作とビジネスマナーが求められますが、業務の内容が比較的ルーティンで明確なため、障害の特性に応じた調整がしやすいのが特徴です。
障害者雇用枠での募集も多く、安定した人気職種のひとつです。
データ入力
顧客情報や伝票、売上データなどを専用のフォーマットに入力する業務です。
正確さや集中力が求められる反面、電話応対がない職場も多く、静かな環境で作業したい方や聴覚障害・発達障害をお持ちの方にも向いている仕事の種類です。
コールセンター業務
電話による予約受付やカスタマーサポートなどを行う仕事です。
マニュアルや研修制度が充実している職場が多く、段階的に仕事を覚えられる環境が整っています。
また、障害者雇用の実績がある企業では、配慮体制が整っている場合も多く、安心して働ける職場に出会える可能性も高まります。
技術職
専門的なスキルや知識を活かして働ける職種で、近年は在宅勤務に対応している企業も増えています。
自身の得意分野を活かし、自分のペースで働きたい方におすすめです。
システムエンジニア
プログラムの設計や開発、運用保守を行う職種です。
作業の多くはパソコン上で完結し、自分のペースで取り組める点が大きな魅力です。
また、成果物で評価されるため、コミュニケーションに不安がある方や、精神・内部障害をお持ちの方にも向いています。
在宅勤務やフレックスタイムを導入している企業も増えており、柔軟な働き方を実現しやすい職種です。
CADオペレーター
CAD(設計支援ソフト)を使って、設計図面を作成する仕事です。
集中力がある方や、細かい作業が得意な方にぴったりで、黙々と作業したい方にも適しています。
視覚・聴覚・発達障害をお持ちの方でも、専門スキルを活かして活躍できる場が広がっている職種です。
未経験でも、研修制度やeラーニングでスキルを習得できる企業もあります。
Webデザイナー
Webサイトやバナーなどのデザインを手がける仕事で、HTMLやCSSを使ったコーディング業務も含まれます。
成果物ベースで評価されるため、在宅勤務やフリーランスとしての働き方にも適しています。
自分の感性やアイデアを活かせるクリエイティブな職種であり、「好き」を仕事にできる点も魅力です。
現場作業
体を動かす仕事が中心となる職種で、一定の作業を繰り返すルーティンワークが多いのが特徴です。
作業内容はさまざまですが、体を動かす仕事が中心となるため、身体の状態に合わせて無理なく選ぶことが重要です。

製造・組立作業
部品の組み立てや検品、梱包といった作業を、工場内でマニュアル通りに進めていくお仕事です。
一つひとつの作業に集中し、決められた手順に沿って正確にこなせる方に向いています。
業務内容が明確で、黙々と作業したい方やコミュニケーションが苦手な方にも適した仕事の種類です。
清掃業務
オフィスビルや商業施設、公共施設などの清掃を担当します。
比較的静かな環境で作業ができ、業務時間も短めな場合が多いため、体力に不安がある方にもおすすめです。
勤務時間帯や作業範囲が明確で、ご自身の体調や生活リズムに合わせた働き方がしやすいのも魅力です。
商品管理
倉庫や店舗の裏方で、商品の在庫を管理したり、商品の受け入れ・仕分け・棚卸しなどを行う仕事です。
整理整頓が得意な方や、一定のルールに沿って正確に作業するのが好きな方に向いています。
人前に出る機会が少ないため、落ち着いた環境で働きたい方にも適した仕事の種類です。
梱包作業
商品を袋や箱に詰めて、出荷の準備を整える軽作業のお仕事です。
作業手順が明確で、集中して丁寧に作業することが得意な方にぴったりです。
一人でもくもくと行う作業が多く、コミュニケーションに不安がある方や、短時間勤務を希望する方にも適しています。
障害者の方が働きやすい環境と雇用形態
障害をお持ちの方が、無理なく、そして安心して働き続けるためには、職場環境や雇用形態の選び方が重要です。
同じ仕事内容でも、雇用形態や会社の体制によって、働きやすさは大きく変わってきます。
この章では、主な雇用スタイルや就労先の特徴を紹介しながら、ご自身に合った働き方を見つけるヒントをお伝えします。

一般雇用と障害者雇用枠の違い
企業が通常募集する「一般雇用」と、法律に基づき障害者を対象とした「障害者雇用枠」では、それぞれに異なる特徴とメリット・デメリットがあります。
一般雇用のメリットとデメリット
- メリット:
- 幅広い業種・職種に挑戦できる
- 障害の開示が不要な場合もある
- デメリット:
- 必要な配慮が受けにくい場合がある
- 選考や業務内容に不安を感じることも
障害者雇用枠の特徴と利点
- 特徴:
- 法律に基づき設けられた雇用枠
- 面接時に障害の内容や配慮事項を伝えやすい
- 利点:
- 通院配慮や勤務時間の調整など、必要な配慮を受けやすい
- 定着支援や相談体制が整っている企業も多い
- デメリット:
- 希望する職種や仕事内容の選択肢が限られる場合がある
- 賃金水準やキャリアアップの機会が少ないこともある
- 周囲との関係性において、“特別扱い”と見られてしまうケースもある
どちらの働き方が自分に合っているかを見極めるために、障害特性・希望条件・企業の理解度をしっかり確認しておきましょう。
在宅勤務の可能性
テレワークに適した仕事の種類
- データ入力
- プログラマー/エンジニア
- デザイナー
- カスタマーサポート(チャット応対など)
在宅勤務の環境整備
在宅で働くためには、自宅にパソコンやネット環境を整える必要があります。
企業によっては、在宅勤務に必要な機材を貸与してくれたり、定期的な面談やチャットでの相談窓口を設けている場合もあります。
自分の生活スタイルに合わせた柔軟な働き方を目指す方にとって、在宅勤務は非常に有効な選択肢となるでしょう。
特例子会社での就労
特例子会社とは、障害をお持ちの方が働きやすいように、配慮された職場環境を整えている企業のことです。
特例子会社の仕組み
親会社の一部門として設立され、厚生労働省の認定を受けて「障害者雇用率」の対象とされています。
主な業務内容と特徴
- 書類のスキャンやデータ入力
- 清掃、軽作業、商品の仕分け
- 社内便の配送や備品の管理 など
職場には、障害に理解のあるスタッフやサポート体制が整っており、安心して業務に取り組める環境が用意されています。
就労継続支援サービスの活用
「すぐに一般企業で働くのは不安…」という方には、段階的に働く力を身につけられる就労継続支援サービスの活用がおすすめです。
A型事業所(雇用型)
- 雇用契約あり(最低賃金が保障される)
- 一般企業への就職を目指しながら、働く習慣を身につけられる
- 職員のサポートのもと、実際の仕事を通じてスキルアップできる
B型事業所(非雇用型)
- 雇用契約なし(工賃支給)
- 体力や精神面に不安がある方も無理なく働ける
- 軽作業や創作活動などを通じて、就労への第一歩を踏み出せる
自分にとって負担の少ない環境で、段階的に働く力を育てたい方にとって、就労継続支援は大きな助けとなる選択肢です。
障害者の就職・転職支援
障害をお持ちの方が自分に合った仕事を見つけるためには、信頼できる支援機関やサービスの活用が欠かせません。
一人で悩まず、サポートを受けながら進めることで、不安や疑問を解消しながら、より自分らしい働き方へとつなげることができます。
ここでは、就職・転職活動に役立つ代表的な手段を4つ紹介します。
ハローワークの活用法

ハローワーク(公共職業安定所)には、障害をお持ちの方を専門に支援する窓口が設置されています。
障害者手帳を持っていれば、誰でも無料で利用可能です。
専門窓口の利用方法
- 受付で「障害者専門窓口を利用したい」と伝える
- 専門の職員が対応し、希望条件や配慮事項をヒアリング
- 障害特性に合った求人を紹介してもらえる
職業紹介サービスの流れ
- 相談・ヒアリング
- 求人情報の提供
- 応募書類作成や面接練習の支援
- 面接日程の調整や企業との連携
- 就職後の定着支援(継続相談や訪問など)
就職活動の入口として、最も身近で頼れる公的サービスです。
障害者向け求人媒体の特徴
民間の求人サービスでも、障害者雇用に特化した媒体やサイトが増えています。
オンライン求人サイトの活用
- スグJOBなど、障害者雇用専門の求人サイトでは、職種や配慮内容で検索が可能
- 応募から面接調整まで、オンライン上で完結できるサービスも多数
- 求人票に「配慮事項」や「就労環境」が明記されているものも多く、自分に合った企業を見つけやすい
障害者専門の求人情報誌
インターネットの利用が難しい方や、地域密着の情報を求める方には、フリーペーパーや情報誌形式の障害者雇用専門の求人媒体もあります。
地元企業の採用情報や、地元の支援機関と連携した求人なども多く掲載されており、より現実的な就職活動が行えます。
ハローワークや福祉事業所に設置されていることが多く、紙面でじっくり選べるというメリットもあります。
専門エージェントによるサポート
就職支援のプロである「人材紹介エージェント」も心強い味方です。
特に障害者雇用に特化したエージェントであれば、企業側との調整や就職後のフォローまで、きめ細かく対応してくれます。
障害者雇用に特化したエージェント
障害者雇用専門の人材紹介会社では、求職者一人ひとりに担当者が付き、希望や特性から適切な仕事の種類を提案してくれます。
企業との間に立って配慮事項を伝えてくれるため、安心して選考に進むことができます。
また、応募から面接対策、条件交渉、入社後の支援まで、就職・転職活動全体をサポートしてくれるので、不慣れな方でも安心して就職活動に臨めます。
キャリアカウンセリングの重要性
自己分析や希望条件の整理に不安がある方は、キャリアカウンセリングを利用するのがおすすめです。
障害の内容や過去の経験、適性などを客観的に整理することで、自分に合った仕事の種類や働き方が見えてきます。
エージェントやハローワークでは無料で相談できることが多く、初めての就活・転職活動を進めるのに役立ちます。
職業訓練と就労移行支援
「まだ働く自信がない」「スキルに不安がある」という方には、働く準備を整える支援制度を活用するのがおすすめです。
公共職業訓練の種類と内容
公共職業訓練では、事務・IT・製造・販売など、実践的なスキルを習得するための講座が幅広く用意されています。
障害をお持ちの方を対象としたコースでは、障害特性に応じた指導体制や補助制度が整っており、職業準備の段階からサポートが受けられます。
訓練期間中は、一定の条件を満たせば「職業訓練受講給付金」を受け取ることも可能です。

就労移行支援事業所の役割
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害者のための福祉サービスです。
事業所では、最大2年間、生活リズムの安定から職場体験、面接練習、応募書類作成までトータルに支援を行います。
就労経験がない方や、就職に不安がある方でも、自分のペースで仕事に慣れていくことができます。
また、就職後の継続支援を受けたい方にも適しています。
障害者の方が仕事を探す際のポイント
仕事探しは、人生の大きな転機です。
特に障害をお持ちの方にとっては、「どんな職場が自分に合うのか」「必要な配慮をしてもらえるのか」など、不安や迷いがあるかもしれません。
いくつかのポイントを意識することで、自分にとって無理のない、安心して働ける仕事を探していきましょう。
ここでは、仕事探しをするうえでの大切な視点を、4つの観点からご紹介します。
自己分析と適性の把握
まずは、自分自身をしっかりと理解することが大切です。
自身の強みと弱みの理解
- 得意な作業、苦手な業務を整理する
- どんな環境で力を発揮しやすいかを考える
- 体力や集中力の持続時間、得意な作業内容、コミュニケーションの得手不得手
たとえば、黙々と作業に取り組める方はデータ入力や軽作業が、対人対応が得意な方は接客業やコールセンター業務などが向いていることがあります。
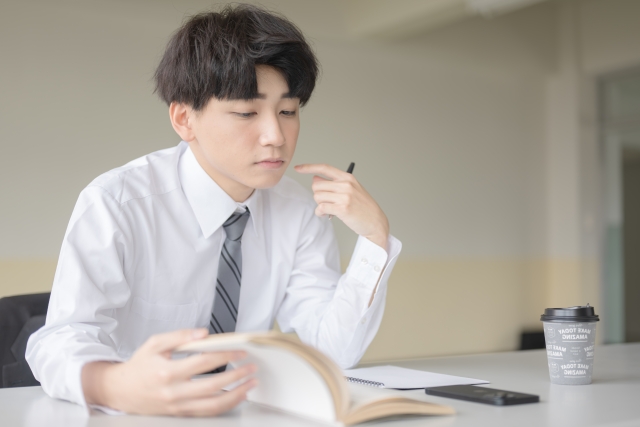
興味・関心のある分野を探る
得意なことだけでなく、「やってみたい」「興味がある」と感じる分野を探しましょう。
- 好きなこと・続けられることから考えてみる
- 興味がある職種に関する情報を集めてみる
自己分析ツールやキャリアカウンセラーとの面談を通じて、自分では気づかなかった仕事の種類や可能性を発見できることもあります。
職場環境への配慮の確認
どれだけ仕事内容が合っていても、職場の環境が合わなければ長く働き続けるのは難しいものです。
以下に、職場環境の確認すべきポイントを挙げます。
バリアフリー設備の有無
障害の種類によって、必要となる設備や配慮は異なります。
たとえば、車椅子の方にとってはスロープやエレベーター、トイレの広さなどが重要です。
視覚障害をお持ちの方であれば、誘導ブロックや案内表示の工夫が役立つ方もいらっしゃるでしょう。
求人票に記載されていない場合でも、面接時や事前見学の際に確認しておきましょう。
柔軟な勤務時間設定の可能性
通院や体調の波がある方にとっては、短時間勤務や週3日勤務など、働き方の柔軟性があるかどうかも重要な判断基準です。
障害者雇用枠の求人では、あらかじめ勤務日数や時間帯の調整が可能なケースも多いです。
自分の生活スタイルに合った働き方を選びやすくなっています。
コミュニケーション方法の工夫
職場での人間関係も、働きやすさに大きく影響します。
そのため、自分に合った伝え方・相談の仕方を考えておくことが大切です。
障害特性に応じた伝達手段
聴覚や発達などの障害がある方にとっては、コミュニケーション方法そのものが仕事選びのカギとなります。
メールやチャットでのやりとり、筆談、マニュアル対応中心の職種など、自分にとってストレスの少ない伝達手段が確保されているかを確認しましょう。
自己申告によって企業側が配慮してくれることも多く、安心して働ける環境づくりにつながります。
職場での理解促進の取り組み
障害者雇用に積極的な企業では、社内研修やマニュアルを通じて、障害への理解を深める取り組みを行っていることがあります。
こうした企業文化がある職場では、長く安定して働きやすい環境が整っています。
キャリアプランの設計
「とりあえず就職する」ではなく、将来の姿も描いたうえで仕事を選ぶことが、長く働くためのカギになります。
短期・中期・長期目標の設定
「まずは週3日から働く」「1年後には正社員を目指す」「3年後には新しい職種にチャレンジする」など、時間軸に応じたキャリア目標を設定することで、長期的な安定につながります。
小さな成功体験を重ねていくことで、自信がつき、より多くの仕事の種類にチャレンジできるようになります。
スキルアップの機会確保
仕事に慣れてきたら、業務に関連する資格取得やスキル向上を目指すのもおすすめです。
通信講座や企業の研修制度を活用することで、将来的にキャリアアップの可能性を広げることができます。
障害者の方向けの職業訓練やセミナーも各地で開催されています。
積極的に参加することで、自分の可能性を広げることができます。
まとめ:自分らしく活躍できる仕事を見つけるために
障害があるからといって、「自分にはできる仕事が限られている」と感じる必要はありません。
今は、障害の種類やライフスタイルに合わせて選べる仕事の種類や雇用形態が、以前よりもずっと多くなっています。
自分に合った仕事を見つけるためには、まず「どんな仕事をしたいか」を考えるだけでなく、「どんな職場で、どんなふうに働きたいか」を具体的に描くことが大切です。
そのためには、自分の得意なことや苦手なこと、働くうえで必要な配慮について、きちんと理解しておくことが大きな力になります。
また、企業の障害者雇用制度や就労支援サービスなど、社会全体で整いつつあるサポートを活用することで、より安心して働ける環境を見つけることができます。
特に、以下のような制度や選択肢は、障害をお持ちの方にとって大きな支えになります。
- 障害者雇用枠
- 特例子会社での勤務
- 在宅勤務(テレワーク)
- 就労継続支援(A型・B型)
「仕事」は、単に収入を得るための手段だけではありません。
人とつながることや、自分の役割を実感することによって、心の豊かさや自信にもつながっていきます。
たとえ障害があっても、自分らしく働ける場所はきっと見つかります。
最初の一歩を踏み出すことに不安を感じる方もいるかもしれません。
でも、その一歩が未来を変えるきっかけになります。
「どんな仕事があるのか知りたい」「自分に合った働き方を探したい」と感じたら、ぜひ一度、障害者向け求人サイト「スグJOB」をご覧ください。
スグJOBでは、障害に理解のある企業の求人を多数掲載しています。
経験やスキルに不安がある方にも、専門スタッフが丁寧にサポートしますので、安心してご利用いただけます。
あなたが「自分らしく働ける仕事」と出会えることを、心から願っています。

スグJOBは求人数トップクラス!
障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ
障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ
この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。










