
特例子会社とは?職種や給料、メリットなど詳しく解説!
障害のある方が「自分に合った働き方を見つけたい」と考えたとき、選択肢のひとつとなるのが特例子会社です。
特例子会社は、障害のある方が安心して働けるように、職場環境や支援体制を工夫して設立された会社です。
多くの企業が積極的に取り組んでおり、実際に多様な職種で活躍している方が増えています。
一方で「一般企業での雇用と何が違うの?」「給料はどのくらい?」「メリットや注意点は?」と疑問を持たれる方も少なくありません。
この記事では、特例子会社の仕組み・職種・給与の実態・働くメリットと考慮点をわかりやすく解説しています。
さらに、実際に働いている方の体験談や、就職に役立つ支援制度・求人情報の探し方についてもまとめています。
読み進めていただくことで、特例子会社という仕組みの全体像を知り、ご自分に合った働き方のヒントを得られれば幸いです。
特例子会社とは?
特例子会社の概要
特例子会社とは、親会社が障害者雇用を目的に設立し、一定の基準を満たしたうえで厚生労働大臣の認可を受けた子会社のことです。
主として大企業による設立が多い一方で、条件を満たせば中堅企業でも設立が可能となっています。
一般の会社と同様に事業活動を行いながら、障害特性に応じた配慮と支援を組織的に実装している点が大きな特徴です。
たとえば、バリアフリー設計、作業工程の見える化、視覚・聴覚支援デバイスの導入、ジョブコーチ等の専門人材常駐などの取り組みが行われています。

親会社は、特例子会社で雇用している障害者を、自社の雇用率に算入できます(資本関係や人的関係など一定の要件を満たす必要があります)。
そのため、親会社はグループ全体での雇用創出と法令遵守を両立しやすくなります。
こうした仕組みにより、働く側には安心感、企業側には継続的な雇用体制の構築というメリットが生まれます。
法定雇用率との関係
法定雇用率は、一定規模以上の民間企業に対して障害者の雇用割合を求める基準です。
民間企業の法定雇用率は、2024年4月に2.5%へ引き上げ、2026年7月に2.7%へ引き上げ予定です。
なお、国・地方公共団体・独立行政法人等には別の基準が適用されます。
特例子会社制度は、「雇用率を満たすための形式」ではなく、実際に活躍できる場を提供するための仕組みとして運用されることが重視されています。
参考として、時期と率を整理します。
| 対象 | 施行・予定時期 | 雇用率 |
| 民間企業 | 2024年4月 | 2.5% |
| 民間企業 | 2026年7月予定 | 2.7% |
一般企業の障害者雇用との違い
雇用規模では、同一拠点・同一工程内に複数名を配置しやすく、受け入れ体制を標準化しやすい特徴があります。
支援体制では、ジョブコーチや人事・産業保健スタッフが常駐して日常的にサポートを行えるため、体調・業務双方の課題に早期対応しやすい仕組みがあります。
仕事内容では、障害特性に合わせて工程設計や役割分担を見直し、作業の見える化・マニュアル化・ツール化を進めている職場が多い傾向です。
その結果、「安心して働ける」「配慮のある環境で強みを活かせる」というニーズに近い選択肢になりやすい点が、一般企業の個別雇用との大きな違いです。
特例子会社の現状と実態
全国の特例子会社数と傾向
特例子会社は年々増加傾向にあり、設立主体は製造・金融・ITなどの大規模法人が中心です。
特例子会社制度が導入された1980年代以降、障害者雇用の重要性が広く認識されるようになり、多くの企業が特例子会社を設立しています。
最新のデータによると、特例子会社の数は全国で数百社に上り、毎年新たな特例子会社が設立されています。
特に大企業を中心に、障害者雇用を積極的に推進する動きが見られ、これが特例子会社の増加に寄与しています。
増加の背景には、法定雇用率の段階的引き上げがあります。
一方で、地方部では設立数や業種の選択肢が都市部より限られる傾向があります。
ですが今後は、サテライトオフィスや在宅勤務の活用により、地域間格差の緩和が進む可能性があります。

業種と職種の多様性
特例子会社の職種は、事務系(データ入力、スキャン、発送・郵便仕分け)、製造・物流系(検品、組立、梱包、ピッキング)が多く見られます。
近年は、IT補助(Web更新、アノテーション、RPA運用補助、ヘルプデスク補助)など、デジタル系の職務も広がっています。
在宅・ハイブリッド勤務を前提にしたチーム運営も増え、内部障害や通勤配慮が必要な方の選択肢も拡大しています。
雇用形態と給与の実態
雇用形態は、短時間勤務・フレックス・時差出勤など柔軟な制度が比較的整っています。
契約社員・パートからのスタートが一定数ある一方、正社員登用制度を設ける企業も増えています。
平均年収の傾向
特例子会社で働く障害者の平均年収は、一般企業に比べてやや低い傾向にあります。
これは、特例子会社が非営利の目的で設立されるケースが多く、企業の利益よりも障害者の雇用安定を重視しているためです。
平均年収は概ね200万円〜300万円程度とされますが、雇用形態・地域・職種によって幅があります。
生活設計や将来の収入見通しは、昇給・賞与・手当の有無を含めて必ず確認しましょう。
給与水準の特徴
特例子会社における給与水準は、職種や業種、勤務地によって異なります。
軽作業中心の現場では地域の最低賃金に近い水準になりやすい一方、IT・事務のスキル職では比較的高い水準が期待できる場合もあります。
企業にもよりますが、従業員のスキルアップやキャリアアップを支援する制度が整っていることもあり、入社後には一般企業と同様に給与が上昇するケースもあります。
また、親会社と同等の福利厚生(社会保険・有休・健康施策等)を享受できる企業も多くあります。
就職先の候補として見る場合は、可処分所得と生活安定の観点から総合評価するようにしましょう。
特例子会社で働くメリット
充実した支援体制
特例子会社では、障害を持つ方が安心して働けるように、一般企業よりも充実した支援体制が整えられていることが多いです。
例としてジョブコーチや産業保健スタッフ、カウンセラー等の専門職が関与し、日常の課題を早期に見える化・解決できる体制などがあります。
定期面談や面談記録の共有、困りごとの相談窓口の明確化により、長期就労できる安心感があります。

柔軟な勤務制度
柔軟な勤務制度を選択できる会社では、個々のニーズに応じた働き方が可能です。
会社によっては週20時間から段階的に増やす働き方や、通院日考慮・時差出勤・在宅勤務など、体調・生活との両立を支える制度が整っています。
無理のない就労継続を第一に、合意形成のうえで就労時間や業務範囲を調整しやすいのが特徴です。
障害に配慮された職場環境
特例子会社では、障害者が働きやすい職場環境に配慮されています。
たとえばバリアフリー動線、拡大読書器・音声ソフト、コミュニケーション支援ツール、休憩スペースの整備など、環境面の配慮が制度として根づいています。
安全配慮・合理的配慮が受けやすいことから、一般企業よりも受け入れられる障害の種類も多くなる傾向があり、間口の広さと働きやすさを実現しやすい点が魅力です。
キャリアアップの機会
近年は特例子会社でも、軽作業に限らず、事務・IT・品質管理・人事総務補助など専門性のある職務が増えています。
職務等級制度・登用制度・社内研修・親会社連携研修の活用で、スキルに応じた役割拡大や正社員登用が見込めます。
特例子会社で働く際の考慮点
求人数と選択肢の制限
地域・業種の偏在により、希望条件に合致する求人になかなか出会えないことがあります。
就職活動の際には勤務地・働き方・職務内容など希望条件の優先順位を決め、情報収集を行いましょう。
また、情報収集する際はハローワーク・紹介会社など複数の情報源から探すことも重要です。
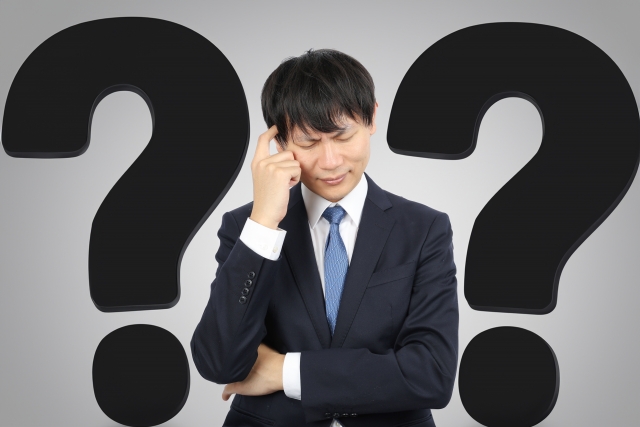
給与水準の検討
特例子会社は一般企業と比べて給与水準が低い傾向があるため、長期的な収入面での計画を立てることが重要です。
応募したい企業があれば、求人票に書かれた年収と生活費の見積りを見比べて、生活が可能かどうか検討します。
長く働くのであれば、昇給・賞与・手当の有無や評価制度も必ず確認しましょう。
金銭だけでなく、福利厚生・通院配慮・在宅費用補助など、金銭以外の支援も確認し、総合的な評価で判断するようにしましょう。
業務内容の限定性
特定の業務に特化している特例子会社では、職種の選択肢が限られることがあります。
また、標準化された反復作業が中心の配置では、将来的に自身のスキルが偏る可能性があります。
スキルアップやキャリアアップを期待する場合は、異動・兼務・学習機会の有無を事前に確認し、将来像に合う職務設計かどうかを見極めましょう。
特例子会社での具体的な配慮例
A社の事例
検品・梱包工程の見える化を徹底し、視覚支援デバイス(拡大読書器・音声読み上げ)を標準装備としました。
写真・イラスト付きマニュアルで作業基準を統一し、ジョブコーチが常駐することで日々の振り返りと課題解決を短サイクルで回しています。
その結果、品質ばらつきの低減と定着率の向上を同時に実現しています。

B社の事例
データ入力・システム運用補助を中心に、在宅・ハイブリッド勤務を制度化しています。
セキュアPC・専用回線の貸与、オンライン手順書の整備、字幕・チャットツールを活用し、コミュニケーション支援を強化しています。
さらに定期オンライン面談で健康・業務の両面を確認し、多様な特性に応じた働き方を実現しています。
特例子会社への就職プロセス
活用できる就労支援サービス
複数の支援機関を並行活用し、求人探索・応募準備・職場定着までを一気通貫で行うするのが成功の近道です。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、一般就労に向けて必要なスキルや知識を身につけるための訓練やサポートを提供する施設です。
ここでは、職業訓練、実習、就職活動支援などが行われ、個々の能力や適性に応じた支援が受けられます。
ビジネスマナー・PCスキル・模擬就労などを通じて職場適応力を育成します。
また、事業所との連携により、企業実習・職場体験を経て、特例子会社への就職もスムーズに進むケースがあります。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、障害者の職業能力開発や就職支援を行う公的機関です。
ここでは、職業相談、職業適性検査、職業訓練、そして就労後のフォローアップまで一貫した支援が提供されます。
ハローワーク・企業との連携で受入環境づくりを後押しします。
ハローワークの役割
ハローワークは、障害者の就職支援において重要な役割を果たしています。
ハローワークでは、障害者雇用専門の相談員が配置されており、求人情報の提供、応募書類の作成支援、面接対策など、就職活動全般にわたるサポートが受けられます。
職場見学や実習を通じて、ミスマッチの予防につなげます。
障害者雇用求人サイト
障害者雇用に特化した求人サイトは、特例子会社の求人情報を効率的に検索できる便利なツールです。
これらのサイトでは、職種や勤務地、在宅勤務、配慮事項などの検索条件を細かく設定でき、自分に合った求人情報を見つけやすくなっています。
さらにサイトによっては、履歴書の作成支援や応募サポートなどのサービスも提供されています。
複数サイトの同時活用で機会損失を防ぎましょう。
採用時に重視されるポイント
特例子会社の採用では、障害者の特性や適性を考慮した上で、いくつかのポイントが重視されます。
通常の採用と同じくスキルや人物のほか、障害特性と職務要件が合っているかが重視されます。
そのため必要な配慮事項・通院や服薬の工夫・体調把握の方法を具体例で伝えられると評価が安定します。
他にも強み(得意工程・集中できる条件・対人連携の得意不得意)を職務に結びつけて説明する準備をしておきましょう。
特例子会社で働く人の体験談
製品発送業務担当Tさんの経験
車椅子利用者のTさんは、バリアフリー動線と高さ調整可能な作業台の導入で、姿勢に無理のない作業を実現できました。
同僚との相互支援と勤務時間配慮により、通勤負担の軽減と安定就労が続いています。
「困ったら相談できる人がいることが、仕事の継続に直結している」と実感しているそうです。
事務作業担当Kさんの日常
発達障害を持つKさんは、工程の明確化・手順書・進捗の見える化が合い、マルチタスクによる混乱が減少しました。
週1回の面談で体調と業務を振り返り、自分のペースを保ちながら達成感を積み上げています。
「曖昧さを減らす工夫が、安心と成果の両立につながった」と語っています。
まとめ
特例子会社は、配慮と支援を制度として組み込んだ就労の受け皿であり、安定就労とスキル活用の両立が期待できます。
その一方で、地域・業種の偏在や給与レンジの課題があるため、福利厚生・登用制度・学習機会まで含めた総合的な職場選びが必要になります。
支援機関・ハローワーク・求人サイトを併用し、可能であれば見学・実習・トライアルを通じて、自分に必要な要件は事前によく確認しておきましょう。
「働きやすさ」と「キャリア形成」の両面を見据えた職場選びが、長く自分らしく働く近道になります。
スグJOBには特例子会社の求人が多数ございます
特例子会社の求人は、在宅可・短時間・フレックス・配慮事項の明記など、条件の幅が広がっています。
ご自身の特性・ライフスタイル・優先順位を整理し、複数求人の比較検討で最適解を探しましょう。
応募前の情報収集(職場見学・実習・Q&Aの事前確認)を行うと、入社後のミスマッチ防止に役立ちます。
支援機関の担当者やキャリアアドバイザーと連携し、書類作成・面接対策・配慮事項のリストアップまで伴走支援を活用するのがおすすめです。
不安があれば一人で抱え込まず、まずは相談することが「最初の一歩」です。
特例子会社への就職を検討する際は、ぜひ一度スグJOBへご相談ください。

スグJOBは求人数トップクラス!
障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ
障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ
この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。










