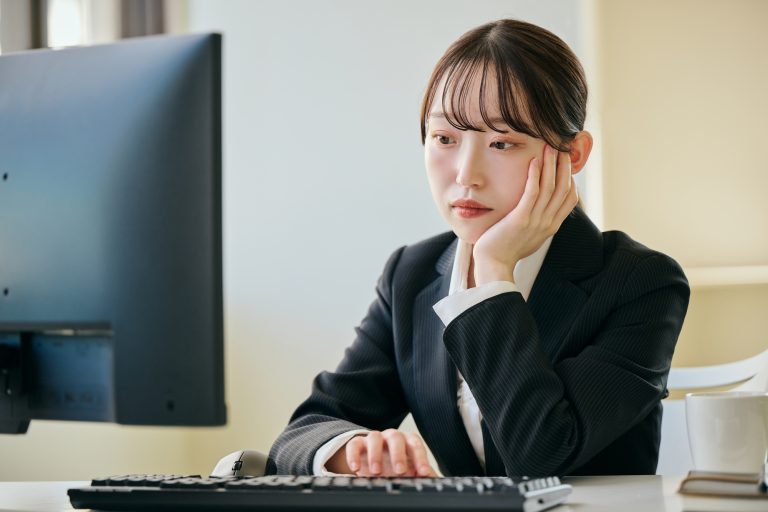低音障害型感音難聴とは?仕事への影響と対処法を解説

低音障害型感音難聴とは?仕事への影響と対処法を解説
耳の聞こえが急に悪くなったり、耳に違和感を感じたりしたことはありませんか?
そんな症状の一つに、低音障害型感音難聴があります。
低音障害型感音難聴は、低い音が聞き取りにくくなる難聴の一種で、ある日突然発症することが特徴です。
軽度の難聴ではありますが、放っておくと症状が悪化したり、再発を繰り返したりする恐れがあります。
特に、仕事をしながら治療を続けるのは容易ではありません。
職場の理解や協力を得ることはもちろん、休職や退職も視野に入れなければならない場合もあるでしょう。
しかし、低音障害型感音難聴と上手に付き合いながら、自分らしく働き続けることは可能です。
大切なのは、早期発見と適切な治療、そして仕事との両立の仕方を知ることです。
本記事では、低音障害型感音難聴の特徴や症状、原因と治療法について詳しく解説します。
さらに、低音障害型感音難聴を発症した際の仕事への影響と、どのように対処すべきかについてもお伝えします。
加えて、聴覚障害のある方の職探しに利用できるサービスもご紹介します。
低音障害型感音難聴について正しく理解し、仕事との向き合い方を知ることで、病気とうまく付き合いながら充実した働き方ができるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
低音障害型感音難聴とは
耳が聞こえにくくなる難聴の1種
低音障害型感音難聴とは、難聴の一種で、主に低い音が聞き取りづらくなる症状が特徴です。
難聴には、外耳や中耳に原因がある伝音性難聴と、内耳から聴神経、脳に至るまでの障害で起こる感音性難聴の2種類があります。
低音障害型感音難聴は、感音性難聴に分類されます。
一般的に、人間の可聴周波数は20Hz~20,000Hzと言われています。
その中でも、500Hz以下の低い周波数の音が聞こえにくくなるのが、低音障害型感音難聴の特徴です。
会話の聞き取りには、1,000~4,000Hzの音が重要とされているため、低音障害型感音難聴は比較的軽度な難聴に分類されます。
しかし、症状が徐々に進行し、中音域や高音域にも影響が及ぶケースもあるため、注意が必要です。

突発性難聴やメニエール病との違い
低音障害型感音難聴と症状が似ている病気として、突発性難聴やメニエール病があります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
突発性難聴の特徴
突発性難聴は、感音性難聴の一種で、原因不明の難聴です。
低音障害型感音難聴と同様に突然発症しますが、以下のような特徴があります。
【突発性難聴の特徴】
- 高音部の聴力低下が主症状
- 片耳での発症が多い
- めまいを伴うことがある
- 耳鳴りを伴うことが多い
突発性難聴は、早期の治療開始が非常に重要で、発症から2週間以内の治療開始が望ましいとされています。
治療が遅れると、聴力の回復が困難になることがあります。
メニエール病の特徴
メニエール病は、内耳の障害によって起こる病気で、以下のような特徴があります。
【メニエール病の特徴】
- 回転性のめまい発作を繰り返す
- 耳鳴り、耳閉感、難聴を伴う
- 片耳での発症が多い
- 低音部から高音部まで、幅広い周波数の聴力低下を示す
メニエール病は完治が難しく、症状のコントロールを目的とした治療が中心となります。
発作時は安静にして、ストレスを避けることが大切です。
低音障害型感音難聴の特徴と症状
低音障害型感音難聴の代表的な症状は、以下の通りです。
【低音障害型感音難聴の症状】
- 低い音が聞こえにくい
- 耳がふさがった感じがする
- 自分の声が響く(自声強調)
- 耳鳴りがする(低い音の耳鳴り)
特に、以下のようなケースに該当する方は、低音障害型感音難聴の可能性があります。
- 朝起きたら、急に耳の症状が出ている
- 風邪を引いた後や、ストレスが溜まっている時に症状が出る
- 症状が断続的に現れる
低音障害型感音難聴は、初期症状が軽度であるため、気づきにくいことがあります。
しかし、放置すると症状が徐々に進行し、聴力低下が進む可能性があります。
違和感を感じたら、早めに耳鼻咽喉科を受診することが大切です。
また、低音障害型感音難聴は再発することが多いのも特徴です。
治療後も定期的な聴力検査を受け、症状の再発がないかを確認しましょう。
再発を予防するためには、ストレス管理や生活習慣の改善も重要です。

低音障害型感音難聴の原因と治療法
低音障害型感音難聴は、適切な治療を行えば回復する可能性が高い病気です。
しかし、原因を理解し、再発を防ぐための対策を講じることも重要です。
ここでは、低音障害型感音難聴の主な原因と治療法について詳しく説明します。
主な原因
低音障害型感音難聴の主な原因は、内耳の異常です。
内耳には、蝸牛(かぎゅう)と呼ばれる器官があり、音を電気信号に変換して脳に伝える働きを担っています。
この蝸牛の内部には、外リンパ液と内リンパ液が存在し、バランスを保っています。
低音障害型感音難聴は、内リンパ液が過剰に蓄積することで発症すると考えられています。
内リンパ液が増えすぎると、蝸牛内の圧力が高まり、低音を感知する部分の機能が低下します。
その結果、低音が聞き取りづらくなるのです。
内リンパ液の増加には、以下のような要因が関与していると考えられています。
【内リンパ液増加の要因】
- ストレス
- 疲労
- 睡眠不足
- ホルモンバランスの変化(月経前や更年期など)
これらの要因は、自律神経のバランスを乱し、内耳の機能に影響を与えます。
低音障害型感音難聴を予防するためには、日頃からストレス管理を心がけ、規則正しい生活習慣を維持することが大切です。
薬物療法が中心
低音障害型感音難聴の治療は、主に薬物療法が中心となります。
目的は、内リンパ液の量を調整し、内耳の機能を回復させることです。
代表的な治療薬は、以下の通りです。
【低音障害型感音難聴の治療薬】
- 利尿剤:内リンパ液の排出を促進する
- ステロイド剤:内耳の炎症を抑える
- 血流改善薬:内耳の血流を改善する
- ビタミン剤:内耳の代謝を促進する
これらの薬を組み合わせて使用することで、多くの場合、数週間から数ヶ月で症状が改善します。
ただし、症状や患者さんの状態に応じて、薬の種類や投与期間は異なります。
治療と並行して、生活習慣の見直しも必要です。
医師の指導に従い、ストレス管理、十分な睡眠、バランスの取れた食事を心がけましょう。
また、喫煙や飲酒は、内耳の血流を悪化させる可能性があるため、控えめにすることをおすすめします。
再発する可能性がある
低音障害型感音難聴は、適切な治療により症状が改善しても、再発する可能性があります。
再発を防ぐためには、治療後も定期的な経過観察が必要です。
再発のサインとして、以下のような症状が現れることがあります。
【低音障害型感音難聴の再発サイン】
- 耳がふさがった感じがする
- 自分の声が響く
- 低音が聞き取りづらい
これらの症状を感じたら、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。 早期の治療再開が、聴力の悪化を防ぐために重要です。
再発を予防するためには、ストレスマネジメントが欠かせません。
自分なりのストレス解消法を見つけ、積極的に取り入れましょう。
また、十分な睡眠と、バランスの取れた食事を心がけることも大切です。
低音障害型感音難聴は、完治が難しい病気ですが、適切な治療と生活習慣の改善により、症状をコントロールすることは可能です。
再発のサインを見逃さず、定期的な通院を続けることが、長期的な聴力の維持につながります。

低音障害型感音難聴を発症したら仕事はどうする?
低音障害型感音難聴を発症すると、仕事への影響は避けられません。
聴力の低下により、コミュニケーションが取りづらくなったり、集中力が低下したりする可能性があります。
しかし、適切な対処法を知ることで、仕事と治療を両立させることは可能です。
ここでは、低音障害型感音難聴を発症した際の仕事への対応について、詳しく説明します。
仕事を続けるため、キャリアの棚卸しと体調管理を整理し職場と相談する
低音障害型感音難聴を発症しても、すぐに仕事を辞める必要はありません。
まずは、自分のキャリアを見つめ直し、今後のキャリアプランを整理しましょう。
そして、治療と仕事を両立させるために、体調管理の方法を確立することが重要です。
職場には、低音障害型感音難聴を発症したことを正直に伝え、必要な配慮を求めましょう。
例えば、以下のような対応を依頼することができます。
【職場に依頼する対応例】
- 静かな環境での勤務
- 筆談やメールでのコミュニケーション
- 会議での資料の事前共有
- 休憩時間の確保
上司や同僚の理解と協力を得ることで、仕事を続けながら治療に専念することが可能になります。
また、産業医や人事部門に相談し、適切なアドバイスを受けることも大切です。

治療に専念するための休職も検討する
低音障害型感音難聴の症状が重い場合や、仕事との両立が難しい場合は、休職を検討する必要があります。
休職期間を利用して、集中的に治療に取り組むことで、早期の回復が期待できます。
休職を検討する際は、以下の点に注意しましょう。
【休職を検討する際の注意点】
- 会社の休職制度を確認する
- 主治医の意見書を用意する
- 休職期間中の収入を確認する(傷病手当金の受給など)
- 復職のタイミングを見極める
休職は、病気の回復に専念するための重要な選択肢です。
会社との十分な話し合いを経て、前向きに検討しましょう。
休職を経て復職するタイミング
休職期間中は、主治医と相談しながら、適切な治療を継続することが大切です。
同時に、復職に向けた準備も進めましょう。
復職のタイミングは、以下の点を考慮して決定します。
【復職のタイミングを決定する際の考慮点】
- 症状が安定していること
- 主治医が復職可能と判断していること
- 会社の復職制度の条件を満たしていること
- 自分自身が復職に向けた準備ができていること
復職後は、無理のない範囲で業務を遂行し、徐々に通常の働き方に戻していくことが重要です。
また、定期的な通院を継続し、症状の再発がないか注意深く観察しましょう。
退職も選択肢のひとつ
低音障害型感音難聴の症状が改善せず、仕事の継続が難しいと判断した場合、退職もひとつの選択肢です。
しかし、退職は慎重に検討する必要があります。
退職を検討する際は、以下の点を考慮しましょう。
【退職を検討する際の考慮点】
- 経済的な影響(収入の減少など)
- 再就職の可能性
- 障害者雇用への移行
- 家族への影響
退職は、人生の大きな転機となります。
十分な時間をかけて検討し、家族や支援者と相談しながら、決断することが大切です。
仕事の継続も検討した上で、体調や症状に配慮しながら働くための就職先探し
低音障害型感音難聴と診断されても、適切な治療と配慮があれば、仕事を続けることは可能です。
しかし、現在の職場での継続が難しい場合は、新たな就職先を探すことも検討しましょう。
体調や症状に配慮しながら働くための就職先を探す際は、以下の点に注目します。
【就職先を探す際の注目点】
- 障害者雇用に理解のある企業
- 静かな環境で働ける職場
- 在宅勤務やフレックスタイム制度がある企業
- 通院のための休暇制度が整っている企業
ハローワークや障害者職業センターを活用することで、条件に合った就職先を見つけることができます。
また、障害者雇用を専門とする人材紹介会社に相談するのも有効です。
低音障害型感音難聴は、適切な治療と環境調整により、仕事との両立が可能な病気です。
自分に合った働き方を見つけるために、様々な選択肢を検討し、前向きに行動することが大切です。

聴覚障害のある方の職探しに利用したいサービス
聴覚障害のある方が、仕事を探す際に利用できるサービスは様々あります。
ここでは、代表的な3つのサービスを紹介します。
ハローワーク、就労移行支援事業所、そして障害者雇用に特化した転職支援サービスです。
それぞれのサービスの特徴を理解して、自分に合ったサービスを選びましょう。
ハローワーク
ハローワークは、国が運営する公的な職業紹介機関です。 全国に設置されており、誰でも無料で利用することができます。
ハローワークでは、聴覚障害のある方のために、手話通訳や筆談でのコミュニケーションに対応しています。
また、就職支援ナビゲーターと呼ばれる専門の相談員が、個別の相談に乗ってくれます。
ハローワークの主なサービスは以下の通りです。
【ハローワークの主なサービス】
- 求人情報の提供
- 職業相談・紹介
- 就職支援セミナーの開催
- 職業訓練の案内
- 障害者トライアル雇用の斡旋
ハローワークは、全国にネットワークを持つ公的機関であるため、幅広い求人情報を保有しています。
聴覚障害のある方にとって、身近で頼りになる存在と言えるでしょう。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、障害のある方の一般就労を支援する福祉サービスです。
事業所内で、就労に必要なスキルを身につけるための訓練を受けることができます。
就労移行支援事業所では、以下のようなサービスが提供されています。
【就労移行支援事業所の主なサービス】
- 就労に必要なスキルの訓練
- 職場実習の斡旋
- 履歴書の作成指導
- 面接対策
- ジョブコーチによる職場定着支援
聴覚障害のある方の中には、コミュニケーションに不安を感じる方もいるでしょう。
就労移行支援事業所では、コミュニケーション面でのサポートも受けられます。
また、就職後の定着支援も行っているため、安心して就職活動に取り組むことができます。
障害者雇用に特化した転職支援サービス
近年、障害者雇用に特化した転職支援サービスが増えています。
これらのサービスでは、障害者雇用に理解のある企業の求人情報を集めています。
また、障害特性に詳しいキャリアコンサルタントが、個別の相談に乗ってくれます。
障害者雇用に特化した転職支援サービスの主な特徴は以下の通りです。
【障害者雇用に特化した転職支援サービスの主な特徴】
- 障害者雇用に理解のある企業の求人情報を保有
- 障害特性に詳しいキャリアコンサルタントが在籍
- 個別のニーズに合わせた支援
- 就職後の定着支援
聴覚障害のある方にとって、障害者雇用に特化した転職支援サービスは心強い味方となるでしょう。
自分のペースで、安心して就職活動に取り組むことができます。
スグJOBは業界最大の求人数であなたにピッタリのお仕事を見つけます!
中でも、聴覚障害のある方におすすめのサービスが「スグJOB」です。
スグJOBは障害者雇用専門求人サイトで、業界最大級の求人数を誇り、6,000件以上の障害者求人を保有しています。
スグJOBの特徴は以下の通りです。
- 業界最大級の求人数(6,000件以上)
- 手厚い個別サポート
- 専任のキャリアアドバイザーが在籍
- オンラインでの面談に対応
スグJOBには、各障害に詳しいキャリアアドバイザーが在籍しています。
あなたの適性やニーズを丁寧にヒアリングし、最適な求人情報を提案してくれます。
また、オンラインでの面談にも対応しているため、自宅にいながら相談することができます。
スグJOBを利用することで、聴覚障害のある方でも、ピッタリの仕事を見つけることができるでしょう。
まずは、気軽に相談してみることをおすすめします。
まとめ
低音障害型感音難聴は、適切な治療と環境調整によって、仕事との両立が可能な病気です。
症状に向き合い、自分に合った働き方を見つけるために、周囲の支援を上手に活用していきましょう。
前向きな姿勢で、新しい一歩を踏み出すことが、充実した社会生活につながるはずです。
最後に、低音障害型感音難聴に悩む全ての方に、エールを送ります。
あなたの適性を活かせる仕事は、必ずあります。 あなたの人生は、これからも輝き続けるでしょう。
聴覚障害と向き合い、自分らしく生きる。
それが、低音障害型感音難聴とともに歩む、あなたの人生です。
今日から、新しい一歩を踏み出してみませんか。

スグJOBは求人数トップクラス!
障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ
障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ
この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。