混合性結合組織病の人におすすめの仕事と就労支援
混合性結合組織病(MCTD)は、全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、多発性筋炎の特徴を合わせもち、全身のさまざまな部位に影響を及ぼす、複雑な症状の病気です。
関節痛や筋肉痛、手足の冷感など、日常生活や仕事に支障をきたす症状が現れるため、仕事選びや職場環境の整備が重要になります。

本記事では、混合性結合組織病についての基礎知識や、適切な働き方を見つけるためのヒントを解説します。
さらに、病気と共にキャリアを築くための支援策についても触れていきます。
混合性結合組織病について理解する
混合性結合組織病を理解することで、自分の症状に合った働き方を選び、健康と仕事の両立を目指す第一歩となります。
混合性結合組織病とは
混合性結合組織病(Mixed Connective Tissue Disease: MCTD)は、全身性エリテマトーデス(SLE)、全身性硬化症、皮膚筋炎/多発性筋炎などの症状が混在する病気です。
自己抗体が自身の結合組織を攻撃することで、複数の疾患の特徴を併せ持つ症状が現れます。そのため自己免疫疾患と考えられていますが、詳しい仕組みなどはまだ未解明となっています。

主な特徴
- 中年女性に多い:発症率は男女比で女性が優位で、特に30~50代での発症が多いです。
- 診断の難しさ:複数の症状が絡むため、診断には血液検査(抗U1-RNP抗体検出)や症状の経過観察が必要です。
- 症状の変化:病気が進行するにつれ、特定の症状が優位になる場合もあり、早期の治療と管理が重要です。
主な症状と治療法
混合性結合組織病は、症状の多様性が特徴です。
以下に主要な症状と治療法を詳しく説明します。
共通症状と混合症状
- レイノー現象
指先やつま先が寒さやストレスに反応して白や青紫色に変色する現象で、冷感やしびれを伴うこともあります。
治療法:保温対策を行います。症状がひどい場合には血管拡張薬が有効です。 - 関節痛・筋肉痛
関節リウマチのような痛みや腫れ、関節の変形が現れることがあります。
治療法:免疫抑制剤が用いられます。 - 全身性強皮症様症状
手のひらから肘にかけての皮膚硬化、肺疾患、食道や腸の機能低下などの症状が現れます。
治療法:症状に応じて抗線維化薬が用いられます。 - 倦怠感・疲労
長期間にわたる慢性的な疲労感は、仕事や日常生活に大きな影響を与えます。
治療法:十分な休息や栄養管理が推奨されます。
合併症と治療方針
- 肺動脈性肺高血圧症
肺の血管が狭くなり、血圧が上昇する状態で、息切れや動悸が主な症状です。
治療法:プロスタサイクリン製剤、エンドセリン受容体拮抗薬等症状に合わせた薬物療法を行います。 - 心臓の合併症
肺高血圧症で心臓に負担がかかる場合、心筋炎や心膜炎を発症する場合があります。胸痛や息苦しさが現れる際は、速やかな診察が必要です。 - 消化器症状
胃腸障害や嚥下困難が起きることがあり、栄養状態の管理が重要です。
治療法:消化器内科での治療や食事療法を併用します。
混合性結合組織病が労働生活に与える影響
混合性結合組織病(MCTD)は、体の多くの部位に影響を及ぼす自己免疫疾患であり、その症状の多様性から仕事や日常生活に大きな影響を与えることがあります。
本章では、混合性結合組織病の特性が労働生活に与える影響と、適した職種選びや職場での配慮事項について解説します。

疾患の特性と仕事への影響
混合性結合組織病は、体調の波や症状の進行により、日々の仕事にさまざまな困難をもたらす可能性があります。
疾患特性と主な課題
- 体調の変動
疲労感や倦怠感、関節痛が日によって異なるため、一定のスケジュールを維持することが難しい場合があります。
長時間の立ち仕事や過度な体力を必要とする業務は、症状を悪化させる可能性が高いです。 - 集中力の低下
痛みや倦怠感により、長時間集中して作業を行うことが難しくなることがあります。デスクワークであっても、症状によっては効率が下がる場合があります。 - 手足の不調
レイノー現象や筋力の低下により、細かい作業や重い物を持つ作業が困難になることがあります。 - 頻繁な医療機関への通院
定期的な診察や治療を必要とするため、休暇の取りやすさや勤務時間の柔軟性が求められます。
職場での主な課題
- 症状の理解が乏しい職場では、周囲の理解を得るのが難しい場合があります。
- 無理な業務スケジュールや、体調を考慮しない業務負担が症状を悪化させることがあります。
これらの課題を軽減するためには、症状を職場に適切に伝え、柔軟な働き方が可能な環境を整えることが重要です。
適した職種の選択と配慮事項
混合性結合組織病を抱える方が労働生活を送る上で、適した職種を選ぶことは、症状との両立を目指すための重要なポイントです。

適した職種の特徴
- 体への負担が少ない仕事
事務職、データ入力、カスタマーサポートなど、体力を必要としない業務が適しています。
これらの職種は、座り仕事が中心で、症状が安定している間に集中して作業を進めることができます。 - 柔軟な働き方が可能な職種
ITエンジニアやクリエイティブ系の職種(デザイナーやライターなど)は、在宅勤務が可能である場合が多く、体調に合わせて働くことができます。 - 自営業やフリーランス
自営業やフリーランスであれば、仕事量やスケジュールを自身で調整できるため、体調が不安定な時期にも対応しやすいです。
配慮事項と職場環境の工夫
- 勤務形態の柔軟性
フレックスタイム制や在宅勤務が導入されている職場では、体調に合わせて働く時間を調整できます。
パートタイムやジョブシェアリングを活用することで、無理なく働ける環境を整えやすくなります。 - 休憩の確保
疲労感や痛みを軽減するために、定期的な休憩を取りやすい職場が理想的です。
静かな休憩スペースがある職場環境は、症状を和らげる助けになります。 - 業務量の調整
症状が重い日には業務量を減らすか、負担が軽い業務を優先して行えるよう、上司や同僚と事前に調整しておくことが大切です。 - 病気への理解とサポート体制
症状について職場で共有し、同僚や上司がサポートできる体制を整えることで、安心して働ける環境が築けます。
混合性結合組織病におすすめの職場環境
混合性結合組織病(MCTD)は、体調が日々変化することが特徴であり、その症状と両立しながら働くには、適切な職場環境が不可欠です。
ここでは、在宅勤務やフレックスタイム制の導入、企業文化の理解が深い職場について詳しく解説します。
在宅勤務やフレックスタイム制の職場
在宅勤務のメリット
- 通勤負担の軽減
通勤は、疲労やストレスを増加させる要因の一つです。
在宅勤務であれば、通勤時間を省略でき、その分を体力温存や休養に充てることができます。 - 体調管理がしやすい
症状が重い日はベッドで休みながら作業を進めるなど、自分のペースで仕事を行えます。
必要に応じて医療機関へ通院する時間も調整しやすくなります。 - 静かな環境での作業
自宅では自分に合った環境(静音や適温)を整えやすいため、関節痛や疲労感の影響を受けにくくなります。

フレックスタイム制のメリット
- 柔軟な勤務時間
フレックスタイム制では、出勤や退勤の時間を自由に調整できるため、体調に合わせた働き方が可能です。
朝の症状が重い場合でも、少し遅い時間から仕事を始めることができます。 - 体調の良い時間帯に集中できる
自分の症状やエネルギーレベルが安定している時間帯を活用して、効率よく業務を進めることができます。
推奨される職種例
- ITエンジニア(プログラミング、システム運用など)
- グラフィックデザイナー、ライター、編集者
- カスタマーサポート(メール対応やチャットベースの業務)
理解のある企業文化と柔軟な勤務体系
理解のある企業文化の特徴
- オープンなコミュニケーション
病気や体調に関する情報を共有できる環境では、症状が悪化した際にスムーズにサポートを受けられます。
上司が業務量を調整してくれる、同僚が業務をフォローしてくれるなどの配慮が期待できます。 - 合理的配慮の実施
合理的配慮とは、障害を持つ従業員が働きやすくなるために企業が取る措置のことです。
勤務時間の調整、デスク周りの環境整備、リモートワークの導入などが含まれます。
柔軟な勤務体系の重要性
- 休憩の取りやすさ
混合性結合組織病で体調が不安定な場合は、体力回復のための休憩が不可欠です。
休憩時間や頻度に柔軟性を持たせることで、症状の悪化を防ぐことができます。 - 勤務形態の選択肢
パートタイム勤務や週3~4日勤務といった働き方が許される職場は、症状に合わせた勤務時間を選べるため、安心して働けます。
企業選びのポイント
- 障害者雇用の実績
障害者雇用の経験が豊富な企業は、病気に対する理解や合理的配慮が整っている場合が多いです。
事前にその企業の取り組みや評判を調べることが重要です。 - 試用期間やトライアル雇用
トライアル雇用制度を利用すると、企業と自分が相性を確認しながら無理なく仕事を始められます。
障害者雇用と年金制度の活用
混合性結合組織病(MCTD)を抱えながら働く方にとって、障害者雇用や年金制度は、生活を安定させながら働き続けるための重要な手段です。
ここでは、障害者手帳の取得や雇用支援制度、障害年金の申請方法と具体的な受給事例について解説します。
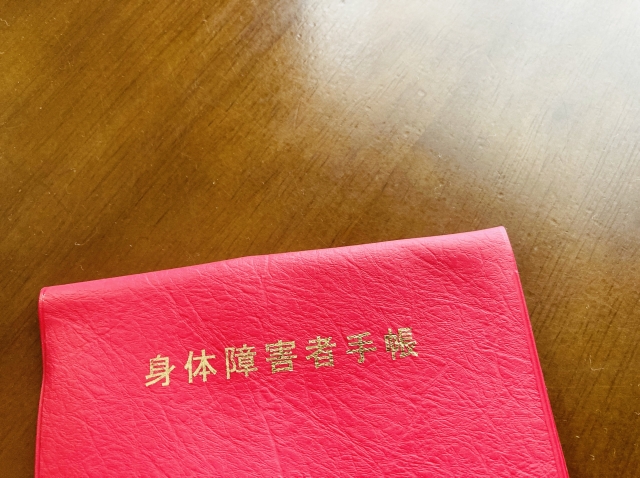
障害者手帳の取得と雇用支援制度
障害者手帳の取得の意義
障害者手帳は、身体や精神に一定以上の障害が認定された場合に交付される証明書で、就労支援や生活支援を受けるために重要な役割を果たします。
混合性結合組織病そのものは障害ではなく指定難病であり、障害者者手帳の取得対象ではありません。
ただし、混合性結合組織病を原因として関節や内臓に影響がある場合、身体障害者手帳が取得できる可能性があります。
取得のポイント
- 対象障害の確認
混合性結合組織病が原因で関節機能障害や視力障害などが認められる場合、手帳の交付対象となります。
医師の診断書が必須です。 - 申請手続き
申請は自治体の福祉課で行います。必要書類には、医師の診断書、住民票、顔写真が含まれます。 - 認定等級
障害の程度によって1級~6級が決定されます。この等級に応じて受けられる支援が変わります。
障害者雇用制度
障害者雇用促進法に基づき、企業には法定雇用率が義務付けられており、障害者雇用枠での採用が可能です。この制度を活用することで、働きやすい環境を見つけやすくなります。
主な支援内容
- 合理的配慮の提供
勤務時間の調整、在宅勤務の許可、設備の改善などの措置が義務化されています。 - トライアル雇用
試用期間を設けて、働きながら企業との相性を確認できます。 - 障害者就業・生活支援センターの利用
就労支援や職場での定着支援を提供してくれます。
障害年金の申請と受給事例
障害年金の概要
障害年金は、病気や障害により生活や仕事が困難になった方に対する公的支援です。
混合性結合組織病が原因で日常生活に制約がある場合、申請することで受給可能なケースがあります。

障害年金の種類
- 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方、もしくは20歳未満だった方が対象です。
- 障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
初診日要件
混合性結合組織病のため初めて医療機関を受診した日が、年金加入期間内であることが条件です。
初診日が厚生年金に加入していない時期にあたる場合は、障害基礎年金となります。
保険料納付要件
- 初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間に、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が全体の3分の2以上
- 上記に当てはまらない場合の特例として、初診日の前日時点で、2カ月前までの直近1年間に保険料未払期間がない
保険料納付要件は「初診日の前日」が基準となることに注意が必要です。
障害等級
障害基礎年金の受給には、障害の状態が1級、2級のいずれかに該当することが必要です。
障害厚生年金の場合は1級~3級のいずれかに該当する必要があります。
混合性結合組織病では、疾病そのものではなく、関節や内臓機能障害の症状の程度に応じて等級が判断されます。
必要書類
・年金手帳または年金番号通知書
・戸籍謄本
・病歴・就労状況等申立書
・振込先口座の情報
40代女性の障害厚生年金3級認定ケース
このケースでは、混合性結合組織病による関節機能障害と慢性的な疲労により、フルタイム勤務が難しい状態でした。
職場での勤務時間の短縮と休養を取りながら働いていましたが、病状が進行し、日常生活にも支障をきたすようになりました。
申請の経緯
- 初診日を証明するため、10年前の診療記録を医療機関から取得。
- 医師に詳細な診断書を作成してもらい、症状が日常生活や仕事に及ぼす影響を記載。
- 初診日が厚生年金加入期間中だったため、障害厚生年金の申請を選択。
認定結果
- 等級:3級
- 週3日程度のパートタイム勤務は可能だが、長時間の労働や通勤は困難と判断。
- 支給額:年額約60万円(加入期間に応じて金額は変動)
診断書には、生活上の制限や仕事への影響を具体的に記載してもらうことが重要です。
申請後は、数か月の審査期間を経て結果が通知されました。
混合性結合組織病の人が就職・転職で利用できる支援サービス
混合性結合組織病(MCTD)を抱える方が自分に合った職場を見つけるためには、支援サービスの活用が大いに役立ちます。
以下に、主な支援サービスを紹介します。
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワークでは、障害者雇用に特化した窓口や「専門援助部門」を設置しており、求職活動を支援しています。
提供されるサポート
- 障害者雇用に対応した求人情報の提供
- 応募書類の作成支援
- 面接対策やトライアル雇用制度の案内
利用ポイント
症状や働き方に配慮した求人を探しやすく、安心して相談できる環境が整っています。
地域障害者職業センター
独立行政法人が運営する地域障害者職業センターでは、就労に必要なスキルや適性を評価し、個別のサポートプランを提供します。
主なサービス
- 職業カウンセリングや適性検査
- 職場実習の提供
- 就労後の定着支援
おすすめの利用方法
初めて働く方や、職場に馴染むことが不安な方にとって心強いサポートを受けられます。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、一般企業での就労を目指す障害者を対象に、職業訓練やスキルアップの支援を行います。
支援内容
- ビジネスマナーやパソコンスキルの指導
- 模擬面接や職場体験の機会提供
- 就職後のフォローアップ
ポイント
自分の症状に合わせた働き方を模索するため、専門的な訓練が可能です。
障害者雇用に特化した転職サイト
障害者雇用専門の転職サイトは、自宅にいながら効率的に求人情報を探せる便利なツールです。
おすすめサイト:スグJOB
- 障害者向け求人情報を豊富に掲載
- 専任エージェントによる履歴書添削や面接対策
- 働き方に配慮した企業の情報提供
活用のポイント
登録後にエージェントと相談し、自分の体調やスキルに合った求人を見つけることが重要です。
まとめ
混合性結合組織病の人が働きやすい環境を整えるには、症状に配慮した職場選びが重要です。
ハローワークや地域障害者職業センター、就労移行支援事業所、スグJOBなどの支援サービスを活用し、自分に合った働き方を見つけましょう。
支援機関を上手に活用することで、病気を抱えながらも安心してキャリアを築くことが可能になります。

スグJOBは求人数トップクラス!
障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ
障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ
この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。










