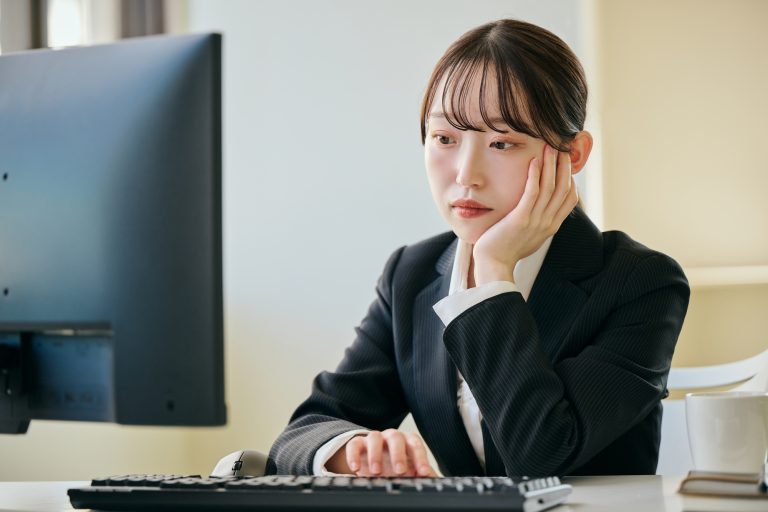障害者の年収アップ対策!給料と雇用の実態を解説
障害者雇用における年収や待遇の現状は、まだ多くの課題が残されています。
障害を持つ方の雇用機会が拡大する一方で、給料や年収面での格差は依然として大きいのが現状です。
非正規雇用が多いことや職種選択の制限、勤務時間の短縮などが、障害者の収入を低下させる要因となっています。
本記事では、障害者の雇用状況や給料の実態について詳しく解説し、年収アップのための具体的な方法を紹介します。
また、障害者にとって働きやすい職場を探す方法も併せて取り上げています。
この記事を通じて、自分に合った働き方やキャリア形成のヒントを得ていただければ幸いです。

障害者の雇用と給料の現状
障害者の雇用や給料の現状について、具体的なデータを元にその課題を紐解きます。
障害者の平均年収は一般雇用と比べて低く、その背景には多くの要因があります。
本章では、障害者の給料の実態を確認し、その低さの理由についても深掘りしていきます。

障害者雇用の平均給料と年収
障害者の平均月収は、障害の種類によって差があります。
厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」によれば、以下の通りです。
- 身体障害者:平均月収は約21万5,000円。
- 知的障害者:平均月収は約11万7,000円。
- 精神障害者:平均月収は約12万5,000円。
これらの数値は、雇用形態や勤務時間、業務内容によっても変動します。
障害種別ごとの給料平均
障害の種類によって、従事する職種や業務内容が異なるため、給与にも差が生じます。
- 身体障害者:事務職や専門的・技術的職業に就く割合が高く、比較的高い給与を得ている傾向があります。
- 知的障害者:生産工程やサービス業に従事することが多く、時給制での雇用が多いため、平均月収が低くなる傾向があります。
- 精神障害者:サービス業や事務職、販売職に就くことが多く、知的障害者と同様に時給制での雇用が多い傾向があります。
これらの違いは、各障害の特性や企業側の配慮によるものと考えられます。
一般雇用との違い
一般雇用者の平均年収は約440万7,000円で、月収に換算すると約30万円となります。
これと比較すると、障害者の平均月収は全体的に低い水準にあります。
この差の要因として、以下の点が挙げられます。
- 雇用形態の違い:障害者は非正規雇用や短時間勤務が多く、これが収入の低さにつながっています。
- 職種の違い:障害者は補助的業務や単純作業に従事することが多く、これが給与水準の低さに影響しています。
- 昇進・昇給の機会の違い:障害者は昇進や昇給の機会が限られている場合が多く、これが長期的な収入の伸びを抑制しています。
これらの要因が重なり、障害者の収入は一般雇用者と比較して低くなる傾向があります。
給料が低くなる傾向にある理由
障害者の給料が低くなる背景には、以下のような要因が挙げられます。
非正規で働いている人が多い
多くの障害者がパートタイムやアルバイトといった非正規雇用の形態で働いています。
非正規雇用は、正社員に比べて時給や月給が低いだけでなく、雇用契約が短期間で更新されるケースが多いため、収入の安定性に欠けます。
さらに、非正規雇用者には、企業が提供する社会保険や福利厚生が適用されない場合も多く、特に退職金や年金制度が整備されていないことが課題です。
これにより、長期的な生活基盤を築きづらく、経済的な不安が伴うことになります。
障害者にとっては、正規雇用への移行が収入向上と生活の安定に大きく寄与しますが、企業側の雇用環境や制度に改善の余地があるのが現状です。
できる仕事の範囲に制限がある
障害の特性や健康状態により、障害者が従事できる業務の範囲が限定される場合が多いです。
例えば、身体障害者の場合、長時間の立ち仕事や重い荷物を扱う仕事が難しいことがあります。
一方で、精神障害者や発達障害者の場合、対人業務や複雑なマルチタスクが求められる業務に制限が生じることもあります。
このような制限は、業務内容が単純作業や補助的な業務に集中する結果を招き、賃金水準が低い業種に集中する傾向を生み出します。
また、企業側も業務を細分化して提供する必要があり、これが障害者の収入向上を阻む要因になっています。
就いている職種ではキャリアアップがしづらい
障害者雇用において、補助的業務や単純作業が多くを占める現状があり、これらの職種では昇進やキャリアアップの機会が限られています。
例えば、工場や倉庫の軽作業、事務補助業務、清掃業務などが代表的な職種です。
これらの職種はスキルの向上が求められる場面が少なく、評価基準も昇進に直結しづらいものとなっています。
その結果、長年同じ職場で働いても収入が変わらないケースが多いです。
また、キャリアアップを目指しても、障害に配慮した研修やスキル開発の機会が限られていることが課題となっています。
スキルの向上や職域の拡大を支援する取り組みが、企業や社会全体で必要とされています。
勤務時間の制限
障害者の中には、体調管理や生活リズムの維持を理由に短時間勤務を選択せざるを得ない方が多くいます。
例えば、精神障害者の場合、ストレスや疲労が症状を悪化させるリスクがあるため、1日4~6時間程度の勤務を希望する方が多いです。
また、身体障害者にとっても、通勤時間の負担や職場での移動時間が体力を消耗させるため、短時間勤務が求められることがあります。
このような勤務時間の短縮は、フルタイム労働者と比較して収入面で大きな差が生じる原因となります。
さらに、短時間勤務者には、社会保険の適用基準を満たせない場合があるため、経済的な負担が増える場合もあります。
減額特例許可制度による最低賃金の減少
減額特例許可制度は、障害の特性や就労能力に応じて、最低賃金の適用を免除する制度です。
これは、企業が障害者の就労機会を増やすことを目的とした仕組みですが、一方で障害者の収入がさらに低くなる要因ともなっています。
この制度が適用されると、時給が最低賃金を下回る水準に設定される場合があり、結果的に総収入が少なくなるケースがあります。
例えば、軽作業や短時間労働を行う場合、時給が大幅に引き下げられる可能性があります。
このような状況は、障害者の自立を妨げるだけでなく、長期的な生活の安定を阻害するリスクを伴います。
制度の見直しや、企業が適正な賃金を支払うための支援が必要とされています。
障害者が年収アップを目指すための方法
障害者が年収をアップさせるには、資格取得や正社員登用の活用、転職、公的制度の利用など、さまざまな方法があります。
本章では、それぞれの具体的な取り組みを解説します。
資格取得にチャレンジする
資格取得は、障害者がスキルを明確に証明し、収入を向上させる有効な方法です。
特に事務職やIT関連、介護分野などは障害の有無に関わらず需要が高いため、収入アップにつながりやすい分野です。

おすすめ資格例
- 簿記検定:経理や財務職への道を開く資格。比較的取得が容易で、安定した職種につながります。
- MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト):WordやExcelのスキルを証明する資格で、事務職での活躍に役立ちます。
- 介護福祉士:介護業界は人手不足が深刻なため、安定した雇用と収入が期待できます。
- ウェブデザイン技能検定:在宅勤務が可能なスキルを証明し、柔軟な働き方を実現します。
資格取得に向けては、障害者向けの教育支援や助成金制度を活用することが推奨されます。
特に公共の職業訓練機関では、無料または低価格で資格講座を受講できる場合があります。
正社員登用制度を活用する
多くの企業では、非正規雇用者を対象にした正社員登用制度が用意されています。
この制度を利用することで、安定した雇用と収入を得ることが可能です。
具体的な活用方法
- 企業選びの段階で確認する:求人情報や企業の採用ページで、正社員登用実績があるか確認します。
- 目標設定を行う:勤務実績や評価基準を確認し、何を達成すれば正社員登用のチャンスがあるのかを明確にします。
- 自己評価の向上:スキルを高め、責任感を持って業務を遂行することで、上司や同僚からの信頼を得ます。
正社員になることで、給与や福利厚生が大幅に改善されるだけでなく、キャリア形成の機会も広がります。
また、企業によっては障害者向けの正社員枠を設けている場合もあります。
経験のある業界・職種に転職する
過去の職務経験やスキルを活かして転職することは、年収をアップさせる有効な手段です。
特に、障害者雇用を積極的に行っている業界や、自身が働きやすい環境が整っている企業を選ぶことが重要です。
- 専門知識を活かせる業界を選ぶ:例えば、ITスキルを持つ場合、在宅勤務が可能なプログラミングやデザイン職種が適しています。
- 障害者雇用に積極的な企業を探す:ハローワークや専門求人サイトを利用して、自分のニーズに合う企業を見つけましょう。
- 職場環境を確認する:面接時にバリアフリー対応や就業時間の柔軟性について確認し、自分に合った職場かどうかを見極めます。
転職活動を成功させるためには、履歴書や職務経歴書の作成を充実させるとともに、面接対策も重要です。
支援機関を活用してサポートを受けることをおすすめします。
公的な制度を最大限利用する
障害者向けに提供されている公的な制度は、収入の補填や生活費の軽減に大きく役立ちます。
これらの制度を積極的に活用することで、経済的な余裕を得られる可能性があります。
障害年金
障害者年金は、障害等級に応じた支給額が設定されており、障害者の収入を補完する重要な制度です。
具体的には、以下のようなポイントがあります:
- 対象者:国民年金または厚生年金の加入者で、一定の障害等級を持つ方。
- 支給額:等級や加入期間によって異なりますが、月額数万円から10万円以上が支給される場合があります。
- 申請方法:障害認定書類を添付し、年金事務所で手続きを行います。
障害者の医療関連制度
医療費の負担を軽減するための制度も多く存在します。
例えば:
- 重度障害者医療費助成:自治体が医療費の自己負担分を一部または全額補助する制度。
- 高額療養費制度:医療費が一定額を超えた場合、超過分が返還される制度。
これらの制度を利用することで、医療費の負担を大幅に軽減できます。
ハローワーク(障害者窓口)
ハローワークでは、障害者向けに特化した窓口を設置しており、以下のようなサポートを提供しています:
- 求人情報の提供:障害者雇用に積極的な企業の求人情報が得られます。
- 職業訓練:スキルアップのための研修や講座を無料で受講できる場合があります。
- 就職支援:履歴書作成や面接練習、企業とのマッチング支援を行っています。
公的施設、交通機関等の割引制度
公共交通機関や公的施設では、障害者向けの割引制度が提供されています。
例えば:
- 公共交通機関の割引:鉄道やバスの運賃が割引される制度が全国で適用されています。
- 文化施設や公園の無料利用:一部の博物館や公園では、障害者手帳を提示することで無料または割引価格で利用できます。
これらの制度を活用することで、生活費を大幅に削減し、経済的な余裕を生み出せます。
障害者にとって働きやすい職場の探し方
障害者が働きやすい職場を見つけるためには、専用の就職支援機関やイベント、オンライン求人サイトを活用することが効果的です。
以下に、具体的な方法を詳しく解説します。
ハローワーク(職業安定所)
ハローワークは、障害者の就職支援に特化した窓口を設置しており、無料で幅広いサービスを受けることができます。

障害者専門窓口:障害者雇用を前提とした求人情報が多く掲載されており、自分の特性やスキルに合った仕事を探すことができます。
職業訓練の提供:特定のスキルや資格を取得するための講座があり、無料または低料金で受講可能です。
事務職向けのパソコン講座やサービス業向けの接客スキル講座などが人気です。
面接対策や履歴書作成支援:
就職活動に必要な書類作成のアドバイスや、面接練習のサポートも受けられます。
企業とのマッチング:企業の採用担当者との個別相談会を実施しており、直接的な採用につながる場合もあります。
ハローワークは、全国に窓口があり、アクセスしやすいのも大きなメリットです。
特に初めて就職活動をする障害者にとっては、安心して利用できるサポート機関です。
就職フェア・合同説明会
就職フェアや合同説明会は、障害者雇用に特化したイベントが開催されることが多く、企業と直接話す貴重な機会を提供します。
障害者雇用に特化したイベント:企業が障害者雇用を積極的に行っている場合、これらのイベントに出展していることが多いです。
障害者に配慮した職場環境やサポート体制について具体的に確認することができます。
直接質問が可能:職場の雰囲気や勤務条件、求めるスキルなどを採用担当者に直接尋ねることができるため、ミスマッチを防ぎやすいです。
即日面接の機会も:場合によっては、その場で一次面接を行い、採用が進むケースもあります。
特に積極的に採用活動を行っている企業では、迅速な選考が行われることもあります。
ネットワーク作り:他の求職者との交流を通じて、情報交換やキャリア形成のヒントを得ることも可能です。
就職フェアは、全国各地で定期的に開催されており、オンライン形式のイベントも増えているため、気軽に参加しやすいのが特徴です。
障害者雇用専門求人サイトの活用
障害者雇用専門求人サイトは、障害者に特化した求人情報を提供しており、自分に合った職場を効率的に探すことができます。
詳細な条件検索が可能:勤務地、給与、勤務時間、障害者支援体制など、自分の条件に合う求人を簡単に絞り込むことができます。
障害者雇用に特化した企業が集結:障害者を積極的に雇用している企業の情報が豊富に掲載されており、職場環境やサポート体制についての詳細な情報も確認できます。
応募書類の作成支援:サイト内で履歴書や職務経歴書を簡単に作成・保存できる機能がある場合が多く、応募時の手間を軽減できます。
スグJOBの活用:障害者の就職支援に特化した求人サイト「スグJOB」では、障害者雇用に積極的な企業を多数掲載しています。
また、応募者の特性やスキルに合わせた求人提案機能もあり、初めての就職活動でも安心して利用できます。
まとめ
障害者が働きやすい職場を見つけるには、ハローワーク、就職フェア、専門求人サイトなど、さまざまな手段を組み合わせて活用することが重要です。
ハローワークでは専門的なサポートが受けられ、就職活動を効果的に進められます。
就職フェアや合同説明会では企業と直接話し、職場環境や条件を確認することが可能です。
障害者雇用専門求人サイトを利用することで、効率的に自分に合った求人を探すことができます。
特に「スグJOB」のような障害者支援に特化した求人サイトは、サポート体制が充実しており、初めての求職活動でも安心して利用できます。
これらのツールを活用し、自分に合った働きやすい職場を見つけてください。

スグJOBは求人数トップクラス!
障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ
障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ
この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。