障害者雇用での配慮不足による課題と解決策
障害者雇用において、職場の「配慮不足」は多くの方が直面する課題です。
本来、障害者の方が安心して働ける環境を整えるためには、それぞれの障害特性に応じた適切な配慮が求められます。
しかし、現実には「理解が足りない」「サポート体制が不十分」と感じる事例が少なくありません。
こうした配慮不足が続くと、働きづらさが増し、ストレスや不安が高まります。

結果として、仕事に対するモチベーションが低下し、最終的には退職を選ばざるを得ない状況に追い込まれることもあります。
本記事では、障害者雇用における「配慮不足の現状」や「配慮が足りないことで生じる課題」を解説し、解決策として企業や障害者本人が取り組めるポイントを詳しく紹介します。
「職場での配慮がなくて困っている…」
「配慮を求めたいけど、どう伝えればいいかわからない…」
「もし今の職場で配慮が得られないなら、どうすればいい?」
そんな不安や悩みを抱える方に向けて、役立つ情報をわかりやすくお届けします。
この記事を読んで、働きやすい職場環境を実現するためのヒントを見つけてください。
障害者雇用での配慮不足の現状
障害を抱える方が安心して働くためには、それぞれの障害特性に応じた適切な配慮が必要です。
しかし、実際の職場では、「配慮が足りない」「サポート体制が整っていない」「周囲の理解が不足している」と感じる方が多くいます。
その結果、働きづらさを感じ、ストレスがたまり、仕事を続けることが難しくなるケースも少なくありません。
ここでは、障害者雇用における配慮不足の現状について詳しく解説し、どのような場面で配慮が不足していると感じるのか、そして障害を抱える方が抱える不安や課題について考えていきます。
障害者従業員の不安点
障害に対する配慮がない
障害を抱えて働いている方の多くが「職場の環境や制度に配慮が足りない」と感じています。
例えば、以下のようなケースが挙げられます。
- 身体障害者:車椅子での移動が難しい、バリアフリーが不十分な職場。
- 聴覚障害者:会議や連絡事項が音声のみで伝えられ、内容を把握できない。
- 精神障害者:体調に波があるのに、柔軟な勤務形態が認められない。
- 発達障害者:曖昧な指示やマルチタスクが求められ、業務をこなすのが困難。
こうした配慮不足が続くと、業務遂行に支障をきたし、「この職場では働いていけないかもしれない」と強い不安を抱えることになります。
障害に関する情報が共有されていない
障害の特性や必要な配慮について適切に情報共有されていないことが多くあります。
その結果、以下のような問題が発生します。
- 上司や同僚が障害の特性を理解しておらず、適切な対応ができない。
- 必要な配慮が行われず、誤解や偏見が生じやすくなる。
- 障害者本人が、周囲の理解がないと感じ、職場で孤立してしまう。
例えば、精神障害を持つ方が「定期的に休憩をとることで安定して働ける」という情報が共有されていないと、「仕事をサボっているのでは?」と誤解されてしまうことがあります。
また、聴覚障害を持つ方が筆談やチャットでのやり取りを希望しているにもかかわらず、それが周囲に伝わっていないと、会話の機会が減り、業務上のミスにつながることもあります。
こうした問題を防ぐためにも、障害に関する適切な情報共有は欠かせません。

配慮がないと感じる場面
障害者が職場で「配慮が足りない」と感じるのは、特定の場面でよく見られます。
- 採用段階での壁
- 面接時に障害への理解がなく、不適切な質問をされる。
- 採用プロセスが健常者向けに設計されており、障害者が不利になる。
- 「配慮が必要なら、採用できない」と言われ、選考で不利になる。
- 入社後の職場環境
- 合理的配慮の制度があっても、現場で実施されていない。
- 職場の設備や業務内容が障害特性に合っていない。
- 上司や同僚の理解が不十分で、協力が得られない。
- キャリアアップの機会
- 昇進や評価の基準が健常者と同じで、障害者には不利に働く。
- 研修やスキルアップの機会が限られている。
- 「障害者だから」と業務の幅を広げてもらえない。
このような場面での配慮不足は、働くモチベーションを大きく下げてしまう原因になります。
障害別の合理的配慮の希望例
障害の種類によって、必要な配慮は異なります。
適切な配慮が行われれば、自分の力を最大限に発揮しやすくなり、企業にとっても戦力となるのです。
| 障害の種類 | 合理的配慮の例 |
| 身体障害者 | 車椅子が通れるオフィス設計、エレベーターの確保、机や椅子の高さ調整 |
| 聴覚障害者 | 手話通訳や筆談の導入、会議での文字起こしソフトの活用 |
| 視覚障害者 | 点字資料の用意、スクリーンリーダー対応のPC環境 |
| 精神障害者 | 柔軟な勤務時間の設定、ストレスの少ない業務設計 |
| 知的障害者 | わかりやすいマニュアルの提供、業務を細かく区切って指示 |
| 発達障害者 | 明確な業務指示、集中できる作業スペースの確保、タスク管理の支援ツールの導入 |
このような合理的配慮が行われれば、障害者の方の職場適応を促進し、長く働き続けることができる環境を作ることができます。
「職場での配慮不足に悩んでいる」という方は、まずどのような配慮が必要かを整理し、職場で伝えることから始めてみましょう。
配慮不足による課題
職場での配慮不足は、障害者雇用の従業員だけでなく、企業全体にも影響を及ぼします。
必要な配慮が行われない職場では、障害者の方が長く働き続けることが難しくなり、結果として離職率が高まる傾向にあります。
また、障害者雇用のサポートを担当する社員にも負担が集中し、職場全体の生産性が低下するリスクもあります。
ここでは、障害者雇用における職場定着率への影響や退職理由、企業側が抱える課題について詳しく解説します。
障害者雇用の職場定着率への影響
職場に適切な配慮がないと、障害を抱える方が長く働き続けることは難しくなります。
障害者職業総合センターのデータによると、精神障害者の1年後の職場定着率は約49.3%と、身体障害者(約65%)や知的障害者(約71%)と比べても低い水準にあります。(障害者職業総合センター|「障害者の就業状況等に関する調査研究」|2020年|https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku137.html)
つまり、精神障害を持つ方の約半数が、就職してから1年以内に退職してしまうのです。
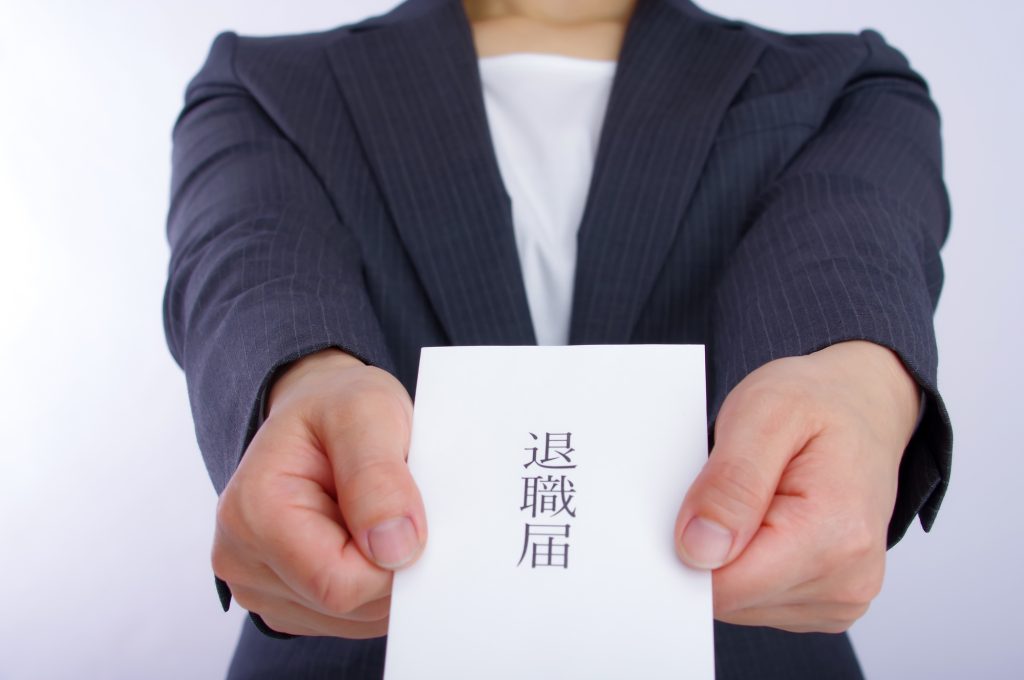
職場定着率が低下する主な要因として、以下のような点が挙げられます。
- 障害の特性に合った業務や働き方の配慮がされていない
- 職場の人間関係がうまくいかず、相談できる相手がいない
- 過度なストレスを抱え、体調を崩してしまう
- キャリアアップの道筋が見えず、モチベーションが下がる
職場定着率が低いと、企業側も採用や育成のコストが増加するため、障害者が長く働ける環境を整えることが非常に重要です。
障害者の主な退職理由
障害を抱える方が退職を決意する背景には、職場での配慮不足や働きづらさがあります。
以下に、退職理由として特に多いものをいくつか紹介します。
- 職場環境への不適応
- 必要な合理的配慮が受けられず、業務遂行が困難になってしまう。
- 職場がバリアフリーになっておらず、移動や作業がしづらい。
- 精神的な負担が大きく、体調を崩してしまう。
- 人間関係の問題
- 上司や同僚が障害への理解を十分に持っておらず、配慮を受けられない。
- 「障害を理由に特別扱いされたくない」と思っていても、周囲からの過度な気遣いが逆にプレッシャーになる。
- コミュニケーションのすれ違いにより、孤立してしまう。
- キャリアアップの機会不足
- 障害を理由に、「昇進のチャンスが与えられない」「責任ある仕事を任せてもらえない」と感じる。
- スキルアップの研修が用意されておらず、成長の機会がない。
- 給与が低く、長く働き続けることが難しいと判断する。
こうした問題が積み重なることで「この職場では長く働けない」と感じ、退職を選択してしまうのです。
企業側の課題:担当者への負担増大
障害者雇用に関する配慮が適切に行われていないと、企業側の負担も増えてしまいます。
特に、サポートを担当する人事担当者や直属の上司が、対応に追われて業務負荷が大きくなることがあります。
具体的には、以下のような課題が生じます。
| 課題 | 具体的な影響 |
| 担当者が1人で対応している | 相談対応が一極集中し、業務の負担が増加する。 |
| 社内の障害者雇用に関する知識が不足 | どう対応すればよいかわからず、適切なサポートができない。 |
| 本人が支援を求めにくい環境 | 相談しづらい雰囲気があると、問題が長期化してしまう。 |
このような状況が続くと、担当者自身が疲弊し、障害者雇用をポジティブに進めることが難しくなる可能性があります。
障害者雇用でのトラブル事例
障害者雇用の現場では、適切な配慮がないとさまざまなトラブルが発生することがあります。
例えば、障害特性を考慮せずに業務を割り振られることで、体調を崩してしまったり、職場の理解不足から人間関係のストレスが増えてしまうこともあります。
また、適切な評価がされずに、働く意欲が下がるケースも少なくありません。
ここでは、障害者雇用において実際に起こりやすいトラブル事例を紹介し、それぞれの課題について詳しく解説します。
障害者雇用でのトラブル事例
ここでは、障害者雇用において実際に起こりやすいトラブル事例を紹介し、それぞれの課題について解説します。
症状の悪化
障害の特性に応じた配慮がされていないと、体調が悪化し、働き続けることが難しくなることがあります。
特に以下のようなケースがよく見られます。
- 精神障害を持つ方がストレスを過度に感じ、症状が悪化してしまう
- 身体障害者の方が無理な姿勢で作業を続けた結果、健康状態が悪化する
- 視覚障害者の方が適切な補助ツールを利用できず、目の疲労や頭痛がひどくなる
例えば、うつ病や適応障害を持つ人が「周囲の理解が得られない環境」で働き続けると、症状が再発しやすくなります。
また、「合理的配慮が得られないまま仕事を続けることは、障害者の方本人にとって大きな負担」となり、最終的に離職を選ぶケースも多いのです。

上司・同僚とのコミュニケーショントラブル
職場の障害に対する理解が不十分な場合、上司や同僚とのコミュニケーションに課題が生じることがあります。
代表的なトラブル例として、以下のようなものが挙げられます。
- 障害の特性を理解してもらえず、配慮のない言葉をかけられる
- 適切な業務指示がないため、ミスが増えてしまい、誤解を招く
- 「特別扱い」と誤解され、職場内で孤立してしまう
例えば、発達障害を持つ人が「曖昧な指示では理解しにくい」という特性を持っているにも関わらず、「言われたことができない」と評価されてしまうことがあります。
また、聴覚障害を持つ人が「筆談やチャットでのやり取りを希望している」のに、上司や同僚がそれを実施せず、コミュニケーションがうまく取れないこともあります。
このような問題を解決するためには、職場内での障害特性の理解を深め、適切な配慮を実施することが必要です。
仕事がうまく進められない
業務内容が特性に合っていないと、仕事がスムーズに進まなくなることがあります。
よくあるトラブルとして、以下のようなケースがあります。
- 視覚障害者の方が紙の資料を使った業務を求められ、対応できない
- 発達障害者の方がマルチタスクを求められ、混乱してしまう
- 精神障害者の方が突発的な業務変更に対応できず、ストレスを抱える
例えば、発達障害者の方は「タスクの優先順位をつけるのが苦手」な場合があるため、複数の仕事を一度に振られるとパニックになってしまうことがあります。
また、身体障害者の方が「特定の動作が困難」であるにも関わらず、業務内容が変更されないと、仕事をこなすのが難しくなることもあります。
このような場合、障害者が適切なサポートを受けられる環境を整え、必要に応じて業務を調整してもらうことが重要です。
評価に不満がある
職場で適切な評価を受けられないと、モチベーションが低下し、働く意欲を失ってしまうことがあります。
よくある評価に関するトラブルとして、以下のような例があります。
- 健常者と同じ基準で評価され、障害特性が考慮されていない
- 「仕事ができない」と決めつけられ、キャリアアップの機会が与えられない
- 逆に「障害者だから」と甘い評価をされ、成長のチャンスを逃してしまう
例えば、精神障害を持つ人が「体調に波があるため、時折業務量を調整する必要がある」のに、それが「仕事に対する意欲が低い」と評価されてしまうことがあります。
また、「障害者だから仕方ない」と過度に配慮され、責任のある仕事を任せてもらえないというケースもあります。
このような不公平な評価が続くと、「この職場では努力しても評価されない」と感じ、転職を考える原因となってしまいます。
障害者への合理的配慮の重要性
障害者雇用において、「合理的配慮」は単なる善意ではなく、法律で義務化されている重要な取り組みです。
企業が適切な合理的配慮を提供することで、障害を抱える方が安心して働ける環境を整えられ、ひいては職場全体の生産性やチームワークの向上にもつながります。
しかし現実には、「配慮が得られないために退職を考えてしまう」という障害者側の悩みや、「どの程度の配慮をすればよいかわからない」という企業側の戸惑いが多く見られます。
ここでは、合理的配慮の義務化の経緯、配慮の範囲と限界、配慮不足による退職リスクについて詳しく解説します。
合理的配慮の義務化の経緯
「合理的配慮」は、2016年に施行された「障害者差別解消法」によって、企業が提供すべき義務として定められました。
さらに、2021年には「中小企業も合理的配慮を提供する義務の対象」となり、企業規模を問わず、障害者の働きやすい環境を整えることが求められるようになりました。

これにより、すべての企業が以下のような対応を行うことが必要となりました。
合理的配慮を提供する義務のポイント
- 障害者が働く上で直面する困難をできる限り軽減するための調整を行う。
- 障害者本人が求めた配慮について、企業が「不当な拒否」をしてはいけない。
- ただし、企業側にとって「過度な負担」となる場合は、合理的配慮の提供を求められない。
つまり、障害を抱える方が働きやすい環境を整えることは、企業の責務であり、単なる努力目標ではないのです。
しかし、どの範囲までの配慮が求められるのか、その限界についても理解しておく必要があります。
合理的配慮の範囲と限界
合理的配慮の範囲は、「企業が過度な負担にならない範囲で可能な配慮」とされています。
例えば、以下のような配慮は、多くの企業で実施可能な合理的配慮とされています。
企業が対応しやすい合理的配慮の例
| 配慮の種類 | 具体例 |
| 勤務時間の調整 | 通院のための柔軟な勤務時間、短時間勤務制度 |
| 職場環境の整備 | 車椅子でも移動しやすい通路の確保、手すりの設置 |
| コミュニケーション方法の工夫 | 聴覚障害者への筆談対応、口頭指示の補助としてメールやチャットを活用 |
| 業務内容の配慮 | 過度なマルチタスクを避け、個別の業務内容を明確にする |
| 職場でのサポート | 障害者が困ったときに相談できる担当者の配置 |
しかし、企業の経営を圧迫するような過度な配慮は求められません。
以下のようなケースは、「合理的配慮」の範囲を超えていると判断される可能性があります。
企業にとって過度な負担となる可能性がある配慮の例
- 1人の障害者のために全社的な業務システムを大幅に変更する。
- 専門スタッフを常駐させることを求める。
- 他の従業員の業務負担が著しく増大するような配慮を求める。
こうした「過度な負担」を避けつつ、障害者にとって働きやすい職場環境を提供することが、企業側の義務となります。
配慮なしによる退職リスク
企業から適切な合理的配慮を提供されないと、障害を抱える方の離職率が高まるリスクがあります。
特に、精神障害を持つ方の離職率は高く、1年以内の離職率が50%近いというデータもあります。
配慮が不十分な職場では、以下のような理由で離職を選択することが多くなります。
合理的配慮がないことで発生する離職理由
- 職場環境が合わず、体調を崩してしまう。
- 障害特性に合わない業務を求められ、成果が出せない。
- 上司や同僚との意思疎通がうまくいかず、孤立してしまう。
- 「障害者だから」と、昇進やスキルアップの機会が与えられない。
例えば、聴覚障害者の方が「会議の内容が聞き取れないまま業務を進めなければならない」といった状況が続くと、仕事の成果に影響が出てしまいます。
また、精神障害者の方が「体調が不安定なときに配慮が得られない」場合、ストレスが増大し、最終的に退職を選んでしまうケースもあります。
配慮不足の解消策
職場での合理的配慮が不足している場合、それを改善するためには「企業」と「障害者本人」の双方の協力が不可欠です。
合理的配慮は企業側の義務ですので、企業側が適切に理解し、実施することが最も大切です。
しかし、障害者本人も自身の必要な配慮を明確に伝えることが求められます。
ここでは、企業ができる具体的な取り組みと、障害者本人が配慮を求める際のポイントを詳しく解説します。
職場の合理的配慮への理解度確認
まず、企業側が「合理的配慮とは何か」を正しく理解することが大前提です。
しかし、多くの職場では、合理的配慮に関する知識が不足しており、結果として障害者が働きづらさを感じる状況が生じています。
企業側が取り組むべきポイント
- 社内研修の実施
- 障害特性や合理的配慮についての研修を実施し、管理職や一般社員の理解を深める。
- アンケート調査やヒアリング
- 現在の職場環境について、障害者本人から直接意見を聞き、課題を把握する。
- 障害者支援機関と連携
- 専門機関のアドバイスを受けながら、職場の合理的配慮の改善策を検討する。
例えば、「障害者にとって働きやすい職場とは?」というテーマで、本人を交えた定期的なディスカッションを行うことで、社員の意識を高めることができます。
障害者本人から企業への配慮事項の伝達
障害者本人も「どのような配慮が必要か」を具体的に伝えることが重要です。
企業が障害の特性を十分に理解していない場合、「何に困っているのか」「どのような支援が必要なのか」が曖昧になり、適切な配慮が提供されないことがあります。

配慮事項を伝える際のポイント
- 具体的に説明する
- 「周囲の理解がほしい」ではなく、「マルチタスクが苦手なので、業務の優先順位を明確にしてほしい」と伝える。
- 業務に直結する内容にする
- 例えば、「静かな環境で作業したい」という要望がある場合は、「集中できる作業スペースの確保」を依頼する。
- 配慮事項を文書化する
- 口頭だけではなく、「業務で必要な配慮事項リスト」を作成し、企業と共有することで、後々のトラブルを防ぐ。
例えば、発達障害のある方が「口頭指示だけだと混乱しやすい」場合、「口頭指示に加えて、文書やメールでも業務内容を伝えてほしい」と具体的に依頼することで、よりスムーズに対応してもらえる可能性が高まります。
外部の障害者支援機関への相談
企業内での配慮が十分でない場合は、外部の障害者支援機関に相談することも有効です。
専門機関は、本人の働きやすさをサポートするだけでなく、企業側との調整も行ってくれるため、問題解決につながりやすいです。
活用できる主な支援機関
| 支援機関 | 提供されるサービス |
| 障害者就業・生活支援センター | 障害者と企業の間に入り、職場環境の調整をサポート |
| ハローワーク(専門援助部門) | 就職や職場定着のための支援を提供 |
| ジョブコーチ支援 | 企業にジョブコーチを派遣し、職場環境の適応を支援 |
例えば、「配慮を求めても企業側が対応してくれない…」という場合、障害者就業・生活支援センターに相談し、企業との調整を依頼することで、解決に向かうケースがあります。
日々のコミュニケーションや面談での状態把握
定期的なコミュニケーションは、職場の配慮不足を解消する大きなカギとなります。
企業と積極的に意見を交換することで、問題が深刻化する前に対応が可能になります。
効果的なコミュニケーションの方法
- 定期的な1on1面談を実施してもらう
- 1カ月に1回など、決まった頻度で上司や支援担当者との面談を実施し、業務や職場環境の悩みを共有する。
- 気軽に相談できる仕組み
- 相談しやすい環境を整え、必要な時にすぐに支援を受けられる体制をつくる。
- 状況を可視化する
- 業務の負担が大きい場合は、「体調やストレスの度合いを記録するシート」を活用し、上司と共有する。
例えば、「業務の負担が増えてきている」と感じたとき、面談で「どの業務が負担になっているのか?」を整理し、業務調整を依頼することで、早めの対策が可能になります。
支援機関や助成金の活用
企業が障害者雇用を進める際には、国や自治体の助成金制度を活用することも有効です。
助成金を活用することで、企業は合理的配慮を提供するための経済的な負担を軽減しやすくなります。
活用できる主な助成金
| 助成金の種類 | 内容 |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 障害者を雇用した企業に対し、一定期間の助成金を支給 |
| 障害者職場適応援助助成金(ジョブコーチ制度) | 企業にジョブコーチを派遣し、職場適応を支援 |
| 合理的配慮助成金(自治体による) | バリアフリー改修費や機器購入費の一部を助成 |
例えば、「バリアフリー化の費用が負担になる」と考えている企業も、助成金を活用することで負担を軽減し、スムーズに職場環境を整えることができるのです。
それでも配慮が得られない場合
企業に何度相談しても適切な配慮が提供されず、働きづらさが解消されない場合、別の選択肢を検討することになります。
「この職場で頑張りたいけれど、どうしても状況が改善されない…」
「もっと自分に合った環境で働ける場所があるのでは?」
このような不安を感じている場合、無理に今の職場に留まるのではなく、新しい環境を探すことを前向きに考えてみることも大切です。
ここでは、転職を考えるべきタイミングや、配慮のある職場の見つけ方、障害者雇用専門の求人を探す方法について詳しく解説します。
転職を視野に入れるべきタイミング
転職を検討するべきかどうか、判断が難しいと感じることもあるでしょう。
しかし、以下のような状況が続いている場合は、新しい職場を探すべきタイミングかもしれません。

転職を考えるべき状況
- 合理的配慮を求めても対応されず、働きづらさが解消されない。
- 職場の人間関係が悪化し、精神的に大きな負担を感じるようになった。
- 配慮不足のため、体調が悪化し、仕事を続けるのが困難になってきた。
- スキルアップや昇進の機会がなく、将来のキャリアに不安を感じる。
- 給与や待遇が低く、生活が厳しくなっている。
このような状況が長く続く場合、無理に今の職場にしがみつくよりも、自分に合った職場を探した方が、将来的にプラスになる可能性が高いです。
配慮ある職場との出会い方
転職を考えたとき、次の職場が本当に配慮のある職場なのかを見極めることが重要です。
「次の職場でも、同じように配慮が足りない環境だったらどうしよう…」
このような不安を抱えている方も多いと思います。
しかし、事前にしっかり情報収集を行い、障害者雇用に積極的な企業を探すことで、より働きやすい環境に出会うことが可能です。
配慮のある職場を見つける方法
| 方法 | 具体的なポイント |
| 企業の障害者雇用の実績を調べる | 企業の公式サイトや採用ページで、障害者雇用の実績や取り組みを確認する。 |
| 口コミサイトやSNSを活用する | 実際に働いた人の意見を参考にし、職場環境や配慮の実態をチェックする。 |
| 障害者向けの転職エージェントを利用する | 専門のキャリアアドバイザーが、障害者に配慮のある企業を紹介してくれる。 |
| 就労支援機関のサポートを受ける | ハローワークや障害者就業・生活支援センターに相談し、職場探しのアドバイスを受ける。 |
例えば、企業の採用ページに「障害者雇用に力を入れています」と書かれていても、実際の職場環境が伴っていない場合もあります。
そのため、転職エージェントを活用して「本当に配慮のある企業か」を確認しながら転職活動を進めるのが安心です。
障害者雇用求人の探し方
「どうやって自分に合った求人を探せばいいの?」
障害者雇用の求人を探す際は、専門の求人サイトや支援機関を活用することで、より効率的に希望に合った仕事を見つけることができます。
障害者向けの求人を探す方法
| 方法 | 特徴・メリット |
| ハローワークの専門援助部門を利用する | 障害者向けの求人情報を提供し、職業相談も受けられる。 |
| 障害者雇用専門の求人サイトを活用する | 障害者向けの求人が豊富で、企業の配慮内容も詳しく掲載されている。 |
| 障害者向けの合同企業説明会に参加する | 企業の採用担当者と直接話し、職場環境や配慮の有無を確認できる。 |
特に、障害者雇用専門の求人サイトを活用すると、合理的配慮が充実している企業をスムーズに探せるので、一般の求人サイトよりもミスマッチが少なくなります。
「スグJOB」で自分に合った職場を見つける
障害者向けの求人を探すなら、障害者雇用専門の転職サイト「スグJOB」を活用するのがおすすめです。
「スグJOB」を利用するメリット
- 障害者雇用に特化した求人が多数掲載されている。
- 企業の配慮内容やサポート体制が明記されているため、働きやすい職場を見つけやすい。
- 転職アドバイザーがサポートしてくれるため、適切な求人を紹介してもらえる。
「次こそ、自分に合った職場で安心して働きたい…」
そう思ったら、まずは「スグJOB」で求人をチェックしてみることをおすすめします。
もし今の職場で「働きづらい…」と感じているなら、「もっと自分に合った職場があるはず」と考え、一歩踏み出してみることが大切です。
まとめ
障害者雇用における配慮不足は、働く上での大きな課題となり、職場定着率の低下や障害者の負担増大につながる深刻な問題です。
「自分の障害に合った配慮を受けられず、仕事を続けるのがつらい…」
「職場で理解されていないと感じることが多く、どうすればいいのかわからない…」
そんな悩みを抱えている方も少なくないはずです。
しかし、企業側の意識改革や支援機関の活用によって、適切な合理的配慮を実施することは十分に可能です。
企業と障害者の双方が歩み寄り、適切な環境を整えることで、働きやすい職場を作ることができます。
もし現在の職場で「何度相談しても配慮が得られない」「働きにくさが解消されない」と感じている場合は、転職を視野に入れ、新たな職場を探すことも一つの選択肢です。
「スグJOB」のような障害者雇用専門の転職サイトを活用することで、障害者雇用に理解のある企業と出会える可能性が高まります。
「今の職場では難しいかもしれない…」と感じたら、ぜひ一歩踏み出して、より働きやすい環境を見つけてみてください。

スグJOBは求人数トップクラス!
障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ
障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ
この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。










