就労移行支援の給料や工賃について徹底解説!就労継続支援との違いも紹介
就労移行支援とは、障害のある方が一般企業への就職を目指すための福祉サービスです。
このサービスでは、就職活動のサポートや仕事に必要なスキル習得の機会が提供されます。
例えば、履歴書の作成や面接練習、ビジネスマナーの指導など、さまざまな支援を受けることができます。
ただし、就労移行支援では給料や工賃の支給は原則ありません。
そのため、利用を検討する際には、収入がない期間の生活費の確保や、支援期間終了後の働き方について、あらかじめ計画を立てることが重要です。
この記事では、就労移行支援の仕組みや給料・工賃の有無について詳しく解説します。
また、就労継続支援との違いについても触れながら、自分に合った制度の選び方について考えていきます。
就労移行支援を活用することで、自分の強みを活かし、長く働ける環境を見つけるための第一歩を踏み出せるかもしれません。
本記事がその手助けになれば幸いです。
就労移行支援とは
就労移行支援は、障害のある方が一般企業での就職を目指すための制度です。
「働きたい」という気持ちはあっても、就職活動に不安を感じる方も多いかもしれません。
そんな方のために、就労移行支援では就職に向けた準備や支援を行っています。
職業訓練を受けながらスキルを身につけたり、履歴書の書き方や面接対策を学んだりすることで、自信を持って就職活動に取り組めるようになります。
この制度は、厚生労働省が定めたものであり、最長2年間の利用が可能です。
特別な理由がある場合にはさらに1年間の延長が認められることもあります。

就労移行支援サービスの内容
求職活動に関する支援
就労移行支援では、履歴書の書き方や面接対策など、求職活動に関するサポートを受けることができます。
例えば、企業ごとに異なる面接のポイントや、自己PRの方法を学びながら、実際の就職活動に役立つ実践的なアドバイスを受けられます。
また、希望する職種や自分の強みを整理し、より自分に合った職場を探すためのサポートも行われます。
就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練
仕事に必要なスキルを身につけるため、事業所ごとにさまざまな訓練が提供されています。
- パソコン操作(Word、Excelなど)
- ビジネスマナー(敬語、電話対応、メール作成)
- 職場での円滑なコミュニケーションスキル
これらのスキルを身につけることで、就職後の実務に適応しやすくなり、安定した職場定着につながることが期待されます。

利用者の適性に応じた職場の開拓
就労移行支援では、利用者の特性や希望に合わせた職場探しのサポートも重要な役割の一つです。
企業見学や実習の機会を提供することで、職場の雰囲気を事前に知ることができ、就職後のミスマッチを防ぐことができます。
また、事業所によっては、特定の企業との連携を強め、利用者に合った就職先を紹介することもあります。
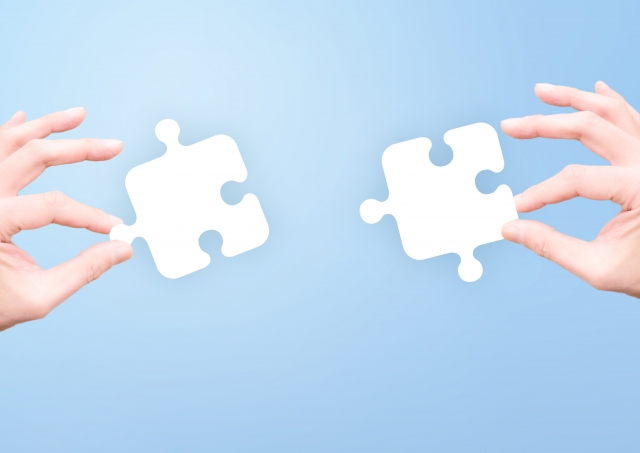
就職後における職場への定着のための相談や支援
就職後も、安心して働き続けられるように、事業所の担当者が定期的にフォローアップを行うことがあります。
職場でのコミュニケーションがうまくいかない場合や、仕事の進め方に悩んだ際には、相談できる窓口があることで精神的な負担を軽減することができます。
また、必要に応じて、企業と利用者の間に入って調整を行うことで、長期的な就労継続をサポートします。
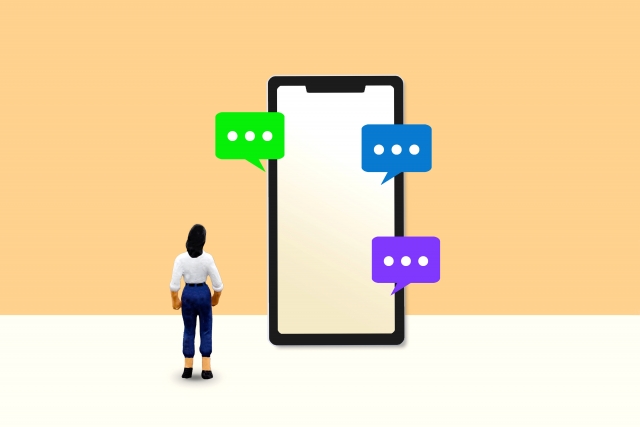
就労移行支援の給料や工賃などの基本賃金について
就労移行支援を利用する際、給料や工賃が支給されるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
一般的な雇用とは異なり、就労移行支援は職業訓練を目的とした制度であるため、基本的には給与の支給はありません。
しかし、就労継続支援などの他の制度と比較すると、働き方や収入面で違いがあることが分かります。
ここでは、就労移行支援における給料や工賃の考え方を詳しく解説し、利用を検討する際に役立つ情報をお伝えします。
工賃とは
工賃とは、障害のある方が福祉的就労を行う際に受け取る報酬のことです。
一般的な給与とは異なり、労働契約に基づくものではなく、生産活動の対価として支払われる点が特徴です。
そのため、最低賃金の適用はなく、事業所によって金額に差があるのが現状です。
就労移行支援事業所では原則的に工賃の支払いはない
就労移行支援は、就職に必要なスキルを身につけるための訓練が目的となるため、工賃や給料の支給は基本的にありません。
労働契約を結ぶ形ではなく、職業訓練の一環としてカリキュラムが組まれているため、給与が発生しない仕組みになっています。
従って、工賃の支給は行われず、利用者は訓練生として位置付けられます。
これは、訓練の質を重視し、利用者がスキルアップに専念できるようにするためです。
そのため、収入を得ることを目的とする場合は、就労継続支援の利用を検討しましょう。
例外ケースもある
一部の事業所では、就労移行支援の利用者が実際の作業を通じてスキルを磨く場合、作業報酬や成果報酬が支払われる場合があります。
例えば、事業所内での簡単な組み立て作業や包装作業など、実際の労働に近い形で訓練が行われる場合です。
工賃が支給される場合、その条件と金額は事業所によって異なります。
一般的に、工賃支給の条件には、作業の種類や難易度、利用者の作業能力などが考慮されます。
これにより、利用者は実際の労働の流れや責任感を体感し、将来の就労に向けた準備をより実践的に行うことができます。
ただし、上記は一部の例外であり、金額も数百円~数千円程度と限られるのが一般的です。
工賃の支給を期待して就労移行支援を利用すると、想定と異なることがあるため、利用前にしっかり確認することが大切です。
就労移行支援の利用料(費用)について
就労移行支援を利用する際に気になるのが、利用料(費用)です。
この支援制度は、公的な福祉サービスの一環として提供されており、基本的には利用者の世帯収入に応じて負担額が決まります。
利用料の仕組み
利用料の負担は、前年度の収入を基準として、以下の4つの区分に分かれています。
| 区分 | 負担額 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(世帯年収670万円以下) | 最大9,300円/月 |
| 上記以外 | 最大37,200円/月 |
このように、多くの方が無料または低額の負担で利用できるように設計されています。
自己負担額の確認方法
具体的な負担額は、お住まいの自治体や施設によって異なることがあるため、事前に確認することが重要です。
また、一定の条件を満たす場合には、減免措置が適用されたり、通うためにかかる交通費の助成を受けられる場合があります。
対応はお住まいの自治体によって異なる場合があります。
詳細な負担額は自治体の福祉窓口や、利用を検討している就労移行支援事業所に問い合わせて確認しましょう。
費用が発生しても利用する価値はある?
就労移行支援は、職業訓練や就職活動のサポートが受けられる制度です。
スキルを習得し、適職を見つけるための支援を受けられるため、たとえ費用が発生する場合でも、長期的な視点で考えると非常に価値のある制度といえるでしょう。
自分にとって最適なサポートを受けるために、費用面も考慮しながら計画を立てることが大切です。
就労移行支援と就労継続支援の違い
就労移行支援と就労継続支援は、どちらも障害のある方が働くための支援制度ですが、それぞれの目的や支援内容には大きな違いがあります。
就労移行支援は、一般企業での就職を目指すための訓練や支援を提供する制度であり、一定期間の訓練を経て一般就労を目指します。
一方、就労継続支援は、一般就労が難しい方に向けて、福祉的就労の場を提供し、働く力を養うための制度です。
この章では、就労移行支援と就労継続支援の違いを詳しく解説し、それぞれの制度の特徴や利用のポイントについてご紹介します。
ご自身にとってどちらが適しているのかを考える際の参考にしていただければと思います。

就労継続支援とは
就労継続支援は、一般企業で働くことが難しい方に対し、就労の機会を提供し、働く力を育む福祉サービスです。
この制度は、障害のある方が自分のペースで働ける環境を整え、社会参加を支援することを目的としています。
就労継続支援にはA型とB型の2種類があり、それぞれ働き方や賃金の仕組みが異なります。
就労継続支援A型事業
- 雇用契約あり
- 最低賃金が適用される
- 一般就労に近い環境で働ける
- 企業と直接雇用契約を結ぶため、安定した給与を得られる
A型は、企業などと雇用契約を結び、一定の労働時間の中で仕事をする仕組みです。
そのため、地域ごとに定められた最低賃金以上の給与が支給され、安定した収入を得ることができます。
また、A型事業所では、労働時間や労働条件も法律に基づいて管理されるため、利用者は安心して働くことができます。
一般企業での就労を視野に入れながら、継続的な支援を受けられる点も特徴です。
就労継続支援B型事業
- 雇用契約なし
- 工賃として報酬を受け取る
- 自分のペースで働ける
- 体調やスキルに応じた柔軟な働き方が可能
一方、B型は利用者の体調や能力に応じて無理なく働けるのが特徴です。
就労継続支援B型の利用者は、雇用契約を結ばないため、労働基準法に基づく最低賃金の適用はありません。
作業を行うことで工賃が支払われるため、働く経験を積む場として活用できます。
また、就労の負担を抑えながら、スキルを磨き、次のステップを目指すことが可能です。
就労継続支援なら給与や工賃が受け取れる
A型は給与が支払われ、B型では工賃を受け取ることができます。
A型は安定した収入が得られる一方で、一定の労働時間をこなす必要があるため、体調管理が求められます。
B型は、自分のペースで働けるため、無理なく長く続けることができる反面、収入が少なくなる傾向があります。
そのため、収入を得ながら自分に合った働き方を探したい方にとって、有力な選択肢となるでしょう。
どちらの制度が合っているかは、自分の体調や生活リズム、働き方の希望を考慮して選ぶことが大切です。
また、将来的に一般企業での就職を目指す場合は、A型を経由してスキルを積むのも一つの方法です。
就労継続支援は、安定した環境で働きながら、自分に合った働き方を見つけられる制度です。
自分にとってどの選択肢が最適かを考えながら、納得のいく決断をしましょう。
就労継続支援と一般就労どちらを選択するのか
自分に合った働き方を見つけることは、長く安定して仕事を続けるためにとても大切です。
就労継続支援と一般就労のどちらを選ぶべきかは、現在の状況や体調、将来の目標によって異なります。
無理なく働ける環境を選ぶことで、自信を持って仕事を続けることができます。
この章では、それぞれの働き方の特徴を整理し、自分に合った選択をするためのポイントを解説していきます。
自分のフェーズにあった選択をしよう
仕事を探すときは、現在の自分の状況や将来の目標をしっかり考え、適切な制度を選ぶことが大切です。
就労移行支援は、一般企業での就職を目指してスキルを身につけることが目的です。
一方、就労継続支援は、無理なく自分のペースで働きながら経験を積むことができる制度です。
どちらが自分に合っているのか、ライフスタイルや健康状態を考慮しながら検討しましょう。
スグJOB障害者は障害者雇用求人専門の求人サイトです
「スグJOB障害者」は、障害者雇用に特化した求人情報を掲載している専門のサイトです。
自分に合った働き方を見つけるために、さまざまな求人を比較しながら情報収集を進めることができます。
障害者雇用の仕事を探している方は、ぜひ活用してください。
まとめ
本記事では、就労移行支援の給料や工賃について詳しく解説しました。
就労移行支援は、一般企業への就職を目指すための制度であり、職業訓練を通じてスキルを身につけることができます。
しかし、基本的には給与や工賃の支給はなく、利用する際には経済的な面も考慮することが大切です。
一方で、就労移行支援を活用することで、働くための知識やスキルを習得でき、将来的に安定した就労につなげることができます。
この制度は、企業の採用担当者と連携したサポートや、個々の適性に合った職場探しの支援が充実しており、長期的にキャリアを築いていくための有益な選択肢となります。
また、就労移行支援は、一般就労を目指す方に向けた制度であるため、自分の状況や将来の希望に応じて、最適な支援を選択することが重要です。
一方、収入を得ながら働くことを優先する場合は、就労継続支援を選択するのも一つの方法です。
どの制度を利用するか迷ったときは、自身の体調や働き方の希望、サポートの内容を考慮しながら決めることをおすすめします。
本記事の内容を参考に、無理なく働ける環境を見つけ、自分に合った就職活動を進めていきましょう。

スグJOBは求人数トップクラス!
障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ
障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ
この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。










